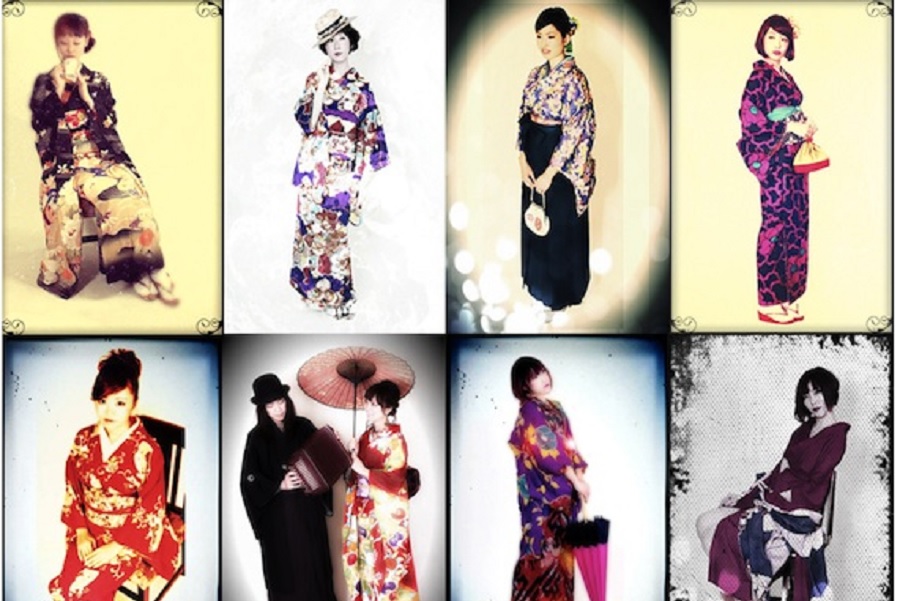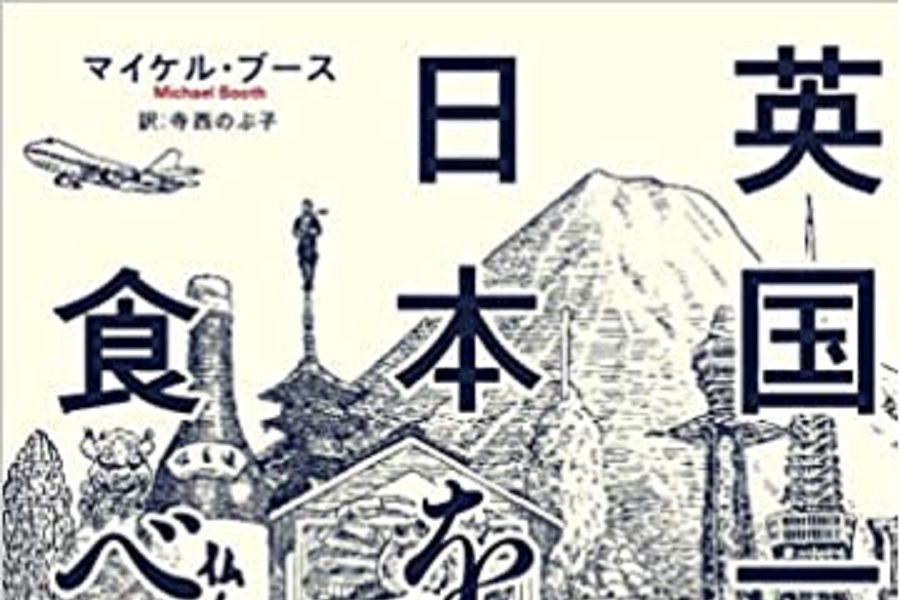和の心 古の思いは一つ

ありがたき!
こんにちは。
後醍醐天皇に「建武日中行事」という著書があります。
この本によって、後醍醐天皇の日々の職務のあらましが知られます。
そこに「石灰(いしばい)の壇」における「毎朝御拝(まいちょうごはい)」のことが記されています。
どんなことなのでしょうね。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
両段再拝
天皇は、朝お起きになると、まず伊勢の神宮を拝まれる。
それに先立って潔斎がなされます。
潔斎がお済になると、正装され、整髪され「石灰の壇」に出られます。
そして、「石灰の壇におはしまして御拝あり」と同書に記されています。
「石灰の壇」に進まれたの後、「辰巳に向かひて両段再拝。そのほか御心にまかすべし」と記されています。
辰巳、すなわち東南の方向に向かって「両段再拝」つまり拝を二度されます。
この本は後に天皇になられる方のために書き送ったものであり、そこで、これ以外のことはその天皇のご自由であるが、「両段再拝」だけは「石灰の壇」にお出ましになった以上、必ずそうさられなければならないと書かれているのです。
この「毎朝御拝」について、以下、谷省吾皇學館大学名誉教授がその著書「神を祭るの中で紹介された記載をもとに要点を記します。
順徳天皇の「禁秘抄」に「清涼殿の帳の北より石灰の壇に着す・・・・・神宮、内侍所以下御祈誓」をと記されていて、単なる方角としての辰巳ではなく、辰巳方角にある「神宮、内侍所」を拝んでいらっしゃるということが知られています。
その拝まれる場としての「石灰の壇」がどのような構造物、たとえば中国の天壇のように、天に近づくための高い壇なのか、逆に、下に壇があって、そこへ下りていかれるのであるか、どちらであるかということについては、大石千引の「日中行事略解」に「南の二間、石灰の壇也」とあって、「此間、地下(じげ)に准じて御拝あり。石灰の壇は石灰をもて是をぬるゆゑの名か」記されていて、地面に准じるわけであるから、一段下の壇に下りて拝礼されるのであります。
「石灰の壇」は、現在の京都御所にもあり、漆喰で塗り固められた一段低いところでありますが、そこから「神宮、内侍所」を拝まれるのであります。(文:白山芳太郎・「日本人のこころ」より)
ありがとうございます
毎朝毎朝、古の時より欠かすことなく続いている御拝。
神さまを、ご先祖さまを、そして国家安泰を拝まれていらっしゃるのでしょうね。
本当に本当にありがたいことです。
だからこそ、世界に類を見ないすてきな国なのです。
自分のためではなく国家のため、みなさまのため。
私達に出来ますか?
感謝の気持ち以外なにもありません。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld