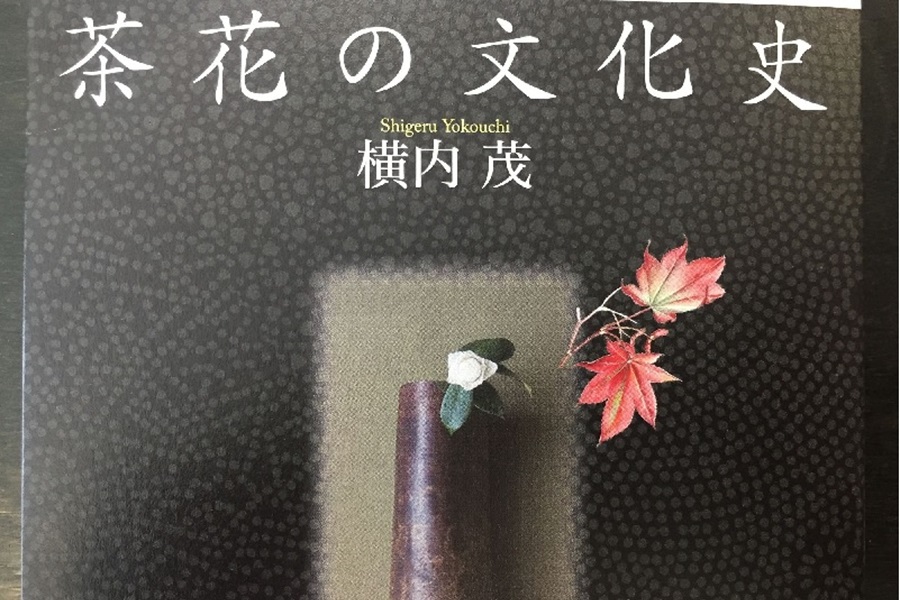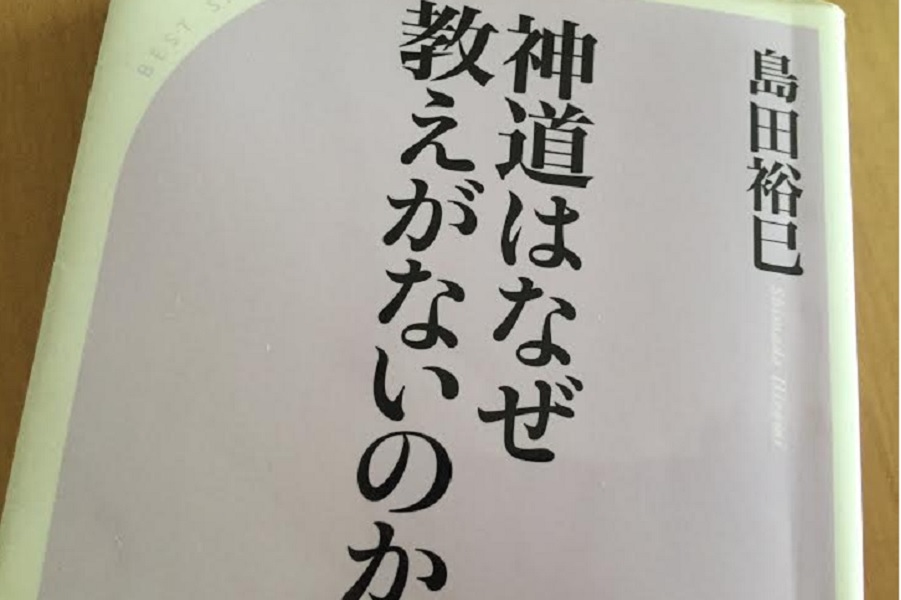刺青の歴史は深い!その情報についてご紹介

刺青、時代と共に
こんにちは。
刺青の歴史はとても古いのですが、現代では社会的にあまり受け入れられていないものです。
日本の刺青は芸術的で海外ではとても評価が高く、美しいと言われています。
鮮やかな色彩とデザインが人の手で描かれていると思うと、職人の技術の高さを感じますよね。
しかし、時代の流れを経て、いつしか怖いイメージへと変化していきました。
世界では、氷河時代から刺青が施されている氷漬けのミイラが発見されています。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
土偶に刺青?
日本で発掘された土偶をみても、全体的に刺青のような模様を確認することが出来ます。
確かにじっくり見ると、腕や足などに模様がついている縄文時代の作品を目にしますよね。
洋服を着てお洒落を楽しむように、古代では体に刺青を入れてお洒落をしていたのでしょうか。
そして、獣や魔物から身を守るためだったとの説もあります。
「魏志倭人伝」にも記されているので、弥生時代には存在していたことが伺えますね。
顔に刺青を施した男性がいたと書かれていますが、身分の位を表すためのものだったのではないかとも言われていました。
刺青を彫る理由
皮膚を鋭利なもので傷つけ、墨や朱などで色をつけながら文字や絵を彫っていく刺青。
周囲の目に留まるものであり、一目でわかることから個別認識に用いられた説があります。
船の乗組員やいろいろな村から集められた兵など、どこの誰なのかをわかりやすくするために用いられたとも言われています。
沖縄の一部では、既婚女性には手に刺青を入れる習慣があったそうです。
地域によって、刑罰として体に刻むということも。
衣服を意識するようになると体を装飾する美意識が変化し、刺青の歴史も衰え始めていきました。
刺青が流行った江戸時代
江戸時代になると、犯罪が増え始め抑制するのが困難な事態へと突入します。
罪人の印として用いられたことから、刺青の歴史が変わり始めたのです。
罪人が増えて罰される度、目にする機会が増えていき、消えないものとして再認識されていきます。
鮮やかな色彩と芸術的な刺青は、仲間との絆を深めると感じた職人の間で、江戸中期に再び注目され始めました。
いつの時代でも、強さやカッコよさに憧れるものなのですね。
文身や彫り物
デザインも増えていき個性的なものが多くなった刺青の歴史は、まさに最高潮かのように広がっていったのです。
木版画家が彫っていたことから、木を彫る道具がそのまま使われていたため、とても痛かったと言われています。
罪人に入れられる刺青とは違うため、芸術度が高いものを「文身」や「彫り物」と変えて区別して呼ばれていました。
真夏の暑い日など、ふんどし一丁で仕事をする職人たちの間では、全身に彫る刺青の人気が高かったそうです。
しかし、金額も高く痛みを伴うことから、一般的に気軽に施術されるものとはいきませんでした。
近代化に伴い禁止へ
華やかな刺青の歴史は、明治政府によって禁止へと追い込まれていきました。
そして、見せる芸術としての刺青文化は、海外の近代文化を取り入れようとしている時代には、受け入れられない物へとの価値観へと変わっていったのです。 芸術作品としての技術は世界的にも評価が高く、海外から彫り師に日本へ来た記念にと、刺青を依頼して彫ってもらうケースが続いたと言います。
国内では刺青禁止令が出されたこともあり、それでも彫り続ける者に対して反社会的と捉える見方が強まったため、任侠とのイメージが定着していきました。
ありがとうございます
刺青の歴史は、日本人の繊細な職人技によって日本らしい文化を築き上げました。
しかし、かっこいいと絶賛する人もいれば怖くて野蛮だと非難する人もいて、庶民に定着した文化とはいかなかったのは言うまでもありません。
彫り師はその後、活躍の場を海外へと移した人も多くいたそうです。
賛否はありますが刺青の歴史を知ることで、今まで抱いていたイメージとは違う、日本の伝統が詰まっている芸術のひとつだということに気付かされますね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
日本伝統の飴アート これ本当に飴?もったいなくて食べられない。
伝統工芸を学びたいと一般人が思う5つの時
日本の伝統文様 「菱」
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld