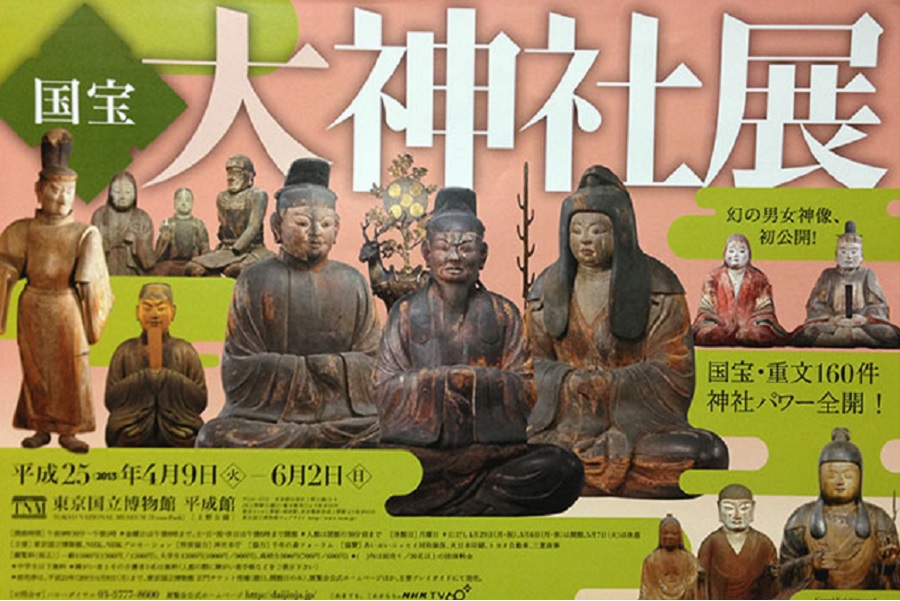「神ながら(かんながら)」の国

神と仏の出会う国
こんにちは。
「秋台風」がこの週末、日本上陸してきそうですね。
みなさま十分にお気を付けください。
日本にはこのように四季折々、美しいことや災害をもたらす事、いろいろありますが、すべてが神のはからいかもしれません。
古来より「ありがとうございます」と尊厳と畏怖を併せ持ってのこのことば、自然とともに大切に過ごしてきた「神ながら」の思いの中から生まれた言葉かもしれませんね。
今日は、鎌田東二先生の「神と仏の出会う国」から「神ながら」を学んでみたいと思います。
それではご一緒に。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
「神ながら」とは
万葉歌人を代表する柿本人麻呂は「万葉集」の中で、わが国の特質を「神ながら 言挙げせぬ国」(「神在随時挙不為国」第十三巻三二五三)と歌っています。
葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国 然(さ)れども 言挙げぞ我がする 事幸(さき)く 真幸くませと 恙(つつみ)なく 幸くいまさば 荒磯(あらそ)波 ありても見むと 百重(ももへ)波 千重(ちへ)波しきに 言挙す我れは
(反歌)
磯城島(しきしま)の 大和の国は 言霊の 助くる国ぞ 真幸くありこそ
柿本人麻呂は遣唐使に派遣される者に対して「葦原の 瑞穂の国」、すなわち日本の特質を「神ながら 言挙げせぬ国」と称えつつも、そうした言挙げしない国の文化の中であえて自分はあなたが長旅ご無事でありますようにと「言挙げぞ我がする」と祈り、帰還して再び会えることを口にしました。
このとき、反歌に歌われているように、「言挙げしない」ということは、口に出したことが必ず実現するという「言霊」信仰と裏腹であることが表明されています。
つまり、大和と呼ばれる日本の国は「言霊の助くる国」なのだという強い信念がうかがえます。
それは別の言い方をしますと、日本は中国のような「理の国」ではなく、「歌の国」であり、「詩の国」であるという自己認識の表明であります。
「言挙げしない」とは事々しく言葉で言い立て理屈を述べ立てないという意味ですが、そのことは、日本の伝統文化および「神道」が日本にとって、言葉に表さなくてもおのずから心は通じ(のちに「以心伝心」という言葉にも結びつきます)、「道」が通じているのだと理解されていたからです。
「神ながらの道」とは
このように、「神道」とは、「神ながら」と表現されたように、ユーラシア大陸の東の果てにある日本列島の風土の中でおのずと醸成され、外来思想や外来文化の影響を受けながら歴史的に形式化され、洗練されてきた日本列島民の信仰と生活の作法・流儀であります。
それは「カミ(神)」と呼ばれてきた聖なる存在に対する畏怖・畏敬の念に基づく祈りと祭りの伝統的な信仰体系であり、生活体系です。
「神道」は日本人が存在世界、すなわち宇宙万物の偉大さや尊厳を感じ取り、それに慎ましく感応してきた道の伝承体系であります。
それゆえ、「神道」には、日本人の宇宙の神聖さの感じ方が折りたたまれ、宇宙万物への祈り方、祀り方が織り込まれています。
神道はユーラシア・環太平洋古祭祀文化の上に形成されていますが、「神道」が具体的にこのような形態・形式・内容を持つに至ったのは、日本という風土と歴史があったからです。
その意味では「神道」は日本を離れて存在しえません。
「神道」を形容する語としての「神ながらの道」とは、「おのずからなる神のはたらきにしたがう生き方」とか、「神々の御心や御業のままに生きる道」という意味ではないでしょうか。
要するに、「神の意志に従う道」という意味です。
それは、「神からの道」すなわち「神々から子孫への恵みと生成発展の道」と、「神への道」すなわち「人々が神々へ感謝と信仰を捧げる祈りと祭りの道」と、「神との道」すなわち神人協働の三つのベクトルを内包しています。
その三方の道が立体交差し、交わるところに「神ながらの道」としての「神道」が息づいています。
これをまとめておきますと、「神の道」としての「神道」とは、
①「神(から)の道」(The Way from KAMI)
②「神(へ)の道」(The Way to KAMI)
③「神(と)の道」(The Way with KAMI)
という三つの道の立体交差路となります。
(文:本「神と仏の出会う国」著鎌田東二さんより)
ありがとうございます
「神々の御心や御業のままに生きる道」という「神ながらの道」。
古よりこの敷島の瑞穂の国の人びとは、すべてのことを神々の御心、御業と信じてきました。
それゆえに、すべてのことに感謝の心を持ち過ごしてきました。
現代において、このような心がどれほどあるのでしょうね。
いつのまにか「言ったもの勝ち」のように文句を言い、人のせいにして、自分というものの価値を損なってきたのではないでしょうか。
すべては自分の責任です。
それを当たり前としてきたから言葉に出さない、言挙げをせずにきたのでしょうね。
これからの時代、今一度日本人の美しい心を取り戻したいと思うのは私だけでしょうか。
この世界が平和で笑顔あふれる毎日を過ごせるのは、この「ありがとう」という和の心だけと思っています。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
これからも浄住寺ともども、宜しくお願いいたします。
参考
言挙げせず 和の心
日本人が決して失ってはいけないもの
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld