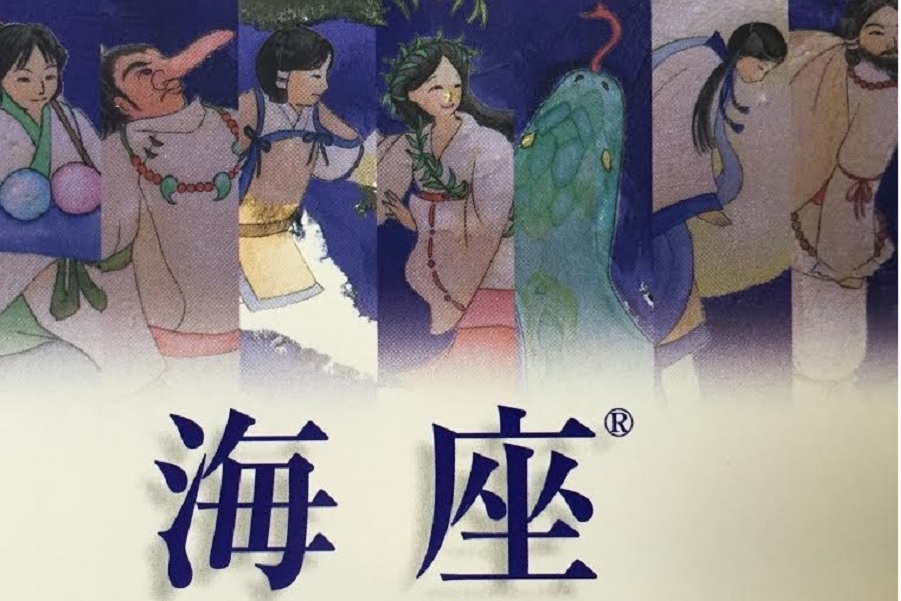歌舞伎のよこ道あるき♪第9回

「勧進帳」
南座で市川海老蔵特別公演を観てきました。
5月に十三代目團十郎白猿を襲名される海老蔵さん。
関西で海老蔵としての舞台はラスト。
その演目は、勧進帳でした☆
◆歌舞伎十八番
勧進帳は、市川團十郎家にとって大切な演目。
「歌舞伎十八番」とは、團十郎家のお家芸のことです。
勧進帳も歌舞伎十八番のひとつなんです。

これが、市川海老蔵特別公演のチラシ。
「勧進帳」の上に小さく、「歌舞伎十八番の内」と書かれています。
5月から歌舞伎座で始まる襲名演目にも
勧進帳が選ばれています!
海老蔵の締めくくり。
そして、團十郎になって最初に弁慶を演じる。
う~~~ん!
海老蔵さんの中で
勧進帳の大切度合いが、伝わってきます!
◆勧進帳って何?
そもそも、「勧進帳」って?
弁慶が読み上げる勧進帳には、何が書かれているの?
ピーンっと張りつめた緊張感の中、
堂々と読み上げていますが、
難しい言葉がいっぱいで、なかなか聞き取りにくいですよね?
演じる役者さんによって、若干異なりますが、
一例を挙げてみましょう!
大恩教主の秋の月は、涅槃の雲に隠れ、
生死長夜の長き夢、驚かすべき人もなし。
此処に中頃の帝おはします。
御名を聖武皇帝と申し奉る。
最愛の婦人に別れ、恋慕やみがたく、
涕泣眼に荒く、涙玉を貫く思いを、
善路翻し上救菩提のため、
廬遮那仏建立し給う
しかるに去んじ治承のころ、
焼亡し、終わんぬ。
かほど霊場絶えなむことを嘆き、
俊乗房重源、勅命をこうむって、
無常の観門に涙を流し、
上下の真俗を勧めて彼の霊場を、
再建せんと諸国に勧進す。
一紙半銭、奉財の輩は
現世にては無比の楽に誇り、
当来にては、数千蓮華の上に座せん。
帰命稽首、敬ってもうす。
勧進とは、仏と縁を結ぶように勧めること。
そこから、寺院建立や修繕の寄付を募ることにも使われます。
弁慶は、平家の南都焼き討ちで焼失した
東大寺再建のための勧進(寄付集め)と偽って関を通ろうしたのです。
「じゃぁ、ちゃんと勧進帳持ってるよね?」
一気に緊張感の増す、この場面。
関守の富樫。
この方、めちゃめちゃ信心深い人だったんです。
弁慶の読んだ勧進帳に心動かされちゃった。
ちょっと聞いてみたかった、
山伏の不思議もスッキリ解決!
関を通ることを許可するだけじゃなく
自分も東大寺再興のために、布施持を渡します。
良い人~!

これが、弁慶の衣装。
ふつうのお坊さんとは、全然違います。
富樫じゃなくても、ナゼ? ナゼ? が、いっぱい!
それにしても、関所で急に勧進帳を読めと言われて
この返し。
命を懸けた大芝居!
凄すぎませんか?
もちろん、手に持っている巻物はただの巻物。
弁慶にしたら、想定内だったのかしら?
◆東大寺の勧進
ちょっと、ここで史実を整理。
1180年 平家の南都焼き討ちで東大寺は焼失
1181年 後白河法皇が、東大寺再建のため僧重源に勧進を命じる
1185年3月 壇ノ浦の戦いで平家滅亡
1185年4月 頼朝、義経対立
1185年8月、東大寺の大仏開眼供養
1185年11月 後白河法皇が、義経追討令を出す
ここから、義経の逃亡生活が始まります。
西国、吉野、京を転々として、京から奥州へ目指したのは1187年2月。
ん?
1185年の8月に東大寺の大仏開眼供養が行われてるのに
東大寺の再建のための勧進なんて、おかしい?
いえいえ、大仏殿建立は1195年。
まだ、勧進活動は継続されていました。

義経追討令を出した、後白河法皇、源頼朝も大きくかかわる東大寺再興。
誰もが知る長期の国家事業。
自分達を捕らえようとしている人達を逆に利用してしまうなんて
弁慶、さすが!
海老蔵さんのラスト勧進帳をご覧になった方も、見逃した方も
新團十郎さんの勧進帳を楽しみに待ちましょう!
2020(令和二年)如月 安積美香
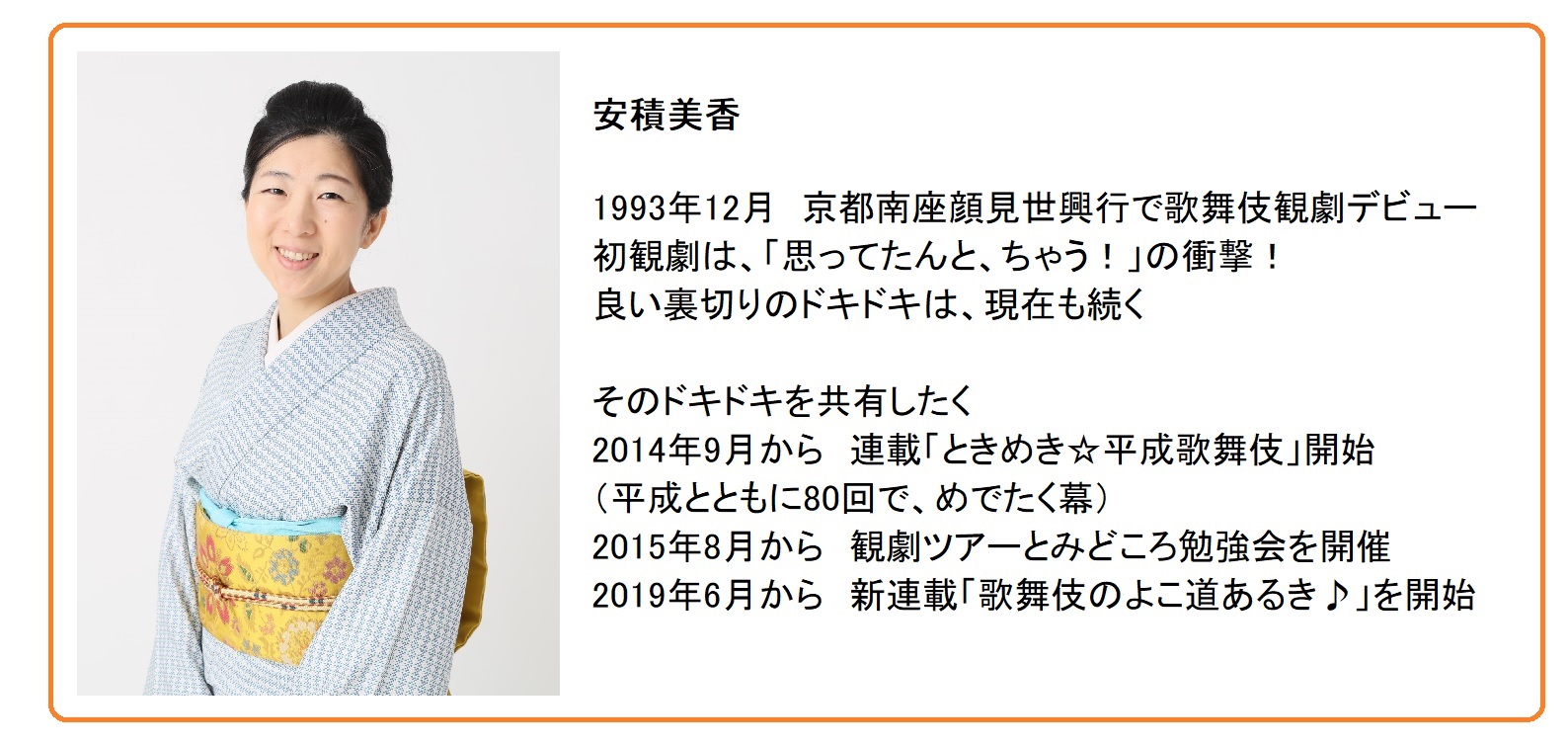
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World