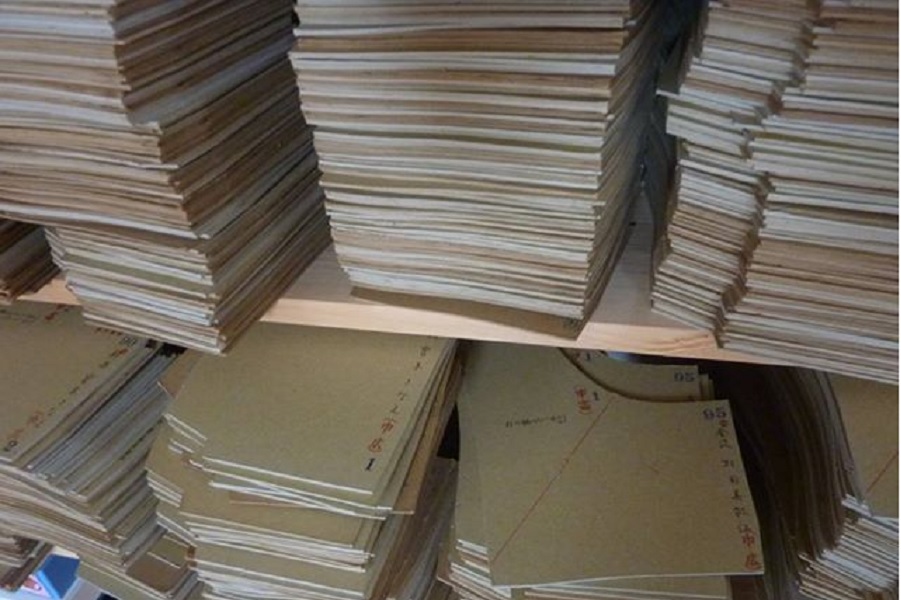しめ縄は神聖な場所を示す印

「しめ縄」をつくりませんか
こんにちは。
師走のあわただしい毎日。
今年中にしなければと思う事がいっぱい。
思えば思うほど焦ってしまう毎日です。
こんな時期に多く行われるのは「しめ縄作り」のワークショップ。
私も三年前に作りましたが、それ以来作ってなくて今年はと思いながら予定が合わず・・・残念。
来年はちゃんと準備して浄住寺で作りたいです。
FBでもさまざまなワークショップがありましたかご紹介しますね。
お時間ありましたら、是非とも作っていただきたいです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
しめ縄は、どうして正月にお家の入り口に飾るの?
昨日、注連縄を作りました。(すいません、2015年の記事です。)
藁の束を3本つくり、それぞれを時計回りと反対によって、次にその2本を時計回りによって、残りの1本をまたよって作りました。
(わかるかな?)
簡単そうで難しい。
でも、横で子供たちも楽しそうに作ってました。
しめ縄の締め方は、中途に七本、五本、三本の縄を通してぶら下げる七五三掛けでおこなわれることから、「七五三縄」とも呼ばれるそうです。
さて、注連縄と言えば出雲大社の注連縄を思い出してしまいますが、なぜ正月に家でも注連縄を飾るのでしょうか。
しめ縄の由来は、「天の岩戸に隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)を岩を引き明けて連れ出して、天照大神のまわりに『しりくめ縄』を引きめぐらした」という神話がきっかけだと言われています。
しめ縄は『しりくめ縄』=『しめ縄』と略されたもので、他にも『注連(しめ)縄』,『標(しめ)縄』とも書かれ一命を『しめ飾り』とも言います。
しめ飾りに使用される縄は、その境界内の出入禁止のしるしの役割。
これを飾る事によってその中は清浄な区域だと示して、わざわいをもたらす悪い神を寄せ付けないようにと使用されています。

正月は歳神さまをお迎えする行事
そもそも正月行事というのは、歳神さまという新年の神さまをお迎えするための行事です。
歳神さまは家々にやってきて、生きる力や幸せを授けてくださると考えられています。
そこで、お正月が近づくとしめ縄やしめ飾りを施し、年神さまを迎える準備をします。
だからお家の門に注連縄をつけるのですね。
また、しめ飾り(注連飾り)というのは、しめ縄に縁起物などの飾りをつけたものをいいます。
代表的なのが、神様の降臨を表す「紙垂」(かみしで/しで)、清廉潔白を表す「裏白」、家系を譲って絶やさず子孫繁栄を願う「譲り葉」、代々栄えるよう願う「橙」などです。
もともとは、神社がしめ縄を張りめぐらせるのと同じ理由で、自分の家が年神様をお迎えするのにふさわしい神聖な場所であることを示すために始まったといわれています。
しめ縄やしめ飾りを施すことで、その内側が清らかな場所となり、年神様が安心して降りてきてくださるわけですね。
さて、自分でつくって注連縄に縁起物つけなければ。

しめ縄を付ける日?外す日?
年末のあわただしい中、せっかく作ったしめ縄、さて、いつ飾ったらいいのでしょうね。
歳神さまを迎えるためですから、遅くても28日までには飾りましょい。
ご存知のとおり、29日は「苦」に通じるので避けてくださいね。
また、大晦日、31日は「一夜飾り」といわれ葬儀と同じなので、神さまに失礼なので避けましょう。
昔、お正月は松の内までは飾ってました。
元々、松の内は15日までを指してましたが、11日の鏡開きの時にまだ門松を飾っているのはおかしいと神さまがお帰りになる7日に外すことが多くなりました。

ありがとうございます
いかがだったでしょうか。
しめ縄とは、神さまと深く関係のある縁起物です。
もちろん、ちゃんとした理由を知らなくて、しめ縄を飾ってお正月をお迎えしていただいても結構です。
しかし、由来や意味について知ることで、新年を迎える気持ちが改まるのではないでしょうか。
何事も、古よりの伝統の意味を知ることで、より真摯な態度で向き合えるようになると思います。
伝統的な行事というのは、長年、私たちの祖先が積み重ねてきた事。
私たちも、そしてこれからの未来を担う子供たちも、きちんとした意味を知ることはとても大切なことと思います。
今の時代、お家でも、学校でもそのようなことを教えてくれる場所でなくなっただけに、どこかで、誰かが語り継がないといけないですね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
年末年始、伝統行事の多いときです。
いつから?どうして?と、調べていくのと楽しいかもしれませんよ。
(旧文2014.12.15 再編集)
参考
しめ縄飾りワークショップ
古代米のしめ縄飾り 〜農とつながる手仕事
古代米を使ったしめ飾り作り
注連縄の原点は「蛇」
お節料理 大好きな私 楽しみ!
「おせち」
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld