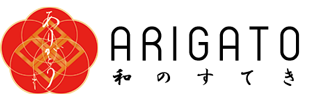500年の時を超えて愛される「日本酒」

醸造文化を後世に残す
こんにちは。
灘五郷の名手『剣菱』は、戦国時代から500年以上も続く清酒ブランド。
江戸時代には“酒”と書けば“ケンビシ”と読まれるほど、日本酒の代名詞的存在であったそうだ。
剣菱ブランドは、長い歴史のなかで数々の戦争や震災などの荒波に揉まれながら、現在までに4回酒造家が変わっています。
しかし、いずれの酒造家たちも、剣菱ブランドと味を守り続けてきました。
その企業精神に触れ、持続可能社会におけるあり方を考えてみたいです。
とまった時計であり続ける覚悟
「とまった時計であれ」。
これは剣菱酒造株式会社の先代(2代目)社長・白樫政一の訓えである。
時世のはやり廃りに合わせようと時計のスピードを変えれば、1日中針が正しい時間を示すことはない。
しかしとまった時計は必ず1日の中で2回は正しい時間を指す。
変わらぬ味にこだわれば、時代が変わっても求める人がいるという意味だ。

お米の風味をしっかりと
剣菱の変わらない味のこだわりは、“お米の風味をしっかり注ぎ込む”ことにある。
酒米を研いで造る吟醸酒のように香りの高い製品も造れないことはないのだが、剣菱らしい味にこだわっている。
現在は、原料の酒米づくりからこだわり、兵庫県内で栽培する山田錦と剣菱専用の愛山を使用。
酒蔵の仕事は、午前3時から酒米を木製の甑で蒸す仕事から始まる。
麹室では2日ほどかけて強い麹菌を繁殖させる。
空気中の天然乳酸菌により乳酸を造り、そこに蔵付酵母が増えることにより、有害な菌に負けない強い酒母造り(酵母を増やす工程)を行う。この工程では、低温でゆっくり繁殖させるため、暖気樽といわれる桶に湯を入れ、酵母を育てるタンクに入れて温度を調整する。
醪造りは、酒母に米と麹、井戸水(灘の宮水)を3段仕込みで、約1ケ月間かけて発酵。
早いものでも一夏を越してから製品にし、製品によって2〜8年、5〜15年貯蔵したものをブレンドして味を整える。
こうした作られた酒は、深みのある香りや味わいに醸される。
醸造文化を後世に残すために
一見、昔ながらの道具や製法にこだわっているようだが、剣菱のこだわりは“変わらぬ味”にある。
味に影響せず、より衛生的にできるように、ホーロー性のタンクにするなど近代化も図っている。
しかし、変わらぬ味を守るために変えられないものもある。
例えば、機械化もできるが長年の経験や的確なタイミングを判断する杜氏の仕事。
また、木製道具にこだわるのは、余分な水分を吸い込んで蒸し具合を安定させたり、時間をかけて温度や湿度をコントロールする上で適しているからだ。
今ではこうした木製道具をつくる職人もごくわずか、原料を探すのも苦労が多い。
暖気樽を作る職人が日本で一人となった時、日本の醸造文化の将来に危機感を覚え、社員として雇用し、また後継者の育成にも取り組んでいる。
現在はその樽の原料となる木を入手するところから取り組み、暖気樽は同業他社にも提供されている。
神淡路大震災で被災した際には、8つあった蔵は7蔵が倒壊し、3年の歳月をかけて3蔵を再建した。
被災直後の絶望感は計り知れない。
その気持ちを奮い起こしたのは、様々な人が500年以上も守ってきた普遍の味と剣菱のブランド、さらに醸造文化を次世代に繋がなければ、という使命感だったのではないだろうか。
電子レンジ対応の「黒松剣菱180ml瓶」。
日本産業デザイン振興会主催の「2008年度グッドデザイン賞」を受賞した。
持続可能な事業は、伝統をただ守るだけでは成立しない。
例えば、このボトルはレンジで加熱対応だ。
レンジ加熱は温度にムラができやすいが、このボトルは対流する構造でよい塩梅にお燗がつく。
創業からの変わらぬ味と、現代の暮らし方に適した楽しみ方の提案。
剣菱酒造は不易流行を見極めつつ、社会における存在意義を常に厳しく問うてきたからこそ、歴史に名を止めてきたのだろう。
剣菱酒造には、「酒は、米と水と土地がつくるもの。それらに経費をかけるべきで、決して自分たちが贅沢するためにお金を使ってならない」という先代社長の魂が愚直なまでに貫かれている。
(文:FUTURUS:南恵子)
ありがとうございます
私の大好きな日本酒。
その中の剣菱。
古を大切にし守りながら、新しいものも。
伝統とは、こうした繰り返しをしながら守られてきたのでしょうね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld