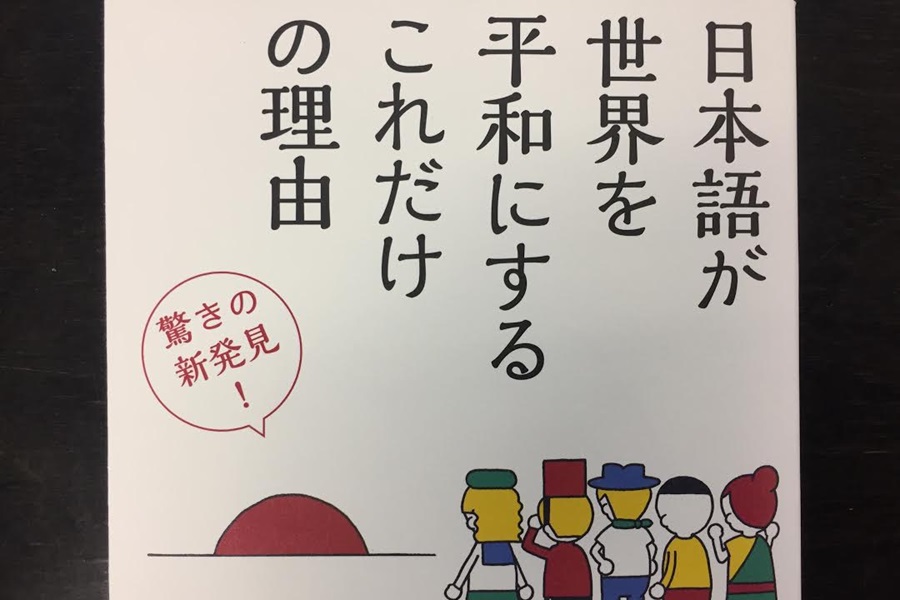二條さま 古事記のお話しの2 第九話 2024.11

カグツチ
心落ち着けて元に戻りましょう。
イザナギとイザナミが最後の子供を生む、これがカグツチという神様ですね。
先ほども言いましたが、これは歴史、考古学、民族学から考えると、やはり朝鮮半島から鉄の技術っていうのが入ってきたんだろう、ということはわかるわけです。
現在もね、実は製鉄に関わっていらっしゃる方は、9月かな釜山っていうところに、日本の製鉄会社のすごく偉い方々は、毎年釜山に社長さんとか会長さんが行って、釜山に日本の神社があるんだそうです。
製鉄会社さんが作った神社があるんですけど、そこで拝んでらっしゃる。
現在でもその交流があってですね、釜山にいる古い、あそこも古いその氏族が名前のついた人たちがいっぱい残っているわけですけれども、交流があるという話を、これは製鉄業界というか鉄工業界の人から伺っております。
こんなことで、カグツチという火の神様を生んで、そしてイザナギが持っていた金属を加工する技術というのが古くなったおかげで、イザナミはもういらないわ、という、国と国が分かれたということなんだと思う。
ただし、ここで重要なのはイザナミという女性神の神、いわゆる出雲の神様ということになるわけですけれども、この神様が置き土産をしていくんですよ。
二柱の神様を置いていくんです。
この二柱の神様、これはイザナミが生んだ神様です。
これ重要なのはイザナギとイザナミが二人で子さえた神様はカグツチまでということなんです。
そこから先は、お一柱ずつ各々が生んでいくんですよ。
すごくここの話を覚えておいてね。
イザナギとイザナミで作った神様の最後は、カグツチってことなんです。
火の神様なんです。
でも、イザナミはこの火の神様を生むことにおいて、この火の神様が呪われるということを自覚していました。
なぜかというと、カグツチの火力だと銅は蒸発しちゃうんだ。
温度が高すぎて溶けちゃうんですよ。
固まらないんですよ。
したがっていらないってことになるわけですよね、カグツチが。
カグツチがいらないっていうことになった時に、火の神が忌みの神になってしまう。
いわゆる、ちょっと呪われてしまう神様になって、生まれた時、イザナギを焼き殺したカグツチのことをイザナギは怒って首を跳ねるんです。
これはトツカ(十束)の剣っていう剣で首を跳ねたっていう風に言われています。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World

トツカ(十束)の剣
トツカっていうのは10個、こうやって持てるぐらいの大きい剣ってことになりますね。
で、ね、このねトツカの剣なんだけれど、そんな大きい剣なんてあるはずがないと思いがちじゃない。
あの当時よ、今から2000年くらい前の話に、そんななんての大きい剣があるはずがない。
例えば江戸時代だとか、江戸時代の最初の頃とか途中、その装飾美にのっとった日本刀っていうんで、割と長い日本刀作って、あの刀剣女子なんかがね。
好きになるような長い刀剣が残ってはいるんだけれども、異物からそんな大きい剣が出てきたっていう話はなかったんですが。
でも、最近出てきちゃったの。
本当に長いやつが。
どのぐらい長いかっていうとね。
多分ね、ここから大谷さんぐらいの長さまであるやつ。
そんな長いの出ちゃったんですよ。
古ったよ。
実際に古ったような痕跡があるということで。
トツカの剣も。
でね、それはね。
トツカの剣の話は、我が国が持っていた最高の宝物だったわけだから、そんな何本もあっちゃおかしいもんなんですよ。
で、出てきちゃったんだ遺物で。
今九州国立博物館に行きますと、実際出土したものが見ることができるし、それを復元したものも見ることができます。
非常に大きくて、これは振るったようです。
一人で振るったかどうかはまた別の話かな。
もしくは本当に戦いで振るったっていうのは、振るいはするけれども、それを戦いに使ったかどうかはちょっと定かでない。
血痕がついてたわけではないから。
でも最新の時に使ったのかもしれないし、もしくは本当に戦争の一番最初にこう相手をひるませるために使ったかもしれないし、いずれにしてもトツカの剣と思われるようなもの。
今までね。
トツカの剣っていうのは、石上神宮から出てきた七支刀(しちしとう)みたいなような、そういうものなんじゃないかっていうふうに思われがちだったんですよ。
七支刀ってご存知ですか。

(東京国立博物館より)
鉄と銅
皆さん七支刀って、こういうふうになっててね。
こういうふうになった剣が石上の神神宮に出るわけですけれども、これ、ほら炎みたいじゃない。
火がボーッと燃えてるように、宝であるこの七支刀みたいなものがトツカの剣だったんじゃないかっていう風に言われていたんだけど、実際本当に10個あって握ってもその束の方に10個かかる。
トツカですから、ぐらいのものがあったっていうことが証明されちゃった。
そういったもの、多分同剣なんだと思います。
なぜかというと、鉄ではまだそこまで大きいものを作れるような技術はないということで、銅でいわゆる低温で溶ける金属で作ったんだと思いますが、そういったものがあった。
それでカグツチの首を切る。
すなわち、ここでカグツチを切ってしまうということは、イザナギはカグツチほどの火力を必要としなかったっていうことじゃないでしょうか。
うちの家ではそんな風に感じているということなんですよね。
で、カグツチは首を切られて高天原のかまどに全部火をつけて、お母さんのところに飛んでいくわけです。
お母さんのところに飛んでいった。
いわゆる、イザナミの方に行ったということです。
したがって高天原の住人でなくなった。
ここまでいいですか。
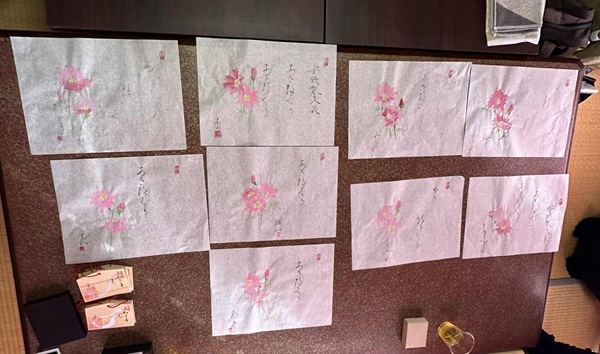
イザナギはイザナミを迎えに
夫婦喧嘩して最初は亭主の方はですね、からいばりします。
出てくるな、出てくるな、みたいなことを言うわけです。
ところがだんだんとね、奥さんの重要性が分かってくるんですよ。
まず靴下とかパンツとかそういったものがどこにあるかわからないから奥さんにかかりっきりになる。
男子っていうのは任せっきりになりますから、奥さん、いわゆる女房役だった人がこの会社でもそうかもしれませんが、大抵の場合、亭主の方が顔になって、裏のことは全部奥さんがやられる。
ということになると、急にイザナミがいなくなったイザナギの家は大混乱ですよ。
どのぐらい大混乱になったかといえばですね、うーん成り立たないぐらい、どのぐらい成り立たないくなったのかっていうと、銅と鉄っていうのを当てたことがありますか。
皆さんこのぐらいの小さな棒でもいいですが、当てますとね、銅はポキンって折れちゃうんですよ。
それは弱いです。
だから何やってもうまくいかなくなっちゃう。
これ、難しいことになりました。
で、大抵の場合、3日のうちぐらいですかね、1週間以内ぐらいでしょうか、実家に帰りますっていう。
奥さんを迎えに行くのは亭主ってことになるわけなんですね。
で、イザナギはイザナミを迎えに行くということになります。
死んでしまったイザナミは黄泉の国に行ったっていう風に言われています。
この段階で我々は間違っちゃいけないのは、根の国、底の国っていう言い方をしますから、地中の方に行ったと思いがちなんですけれども、古事記では決して地中とは書いてないんだ。
理屈好きなんです。
すごく重要なことで、我々の世界には黄昏の国、そして常世の国、そして天の国。
天の国だけは、どうやら空間があるようです。
それはなぜかというと、イザナギ、イザナミが乗ってきた雲があって降りてきたということが分かっていますので、上から降りてきたということが分かります。
ここには空間がありますが、いわゆる今現在イザナギとイザナミがいた世界と、それからイザナミが火で焼かれて亡くなった先の世界というのは陸続きだったということになるんです。
これには、古事記にはこの黄泉の国に対する肯定さが出ていないのです。
書かれていないです。

根の国、底の国
例えば、ここはね雲に乗っていったとか、地中に潜っていったっていうふうに言われているし。
例えばゼウスなんかも地中に戻っていったっていう風に言ってるわけですが、日本の神話には土の中に入っていたっていう文章は書かれていません。
もちろん、言葉として根の国、底の国という言い方をします。
このイメージから言うと、木の根、それから何かの底ってことになるから、この後、入ってくる仏教の世界観、これから言うところの地獄っていうことと集合していくことによって、根の国、底の国がまるで地下の世界のように我々はイメージするわけです。
けれども、実際、あの時代はそういったことではないと思います。
むしろ気持ち的な問題だったんじゃないかっていうふうに私どもは思っています。
この気持ちって、明るいところに行ってもすごい暗い気持ちにさせられる。
これ、根の国、底の国ってか、黄昏れた国に見えたのでしょう。
昭和天皇が初めてアメリカに皇后様と国賓で行かれた時に、我々がテレビで拝見した時にはすごくディズニーランドにもお出ましになって友好的に見えたんだけれども、やはり随行の人たちはものすごく緊張したそうです。
まだ日本とそんなに仲良くなったって思えてない人もいっぱいいたっていう。
そういう国に行くと、ああいう方々はすごくニコニコしていらっしゃるけれども、周りの人はやっぱり、かなりがっちり固めて暗い気持ちで何とかそこから突破口を開こうという気持ちはあるけれども心はかなりしぼんでいたんだというふうに思う。
我々ですらそうですから、あの時代、もっと国っていう形がちゃんとしていたというか、もっと心と心でつながっていたような時代、もっと泥臭い時代、国って我々が想像するよりも精神的に外国に行ったような気分になったんだと。
これを黄昏の国、根の国、底の国って言ったんじゃないかなって僕は思います。
うちの祖父や父なんかに言わせると、まさに色も違った九州の南の方で非常に緑あふれるようなところ。
そして大地が、食性も違う。
それが本土に渡って日本海側に行くってことになると気候も全く違うわけですよね。
冬にもし、日本海側に行ったら常に曇りがちで、少し雨が降っている。
たまに晴れたとしても寒いっていうような。
南国、宮崎から出雲に行ったら相当寒かったと思う。
考えるなら、そういうことが僕は黄昏の国に行ったっていうことにつながっていく。
ここが根の国、底の国だったんじゃないかなって思います。
つづく
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld