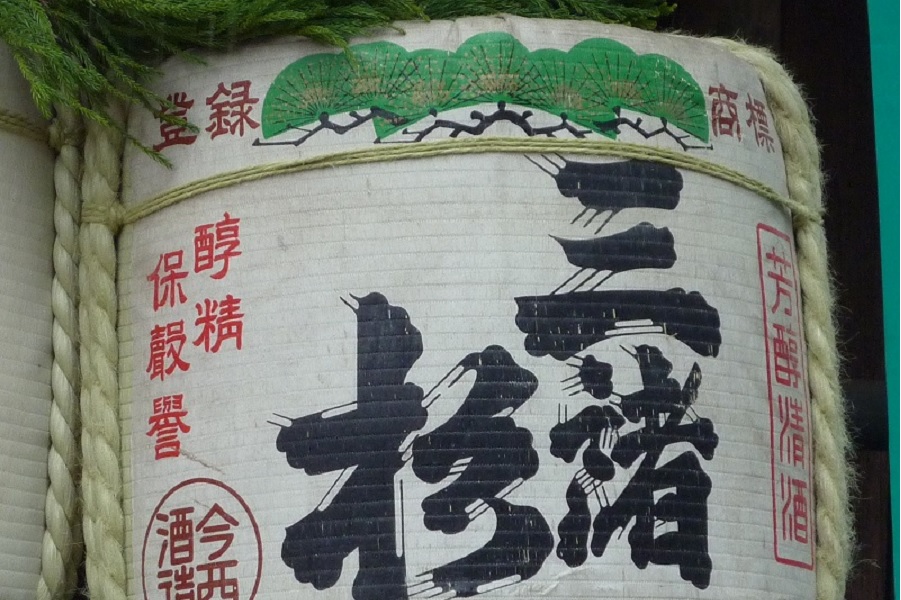今日は、二十四節季の「大暑(たいしょ)」

「大暑」に涼しさを
こんにちは。
梅雨明と同時に連日の猛暑、お元気に過ごされてますか。
熱中症にはくれぐれもお気を付けください。
子どもたちは夏休みに入り、プールでこんがり小麦色の肌は、夏の風物詩ですね。
元気な子供たちと同じく元気なのが油蝉の大合唱。
一年でもっとも暑い「大暑」と時を同じくして、蝉時雨は降り注ぎます。
こん猛暑の毎日、クーラー全開、日差しを避けて過ごすより、ときには、最大級の暑さを積極的に楽しんでみてはいかがですか。
和の知恵には、涼しく感じる工夫が盛りだくさん。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
夏は和の風情が似合う季節
吉田兼好が「徒然草」に記したように、かつて日本家屋は蒸し暑い夏の気候に合わせた造りになっていました
軒を深くとることで直射日光が当たるのを避け、厚い茅葺き屋根は太陽の熱が伝わりにくい構造になっています。
壁が少ないため、襖などを開け放てば風がたっぷりと通り抜け、畳からは素足にひんやりした触感が伝わります。
暑さが盛りの時間、庭先に打ち水して涼風を呼び込み、縁側で冷やした西瓜やかき氷を食べるだけで、お腹の底から涼しくなったものです。
そして、気持ちもさわやかに風鈴の音・・・。
夏は和の風情が似合う季節です。
夏の風物
「風鈴」
耳で涼しさを感じる国民は日本人だけとか。硝子に絵付けした江戸風鈴は低い音。鉄製の南部風鈴は澄んだ音。近隣を配慮して、夜間ははずすのが風流です。
「つりしのぶ」
しのぶ草を苔に植えつけ、軒端につって、江戸の手狭な長屋でも気軽に楽しめ、庶民に大人気になりました。風鈴や金魚玉と組み合わせれば、さらに涼やかです。
「金魚鉢」
尾びれ背びれをなびかせる優雅な金魚の舞姿は、暑さを忘れさせてくれるもの。水草でジオラマを作れば、森の中を浮遊する風景にも見え・・・。
「団扇」
古代の貴人の日よけ「翳(さしば)」を元とする団扇は単純な形ですが、絵柄によってその装飾性は無限。工芸品としてもすぐれた品は専用器具で壁掛けにしてもいいですね。
「たらい」
小さい子なら縁側で行水。西瓜を冷やすにももってこい。そうめんをたらいに泳がせれば、食卓に涼やかな風情。桧の香りが和の趣をアップさせます。
「打ち水」
水が蒸発する際、周囲から気化熱を奪って気温を下げる効果で涼を呼ぶ「打ち水」。昔の人は科学的な根拠は知らなくても、きらきらとはずむ水滴。しっとり濡れた地面の輝き、ほこりを払って清々しくなった空気のにおいにも、暑中の涼を感じてきました。
ありがとうございます
和の風情は、五感に訴える涼しさをかもしだします。
それは、夏の暮らし方に主眼を置いてきた日本人の美意識が結晶しているからのでしょうね。
でも、今年は暑すぎ。
38℃・・・、どういうことでしょうね。
幼いころ日本は温暖と教わりましたが、今や温暖ではなく亜熱帯ですね。
どうしてこのような猛暑の夏日になったのでしょうね。
おわかりとは思いますが、何をどうしていいのかわからないですよね。
自然にやさしい伝統文化と世界に誇る環境技術や環境マネージメントを有するわが国が・・・。
もう遅い?いや、まだ間に合うなら、これからの子供たちの将来のためにできることからしていかなければ。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
これからの子供たちのために、真剣に何ができるのか教えていただきましょう。
参考
夏の風物詩と聞いて思い浮かぶもの
夏の風物詩「風鈴」 チリンチリン
暮らしに寄り添う扇子
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld