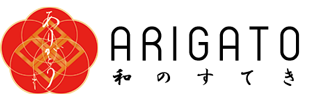「神社と神道の歴史」第5回 著:白山芳太郎

神社と神道の歴史(第5回) 著:白山芳太郎
縄文祭祀をうかがうことのできる祭祀として諏訪大社の「御頭祭(おんとうさい)」がある(既述)。
この祭りにおける神饌(しんせん)は「鹿」である。
鹿とともに縄文時代のご馳走であったのが「猪」である。
「猪」を神饌として供えるのは、九州山地の山中、宮崎県米良(めら)町の「米良神楽」(銀鏡神社(しろみじんじゃ))である。
.jpg)
(米良神楽の神饌 文化庁 重要文化財データベースより)
「米良(めら)」は、江戸時代にいたるも焼畑(やきはた)耕作(稗(ひえ)や粟の栽培)を行っていて、稲作が行われなかった。
(米の取れ高)1万石以上の藩主を大名(だいみょう)と呼んでいた江戸期に「米良」を我が藩だと唱えた大名がいなかった。
米が取れないためである。
江戸時代の九州の地図を見ると、米良への交通路が記されていない。
米良は、椎葉(しいば)や五家荘(ごかのしょう)とともに、地図に墨塗りされていた地域で、地図製作者にとって、この地は図面を描けない地域であった。
そのような江戸時代の米(め)良(ら)に入った人物がいる。
(寛政の3奇人の1人)高山彦九郎である。
高山彦九郎は、肥後の「人吉(ひとよし)」から東行し、山中をめぐり、米良に入った(高山彦九郎『筑紫日記』)。
このような地に「米良神楽(めらかぐら)」(国の重要無形民俗文化財)が伝わった。
民俗学の最高の賞(柳田國男賞)受賞の石塚尊俊氏『西日本諸神楽の研究』によると、この神楽は「日本最古の神楽」である。
その神楽の演目に「ししとぎり」というのがある。
「しし」は「猪」を意味する。
「きり」は「伐(き)る」の連用形が名詞化したもの。
「と」は「頭(とう)」がなまったものとされるが、訓読み基調の語に音読みがあるのは不自然。
頭が胴体から「途ぎれる」ことを言ったものであるから、その行為を行う側から「途ぎる」と言ったのではないか。
弓と矢を持った夫婦が「猪」の猟(りょう)へと出かける。
そのような神楽である。
狩猟採集生活時代の「神饌(しんせん)」が伝わったものとして、もう1つ、春日若宮おん祭り(12月15~18日)の初日(大宿所祭(おおしゅくしょさい))の「懸物(かけもの)」があげられる。
「懸物(かけもの)」とは、正規の年貢のほかに割りあてられる「税」のことで、春日社は周辺の大名や有力武士に神税(しんぜい)(神戸(かんべ)から徴収する税)を課すことができた。
この「懸物」に対し、次のような「囃子歌(はやしうた)」が残っている。
センジョ行こう マンジョ(万衆)行こう
センジョの道に何がある
尾のある鳥と尾のない鳥と
センジョ行こう マンジョ行こう
というものである。
センジョは「遍照(へんじょう)」が訛(なま)ったもので、遍照院(へんじょういん)のことである。
「尾のある鳥」は、雉(きじ)をさす。
「尾のない鳥」とは、何をさすのであろう。
「ウサギ」である。
狩猟採集生活時代のご馳走の1つである「ウサギ」(縄文遺跡の三内丸山では主食)を獣(けもの)としないで「尾のない鳥」といって供え、今日に至っている。

(春日若宮おん祭り「大宿所祭」の懸物(かけもの) 春日大社ホームページより)
イギリスの湖水地方に「ストーン・サークル」のあることは、よく知られている(BC2500年~BC2000年の遺跡)。
Easter(ドイツ語のOstern)は、ゲルマン人の春の女神(Eostre)が転じた語で、春の初めに、ことしの狩猟の獲物(えもの)がゆたかであるようにと祈る祭りである。
Easterは、このような「ストーン・サークル」で行ったものではないか。
秋の終わりになると、また、ここで獲物(えもの)への感謝祭(Halloween)を行った。

(イギリス湖水地方のストーン・サークル Wikipediaより)
「秋の終わり」(現在は10月31日)に行われるHalloweenの趣旨は、今年の獲物(えもの)への感謝であるが、春日若宮おん祭りは、明治まで陰暦9月17日(陰暦は7~9月を秋とし、9月はそのうちの晩秋)に行われていた。
祭りの趣旨はHalloweenと同じで、秋の終わりの感謝祭(現在は12月17日)であり、このような祭りは、人類共通のものであり、太古にさかのぼるものである。
そのような感謝祭に残った縄文祭祀のおもかげが、キジとウサギを供える「大宿所祭(おおしゅくしょさい)」である。
縄文遺跡から出土した獣骨の種類をあげてみると鹿、猪、ウサギ、熊、狐、猿、狸、ムササビ(ネズミ目・リス科の哺乳類)、カモシカ、鯨、イルカ、アザラシ、オットセイなどがあげられる。
弥生遺跡からも、獣骨が出土する。
鹿、猪、ウサギ、熊、猿などである。
これらは弥生時代の食に残った狩猟採集生活時代の面影であって、時代がかわっても、味覚は変わらないものなのである。
中国では、ブタを「家猪(カチョ)」、イノシシを「野猪(ヤチョ)」といい、単に「猪(チョ)」という場合「家猪」をさす(中国の歴史小説『西遊記』にみられる「猪八戒(ちょはっかい)」はイノシシではなくブタ)。
弥生時代に、中国または朝鮮半島から「家猪」が伝わった。
『日本書紀』安寧11年正月条と、同書天武13年12月条に「猪使(いつかい)」氏という姓がみられる。
当初は猪使連(いつかいのむらじ)であった。
天武天皇の八色(やくさ)の姓の制定により、猪使宿祢(いつかいのすくね)(『新撰姓氏録』では右京皇別)となる。
「家猪」の飼育、または「家猪」と「野猪」を混成したイノブタ(イノブタも生殖能力がある)の飼育を職としていた氏族である。
『日本書紀』欽明16年(555)7月条には、吉備国に「猪屯倉(いのみやけ)」を置くようにという命がくだっている。
「猪屯倉(いのみやけ)」の職に従事する者には「白猪史(しらいのふひと)」という姓が与えられた。
この時の「猪」は「野猪」ではなく、白い「猪」というのであるから「家猪」とみられる。
弥生時代に伝わっていた狩猟採集生活の味覚である「野猪」への思いが、新たに伝わった「家猪」への執着心となるのである
『魏志倭人伝』によると、日本には「牛」と「馬」がいないとある。
その後、平安初期の『古語拾遺』に、次のような記事がみられる。
田を営(つく)る日、牛の宍(しし)を以て田人(たひと)に食(く)はしめき。時に、御歳神(みとしのかみ)の子、其の田に至りて、饗(あへ)に唾(つば)きて還り、状(さま)を以て父に告(まを)しき(御歳神の子は憤慨して父に告げ口をした)。<中略>(その怒りを鎮めるために)牛の宍(しし)を以て溝の口に置き、男茎形(をはせがた)を作りて、之に加え(男根の形の品を作って、牛肉に添える)、薏子(つすだま)(ジュズダマのこと)・蜀椒(なるはじかみ)(サンショウのこと)・呉桃(くるみ)の葉、及(また)塩を以て、其の畔(あ)に班(あか)ち置くべし(田の畔に散布しておく)とのりたまひき。仍りて、其の教へに従ひしかば、苗の葉、復(また)茂りて、年穀(たなつもの)豊稔(ゆたか)なり。是、今の神祇官、白猪・白馬・白鶏を以て、御歳神を祭る縁(ことのもと)なり。
田植えをしてもらった農夫たちに、雇用主は通常以上の重労働であるとして「牛」の肉を食べさせた(後に白猪・白馬・白鶏が御歳神を祭る際のお供(そな)えになったが、古くは牛を御歳神にお供えとして供え、神専用のご馳走であるのに、民が食べたとして御歳神の子が憤慨し、父神に告げ口したとあるので、民の通常の食卓にのぼるものではないながら、特別な時、たとえば祭りのあとの直会(なおらい)では食べた)ことが知られる。
時代はくだるが、江戸時代の武士の服喪(ふくも)規定(服忌(ぶっき)令)によると、近親の死後(10日間)の食肉が禁じられている。
ということは、近親の死後10日以内をのぞくと、武士は食肉を禁止されていなかった。
春日若宮おん祭りでは、神饌として、野山から得られる獣肉を供えた。
供えているのは武士たちであるので、武士はこれらを直会で食べた。
古来の神饌であり、このことそのものは、仏教が伝来しても不変であった。
獣肉を供えた後「直会(なおらい)」(祭りが終わったのち、お供えの御酒を飲み、神饌を食する宴)において、これを関係者で食べた。
奈良時代には、仏教が普及し、その思想に基づき、食肉を禁じる法が幾度か出されている(続日本紀)。
法が出ると言うことは、出る前は食肉していたこと、幾度も出されるということは、出されてもしばらくたつと、もとの食にもどってしまうので、また出されるということである。
『続日本紀』天平4年(732)7月6日の条に、仏教の信仰の篤い聖武天皇が、畿内の人びとから家畜の猪(40頭)を買いとり、山に逃がしてやったということが記されている。
法を出しても抑えることのできない食肉習慣への緊急措置であり、崇仏の天皇をして、このような行動に走らせてしまうほどの目に余る食肉習慣であったということである。
それほど定着している食肉が背景にあった。
現存最古の国語辞典『和名抄』(平安中期)によると、猪とウサギが食品のなかに記載されている。
猪やウサギは、奈良~平安時代における普通の食材であった。
上記の春日大社は、奈良中期創建の神社であり、ウサギを神饌に供えるのは創建期にさかのぼるものではないか。
平安末の説話集『今昔物語』では、庶民が猪肉を買いに行く場面が描かれている。
鎌倉時代になると『百錬抄(ひゃくれんしょう)』嘉禎2年(1236)条に、武士が寺で鹿を食べていると記されている。
九条兼実の日記『明月記』安貞元年(1227)条に、貴族たちはウサギと猪を食べると記されていて、食肉習慣は武士だけのものではなく、上記の批判も、寺内で食べるのを批判したものである。
室町時代になると、年中行事や各種事物の話題を集めた『尺素往来(せきそおうらい)』に、猪、鹿、カモシカ、熊、ウサギ、狸、カワウソを食べると記されている。
江戸時代になると、当時の政府(江戸幕府)が戸籍を僧に管理させる寺請(てらうけ)制度を採択したため、庶民は食にまで僧の指導を受けた。
したがって、庶民は食肉をタブー視し、ほとんど食べなかったようである。
一方、将軍や大名の間では、牛肉が好まれ、近江牛(彦根藩主から将軍と御三家に対し、お歳暮として牛肉の味噌漬けを贈っている)、但馬牛、会津牛、津軽牛、出雲牛、信濃牛、甲斐牛は各地の特産品にまでなっている。
薩摩藩では豚が飼われ、島津家は豚が好物の将軍(徳川慶喜)に豚を贈っている。
これら牛や豚を食べる習慣は、前引の『服忌令』をもとに考えると、将軍や大名に限ったことではない。
多くの武士たちにとって、滅多に手に入るものではなかったかもしれないが、需要があり、供給もあったのである。
牛肉以外の食材も、猪の肉は「牡丹肉」、馬の肉は「桜肉」、鹿の肉は「紅葉肉」とする言葉まで今に残っているので、それらを時には食べることがあった。
各神社では、キジなどの野鳥、鴨などの水鳥、鯛などの海の魚、鯉などの淡水魚を「神饌」として供えていた。
時には鹿や猪を供えた(前述のように仏教思想との矛盾からウサギを「尾のない鳥」と称しつつ供えることもあった)。
このような神饌は、仏教が入ってくる以前の食が残ったものである。
したがって、明治となって寺請(てらうけ)制度が廃止されるや、庶民はただちに「すき焼き」(農具の鋤(すき)で肉を焼く)などの方法で、食肉習慣を復活させたのである。
弥生時代の祭祀では、稲を「御饌(みけ)」として供えた。
日本の「稲」の最古のものは、岡山県の朝寝鼻(あさねばな)(貝塚)出土のものである。
出土した貝や土器は縄文後期(BC2000年頃)のものであったが、その下の層から縄文前期(BC4000年頃)の石器・獣骨とともに、稲のプラント・オパール(植物珪酸(けいさん)体化石)が出土した。
したがって稲作は縄文前期のBC4000年には伝わっていた。
水田遺跡は見つかっていないので、畑作としての稲作(陸稲(おかぼ))であったとみられる。
長江下流域の「河姆(かぼ)渡(と)遺跡」から、炭化した稲(BC5000年)が発見され、DNA鑑定の結果、ジャポニカが含まれていた。
この発見により、日本の「稲」は、従来言われてきた朝鮮半島経由(もしくは沖縄経由)という説は間違いであり、長江下流域から直接伝わってきたとされるようになった。
「稲」の伝来は、縄文前期(BC4000年)であるが、弥生時代への引き金となった「水田稲作」は既述(第4回)したように、縄文晩期(BC900年頃)である。
ただし、九州全域から関東にいたる日本列島の中心地域一帯における弥生祭祀はBC300年頃からとみられる。
それほど長く縄文祭祀側からの抵抗が続いたのである。
弥生時代の祭祀では「御饌(みけ)」とともに「御酒(みき)」が供えられた。
3世紀の『魏(ぎ)志(し)倭人伝(わじんでん)』に、倭人は「父子男女の別無く、酒を良く飲む」とあるが、これは祭りの日に「御酒」を飲んでいる様子を見聞し、記録したものであろう。
この時の「酒」は「口(くち)噛(か)み酒」(麹(こうじ)かびによる酒造りについては後述)だったとみられる。
「口噛み酒」についての古い史料は『大隅国風土記』(逸文)に「米を噛んで器に吐き出し、酒の香りがしはじめると飲む」と記されているもので、今日でもメコン川上流ではそのような酒造りが行われている。
また『古事記』によると、即位前の応神天皇が越前(気比(けひ)。現在の敦賀)で禊(みそぎ)をされ、夢のお告げで「気比の神」(気比神宮)と名を交換し、帰京してこられる時、母(神功皇后(じんぐうこうごう))は帰ってくる我が子のため「待酒(まちざけ)を醸(か)みて」宴の準備をしたと記載されている。
この時の神功皇后が詠んだ歌が同書にみられる。
それによると「この御酒(みき)」は私が噛(か)んだ酒ではなく「少名御神(すくなみかみ)」が噛んだ酒であるから「残さず食(め)せ」と記されていて「口噛酒(くちかみざけ)」とみられる。
「少名御神(すくなみかみ)」とは少彦名(すくなひこなの)命のことである。
この神は『新撰姓氏録』(右京神別「鳥取連(ととりのむらじ)」の条)に「天つ神」と記されている。
また『古事記』によると、この神は天つ神(神産巣日(かんむすひの)神)の子(日本書紀では高皇産霊(たかみむすひの)神の子)であると記されている。
大国主命の国造りに際し、天の羅摩(かがみ)の船(ガガイモの実を割って作った舟)に乗って「鵝(ひむし)」(旁(つくり)に鳥の字があってこの字はガチョウであるが、「蛾(が)」を飛ぶ鳥に見立てたものとされていて「ひむし(即ち、ひらひら飛ぶ虫)」とされている)の皮の着物を着て、つまり、ミノムシのような恰好(かっこう)で渡ってきたとされている。
「神産巣日(かんむすひの)神」から、大国主命の義兄弟となって「共治」するようにという命がくだり、大国主命との「2神共治」を行った神である。
『古事記』などの中央の立場から記したものではない出雲の地方神話の側から記録した『出雲国風土記』(飯石(いいし)郡多祢(たね)郷の条)に「多祢(たね)」という村里の名の起源説話があって、そのなかに「2神共治」の話がみられる。
同書に「天の下造(つく)らしし大神大穴持命(大国主命の別名)と須久奈比古(すくなひこの)命、天の下を巡る時、稲種(いなだね)ここに堕(お)つ。故(か)れ、種(たね)と云ふ」とある。
「多祢(たね)」という村里の名は「稲の種」の「たね」から来ているというのである。
「出雲の国づくり」は大国主命1神によるものではなく、国つ神(大国主)と天つ神(少彦名)の「2神共治」によるものなのである。
このような「2神共治」の伝承は、出雲国だけではなく『播磨国風土記』『尾張国風土記』『伊豆国風土記』『伊予国風土記』などにもみられ、各地で「国つ神と天つ神の共治」(即ち、国つ神を奉じる人々と、天つ神を奉じる人々の共治)があって、その結果、弥生祭祀の引き金となる「水田稲作」が普及したのである。
御酒(みき)は、その後「口噛み酒」から「麹(こうじ)かび」による酒造りへと変化する。
「麹(こうじ)かび」による酒造りについては『播磨国風土記』に記して「携行食の干飯(ほしいい)が水に濡れてカビが発生し、それにより酒を造った」とある。
この時のカビが「麹かび」である。
「麹かび」は、でんぷんやたんぱく質を分解する酵素が含まれていて、味噌や酒造りに用いられた。
祈年祭や新嘗祭などの祭りにおいて、米を「御饌(みけ)」として供え、「麹かび」で造った「御酒(みき)」(その他に野山の鳥や海川の魚などを供える)を供え、それが終わると、祭りにたずさわった人びとで御饌その他を食べ、御酒を飲んだ。
そのような生活の中で「血縁による氏族」を中心とする氏族社会が始まった。
氏族社会では、 氏族の長(おさ)への「尊崇の念」が生前からあり「ミコト」と呼んでいた。
「ミコト」は、もともと尊いかたが発するお言葉、即ち御言(みこと)という意である。
そこで『古事記』は、それを命令と受け止め「命(みこと)」という字をあてた。
『日本書紀』も「命(みこと)」の字をあてている。
ただし『日本書紀』は「ミコト」と称しつつ「命」以上の「ミコト」があると記している。
「ミコト」の中の「至って尊いミコト」である。
その場合は「尊(みこと)」とするという説である。
『古事記』はそのような説を採らない(『日本書紀』編者による編纂過程で発生した書き分けであろう)。
これは編纂上のことであって、いずれも「ミコト」と称した。
そのような「ミコト」は、時間の経過を経て、神聖性・呪術性を帯び、一段高い「カミ」と称されるようになる。
例をあげると当初「大国主(おおくにぬしの)命」と呼ばれていたが、後になると「大国主(おおくにぬしの)神」と呼ばれるようになる。

(出雲大社にある大国主命像、谷口勝彦氏撮影)
あるいは「天照大神(あまてらすおおみかみ)」は当初「オオヒルメムチノミコト」と呼ばれていたが、後になると「アマテラス大神」と呼ばれるようになる。
なお「アマテラス大神」の「ス」については、これを尊敬の助動詞「ス」とする説があるが、間違いであろう。
「霜置く」とか「雪降る」の「置く」「降る」と同様であって「照らす」という自動詞である。
つまり、日本人は「霜」「雪」「太陽」などは意志を持っていて、みずから「置く」「降る」「照らす」という行為を行うと考えていた。
そのため、自動詞なのである。
このような自動詞は、日本語以外ではイヌイット語やアイヌ語にみられるものである。
我々は太陽に照らされ、雪に降られているが、太陽や雪の立場からいうと、太陽が照り、雪が降るのである。
そのようにして「ミコト」は「カミ」として尊崇されるようになった。
すると「カミ」は内在的に「霊力」を持っているとされ、人びとはそれを「畏怖」するようになる。
そのような「カミ」を、 血縁上、密接な関係にある集団で祀ったのが「氏の神」(後に言葉が短縮され「氏神(うじがみ)」となる)である。
生前あった氏族の長(氏の上(かみ))への尊崇が、その逝去により「氏の上の祟(たた)り」を畏怖する観念となる。
その観念が時の経過とともに、「氏の上」は、もともと「氏を守る神」であったのだとするようになる。
そして「氏の神」を尊崇する子孫は、その神によって守られるという信仰へと発展する。
このようにして誕生したのが「氏神信仰」であって、中臣氏(天児屋命を祖とする)、忌部氏(天太玉命を祖とする)、三輪氏(大物主神を祖とする)、諏訪氏(建御名方神を祖とする)、安曇氏(綿津見神を祖とする)などの例がある。
中世になると「氏神」を祀る地域に住み、同じ「氏神」の祭りに参加する人びとを互いに「氏子中(うじこちゅう)」と呼ぶようになる。
そうなってくると「氏神信仰」は「地域信仰」へと発展する。
その結果、その地で生まれた子(氏神が生んだ子とされ、氏神のことを「産土(うぶすな)の神」とも呼ぶ)の「氏子入り」が生後1か月の「初宮詣で」として行われる。
出産した母にとっても「氏子入り」(嫁入りし氏子区域に引っ越した後、母となって行う最初の「初宮詣で」で氏神の養女のような関係になれる)の日であって「初宮詣(はつみやもう)で」は、新生児の「氏子入り」であると同時に、母の「氏子入り」の日(父は出生時に「氏子入り」)であった。
そのため、母も盛装して参詣する(父もしくは祖母はそれを見届ける)。

(初宮詣で Wikipediaより)
また、成長のいくつかの段階で「七五三」(三歳と七歳が女児、五歳が男児で、さらに十五歳の元服が加わる)や「秋祭りの神輿(みこし)かつぎ」を行うことを通じて「氏神」ひいては「氏子中」との交流を深める(このような儀礼を、文化人類学は「加入儀礼(initiation)」と呼んでいる)。
第6回に続く

白山芳太郎 プロフィール
昭和25年2月生まれ。
文学博士。皇学館大学助教授、教授、四天王寺大学講師、国学院大学講師、東北大学講師、東北大学大学院講師などを経て、現在、皇学館大学名誉教授。
おもな著書に『北畠親房の研究』『日本哲学思想辞典』『日本思想史辞典』『日本思想史概説』『日本人のこころ』『日本神さま事典』『仏教と出会った日本』『王権と神祇』などがある。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World