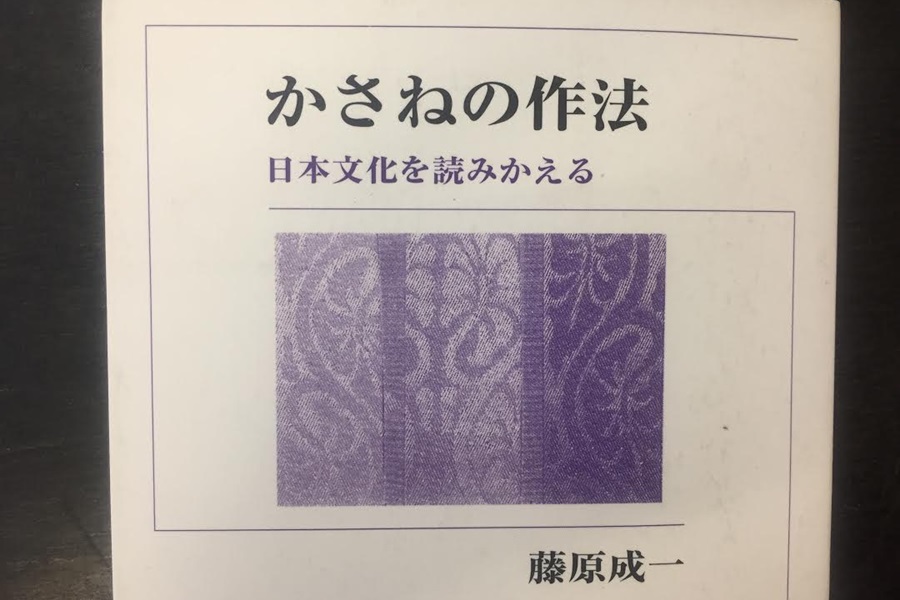お社は自然と人間の聖なる出会いの場

お社とは
こんにちは。
お社(やしろ)といいますと、今は、神さまが鎮まる御社殿という意味でとらえていますが、古いことばの意味ですと、建物を建てる場所という意味であって、必ずしも建物ではないといいます。
これは歴史的に実証できることではないのですが、「万葉集」の歌など、いろいろなものから考証できるのです。
ですから、お祭りのときには簡単な建物を建てたりしますが、ふだんは聖なる場所として、例えば、注連縄(しめなわ)を張ったりして、中へ入ってはいけませんよというように、禁足地といいますか、そういうふうに囲っておく場所がお社であると理解されるといいのではないでしょうか。
社は、もと屋代(やしろ)ですから、苗代(なわしろ)とか、糊代(のりしろ)とか、そういうような言葉から見ると納得できるのではないかと思います。
このように、かなり永い間、常設の御社殿をもっているお社は、それほど多くはないのです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
延喜式
西暦927年に編纂された「延喜式」という法律書がありますが、その中に、中央の政府や地方の政府がお祀りをしてさし上げるという由緒あるお宮のリストがあり、それによると、全国で2862社あります。
それらの中で、神宮(かむつみや)といいますと神宮ですが、神宮という名前を使っていますお社は全国で8社しかありません。
あとは全部、神社(かむつやしろ)といいます。
社という言い方ですから、おそらく、10世紀はじめまでは、浄らかで神聖な森はあったとしても、常設の社殿を持たない神社の方が、圧倒的に多かったのではないかと推定できます。
(文:神道の世界:薗田稔)
「神宮」「神社」の名称
「神宮」「神社」の名称は、神社名に付される称号で社号といいます。
現在、単に「神宮」といえば、伊勢の神宮を示す正式名称として用いられています。
また「○○神宮」の社号を付されている神社には、皇祖をお祀りしている霧島神宮や鹿児島神宮、また天皇をお祀りしている平安神宮や明治神宮などがあります。
このほか、石上神宮や鹿島神宮・香取神宮など特定の神社に限られています。
これに対して「神社」は、その略称である「社」とともに一般の神社に対する社号として広く用いられています。
また、「宮」や「大社」などの社号もあり、「宮」は天皇や皇族をお祀りしている神社や由緒により古くから呼称として用いられている神社に使われます。
「大社」はもともと、天孫に国譲りをおこない、多大な功績をあげた大国主命を祀る出雲大社を示す社号として用いられてきました。
しかし、現在「大社」は、広く崇敬を集める神社でも使われています。
このほか、社号と異なりますが、古くから神様の名前に「大神」や「大明神」、また神仏習合の影響による「権現」といった称号を付して、社号に類するものとして一般的に用いられ、信仰されている社もあります。
このように神社により社号は異なりますが、それぞれの神社に対する人々の篤い信仰にはいささかの変わりもありません。
(文:神社本庁より)
ありがとうございます
自然の中に神聖さを感じませんか。
そこは神が宿る聖なる場所。
気持ちのいい場所。
癒される場所。
日本にはたくさんの聖なる場所があり幸せですね。
ちなみに、延喜式に出てくる神宮は
内宮<皇大神宮> 神宮 --- 三重県伊勢市宇治舘町
外宮<豊受大神宮> 神宮 --- 三重県伊勢市豊川町
熱田神宮 三の宮 官幣大社 愛知県名古屋市熱田区
香取神宮 一の宮 官幣大社 千葉県佐原市香取
鹿島神宮 一の宮 官幣大社 茨城県鹿嶋市宮中
惣社大神宮 惣社 県社 福井県武生市京町
出雲大神宮 一の宮 国幣中社 京都府亀岡市千歳町
日前・国懸神宮 一の宮 官幣大社 和歌山県和歌山市秋月
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld