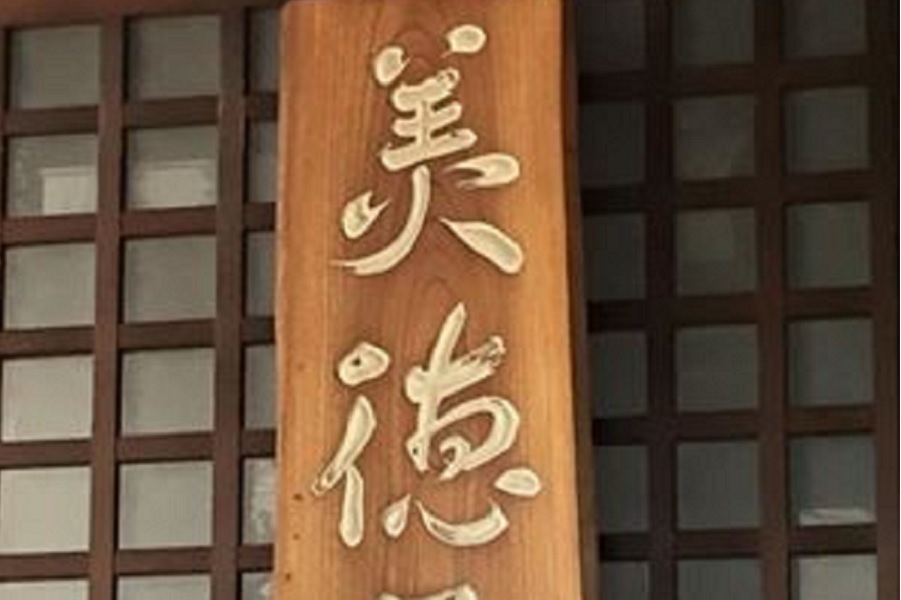蝉羽月、何月のことでしょか

蝉の羽月
こんにちは。
蝉の羽月(せみのはづき) 陰暦6月の称です。
薄い着物を着るからだそうです。
「蝉の羽」といえば蝉のはねのような薄い着物と言う意味があります。
源氏物語夕顔には「蝉の羽もたちかへてける夏衣」という表現が登場します。
襲(かさね)の色目にも「蝉の羽」が有ります。
その組み合わせは、表は檜皮(ひわだ)、裏は青だそうです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
日刊こよみのページより
夏蝉の鳴き出す時期は地方によって大分違うでしょうが、東京近郊では大体6 月末~ 7月初め(共に新暦の日付)辺りであったそうです。
この時期というと半夏生の時期に一致しますので、蝉を「半夏虫」と呼ぶこともあるそうです。
半夏虫と呼ばれる蝉の鳴き出す頃、蝉の羽を思わせる薄衣を身につける月、その月の名前が「蝉の羽月」とは、何とも優雅ですね。
心配なのは、地球温暖化の影響か、はたまた都市のヒートアイランド現象のためか、昔に比べて気温が上がって蝉の初鳴きの時期が早まっているとのこと。
それと、気温が上がって「蝉の羽」のような衣でも暑くてたまらなくなってしまうことですかね?
(文:日刊こよみのページ)
有職のかさね色
「襲(かさね)の色目」ってご存知ですか。
かさね色目には3種類の意味があります。
1.表裏のかさね色目(合わせ色目)(重色目)
2.重ね着のかさね色目(襲色目)
3.織物のかさね色目(織り色目) 経糸緯糸に違う色を使うことで複雑な色合いを作り出します。
装束の色彩は、これら3種の色目の混合体なのです。
数多くの新案かさね色目が生まれています。
時代、公家の家流で同じ色目でも名称が変わったり、逆に名称は同じでも色目が異なったりします。
宜しかったらこちらをご覧ください、学べますよ。
有職のかさね色
ありがとう
襲(かさね)は平安時代から伝わる、衣の配色 紅梅とその上に降り積もった雪の取り合わせといった、微妙な四季の移ろいを自然から映しとって着物に組み合わせた日本人ならではの色彩感覚です。
美しい風景から襲の色彩がたくさん。
古(いにしえ)の日本人が持っていた繊細な美意識、素敵ですね。
平安王朝の雅な感性にはまだまだ遠く及びませんが、日本人の心の琴線に触れたいものです。
やっぱい日本はすてきですね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld