
日本の伝統文様 霰(あられ)
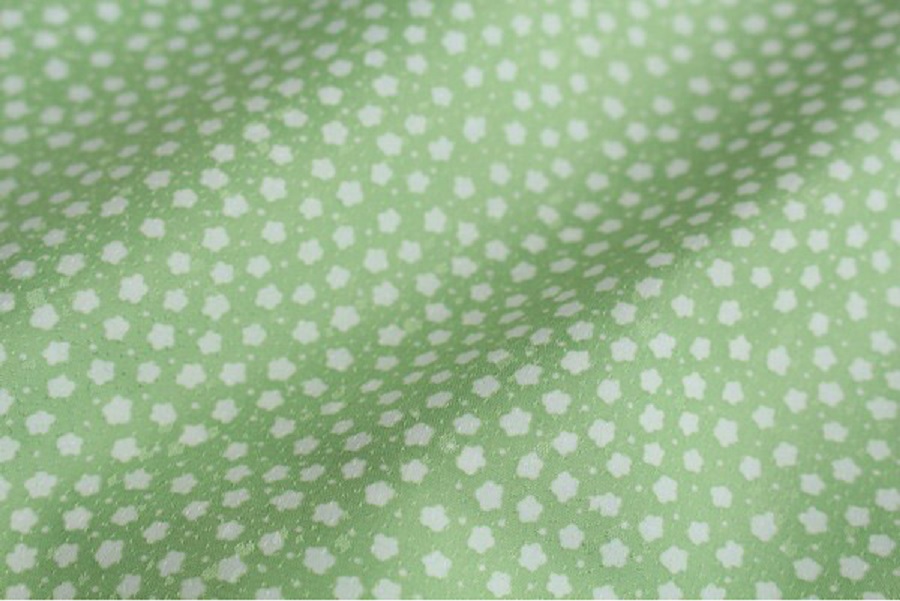
霰文(あられもん)
こんにちは。
霰文は江戸小紋によくある文様です。
降りかかるのは雨か雪か霰かという、霰をも図案にしています。
霰は雨まじりで重い音がする感じですが、霰は粒の大小はあっても飛びはねるような勢いがあるもの。
丸く不規則な点々を自由に描いてできた図案にこの名をつけたのでしょうか。
小紋染の霰文はなかなかモダンな文様だと思います。
武士の裃に使われていたというのに、現代の若い人が、江戸小紋の「黒字に霰」を、これなら着てみたいといいます。
時代が変わっても命の長い文様のひとつです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World

文様の名
地色を変えるとドレスにも使えます。
洋服地の水玉というのは、江戸小紋と違ってその円形が同じ大きさなので、平板になりやすい柄です。
水玉は白地に色水玉を使うことが多いものです。
ここでいう霰は、空から降る霰を文様化した自然文様ですが、割付文様のひとつ石畳文も、霰文とよばれています。
これは入れ替わり文様といって、同じ大きさの同じ形が連続して、隣り合う形の色が入れ替わりに変わるものです。
現代では市松といえばわかりやすいでしょう。

霰地、霰文というときは、装束用二重織物の地紋です。
織物でも霰絣(あられかすり)といえば、久留米絣などにある縦横糸で点々と白い絣の粒を織りだしたものです。
しかし、染物で霰といえば、大小の水玉状の文様と思えばよいのです。 季節を問わずに古くから用いられています。
地色に明るい中間色を使うと、若い人に着やすい江戸小紋です。
(文:和の意匠に見る 文様の名の物語:木村孝著)
ありがとうございます
日本人って見たまま、感じたままに描くから、同じ大きさなんてありえないのでしょうね。
作品ひとつひとつが違う。
違うのが当たり前のようですが、今の世の中すべて同じ柄。
もっと、自然と共に見たまま、感じたままで過ごしていきたいです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
これからも浄住寺共々、宜しくお願いいたしますね。
他の文様:青海波・矢羽根・霰・立湧・松竹梅・梅
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld











