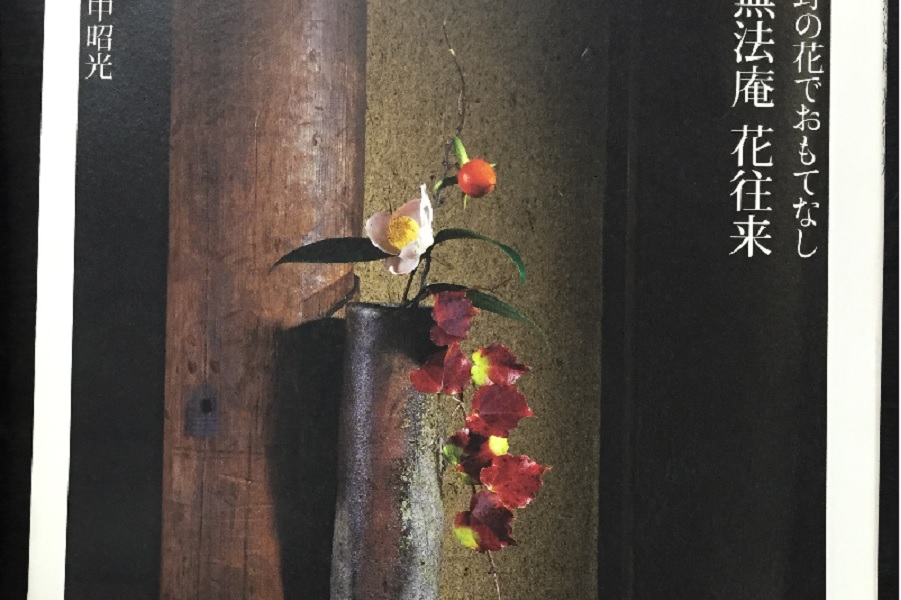蹴鞠をご存知ですか。

蹴鞠保存会
こんにちは。
先日、霞会館で「伝統文化の日」という催しがありました。
皇族、公家に伝わる伝統文化が幾つか紹介され、とっても学びが多かったです。
その中の一つに蹴鞠があり、鞠や装束が展示されてました。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
約1400年前に日本に
蹴鞠は今から約2300年以上も前、中国の春秋戦国時代の斉(せい)の国の都で行われていたことが、約1200年前に前漢の司馬遷によって著された史記の中の蘇秦列伝に記載されています。
史記には蹴鞠と書かれていますが、実際には現在のサッカーのようなものではなかったかと言われています。
その後、日本へは約1400年ほど前、仏教などと共に伝来したと伝えられています。
本家の中国では蹴鞠は衰退したようですが、我が国では独自の発展を遂げ、現在まで継承されています。
歴史的には、飛鳥の法興寺における蹴鞠の会で、中大兄皇子、後の天智天皇が鞠を蹴って脱げた沓(くつ)を、中臣鎌足、後の藤原鎌足が拾われたのがきっかけで、翌645年の大化の改新が成就したと言われています。 
その後、平安時代後期、白河院から鳥羽天皇の頃には藤原成通という名足(めいそく)が出ました。
蹴鞠では名人のことを名足と称します。
藤原成通は数々の逸話を残しましたが、66年の生涯で7000日も鞠を蹴ったとのことです。
また、鎌倉時代の後鳥羽上皇は蹴鞠を大層お好みになられ、「此道の長者」と称せられ、蹴鞠の基礎を築かれました。
その後の歴代の天皇も蹴鞠を好まれ、鎌倉・室町時代を通じ、蹴鞠は貴賤を問わず流行し、京都だけでなく地方にも広がりました。
また、江戸時代には現在の京都の新京極や円山公園などの各所に鞠場が設けられ、多くの人々が蹴鞠を楽しんだと伝えられています。
この頃には女性が蹴鞠をしている絵も残されています。
このように流行した蹴鞠ではありますが、明治維新を迎えて西洋化が進み、我が国古来の文化が顧みられなくなると、蹴鞠も存亡の危機に立たされました。 しかし、旧公家を中心に蹴鞠は継承され、明治維新後もしばしば天覧鞠が開催され、明治天皇より「蹴鞠を保存せよ」との勅命と御下賜金(ごかしきん)を賜って、現在の蹴鞠保存会が設立されました。
それ以来、蹴鞠保存会は公家の飛鳥井家が蹴鞠を継承しています。
(文・写真:蹴鞠保存会「蹴鞠」より)
ありがとうございます
蹴鞠、一度は蹴ってみたいですね!
優雅にね!
蹴鞠だけでなく平安のころから伝わる文化は明治のころまで、独自の形になっていったものもありますが楽しまれてきました。
伝える、残すということはとても大変なことです。
これまでに、これからもなくなってしまう文化や娯楽はたくさんあるかもしれませんね。
それはそれでしょうがないです。
この時代に楽しんでもらえないからかな。
でも、私は今風に少し変えるだけで皆さまと楽しめるのではないかなと思ってます。
サッカーの起源と言われる蹴鞠もいつまでも残りますように。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
最初の絵は「蹴鞠をする徳川吉宗(月岡芳年画)」
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld