
「和」を貴ぶこころ
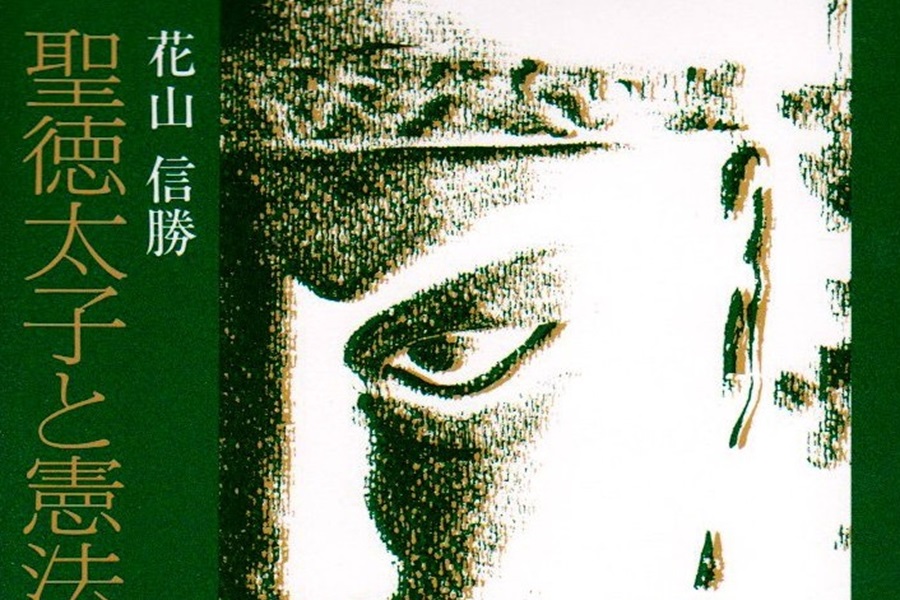
白山先生
こんにちは。
私が尊敬する白山先生の皇學館大学退任記念に書かれた「神道論集」。
今の時代だからこそ、多くの方に読んでいただきたい「和のこころ」が全編にわたって書かれています。
今日は、その中の一つ「「和」を貴ぶこころ」です。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
「和」の尊重
「和」について、谷省吾皇學館大学名誉教授が、その著「神職の立場」で神職の職務を説明して「ナカトリモチ」とされるなかで「家伝」に記載の「和」の語を紹介されている。
同書は「藤氏家伝」ともいわれるが、そのなかに、藤原氏の前身を記して中臣氏であるとし、そして中臣氏とは何かを記して「その先は天児屋根命より出づ。世々、天地(あめつち)の祭りを掌(つかさぢど)り、人と神との間を相(あい)和す。よりてその氏(うじ)に命じて中臣という」とあって、神と人との「和」を職務とする家だと紹介された。
中臣というのは、人と神との中を和すという職務を果たしてきたので「中臣」と称しなさいと我等は命じられ今に至ったというのである。
つまり、神職を任務としてきた家筋から出た中臣鎌足は政治家に転じて藤原鎌足となったが、本家としての中臣氏はその後も変わらず大中臣といわれることとなるが、引き続いて神職たる任務を継承していった。
人と神との間を和して下さる存在、それが神職なのであって、その神職の中心の家に「中臣」と称しなさいと命じられたというのである。
そのような「和」を大切と考えられたのが聖徳太子であった。
聖徳太子「十七条憲法」第一条に、中臣氏が神と人との間を相和しているのをふまえて、今後も「和」を尊重しようと宣言された、それが和を以て貴しと為すである。
聖徳太子があれほど大事と考えられた仏法の尊重は第二なのであって、第一は「和」の尊重であった。
そのような「和」を愛する我が国民性を築き上げた第一は、神職さん達が神と人との間を和してこられた営みによるものであり、そのような和を尊重しようと発言された聖徳太子によるのである。

「和」を貴ぶ
「和」というのは、そのような極めて神道的な概念である。
また、神社には自然がある。
山があり川がある。
太陽の恵みがある。
それらとの調和をはかること、それが神道である。
海外の寺院に、自然はない。
自然との調和は、日本型「和」であって、それが神道であるといってよい。
聖徳太子は「十七条憲法」に何度も「和」という語を使われている。
第一条にはすでに紹介した部分があり、かつ「上(かみ)和し下(しも)睦ぶ」とある。
第十二条にもあり、第十五条にもある。
概していえば、よく話し合いなさいということである。
そのような「和」の心に人は「睦(むつ」みなさいということもいわれている。
かかる人々の自然な心のいとなみを「和」と称されたと推断する。
そのような「和」を貴ぶこころ、それが「神道」である。
(文:皇學館大学退任記念「神道論集」 白山芳太郎著)
ありがとうございます
「睦みなさい」、仲良くしなさいって、とってもすてきなことですね。
相手を思う気持ちがないと睦まじく出来ないです。
それは人間同士だけでなく、生ある生物すべて、自然も、目に見えないものもすべてと仲良くする。
これが、和の心なのです。
先日、冨山房の坂本社長にいただいた、「聖徳太子と憲法十七条」。
みなさまにも是非ともお読みいただきたい一冊。
ここにも聖徳太子が、どれほど和を大切にされていたかが書かれています。
日本の歴史の中で一番血を流した時代かもしれません。
だからこそ、「血を流して争うことはもうやめましょう」という思いから「和を持って貴し」、和を一番大切にされたのでしょう。
昔も今も、人間、何も変わっていません。
ちょっと文明が進歩しただけです、本当にちょっとだけ。
だから昔と変わらず、和を大切にしていきましょうね。
「和」、これは「わ」と読むのでしょうか。
もしかしたら「やわらぎ」と読むのかもしれませんね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld











