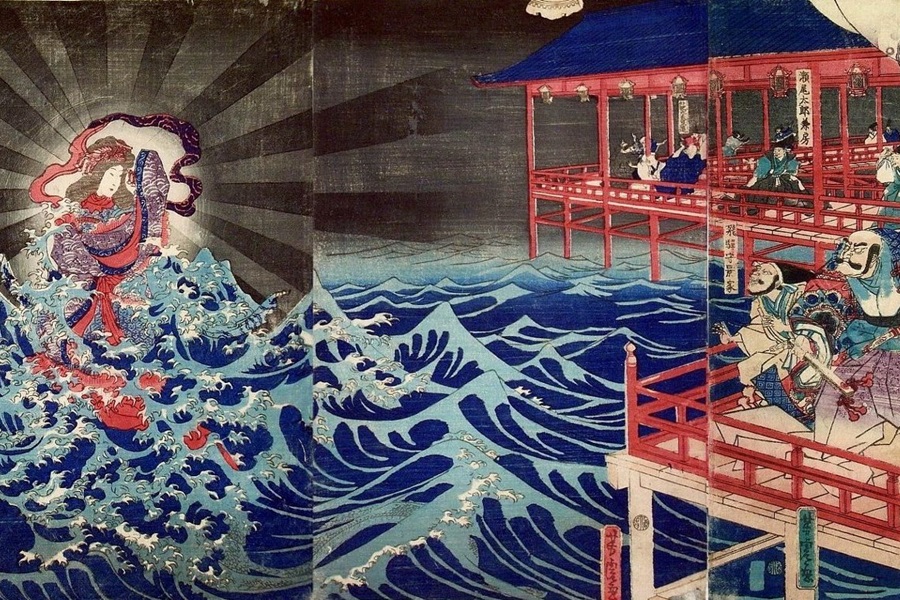囲炉裏で和の心を感じよう〜道具編Part1〜

囲炉裏をご存知ですか
こんにちは。
囲炉裏の設備が整っても、道具がなければ使うことができません。
囲炉裏には、必要な道具がたくさんあります。
昔から同じような形状で使われ続けているものも多いですが、今でも作成されており、手に入るものばかり。
今回はその道具をご紹介する第一弾です。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
囲炉裏といえば灰
囲炉裏に必要な道具といえば、灰です。
現代私たちが目にする囲炉裏でも必ずといっていいほど灰が使われていると思います。
しかし意外なことに、囲炉裏に必要不可欠と思われる灰ですが、熱効率や見た目の美しさなどにこだわらないのであれば、絶対に必要というわけではないそうです。
灰がなくても木炭や薪は燃えると言うことですね。
灰といっても様々な種類があり、囲炉裏に最適な灰が存在します。
囲炉裏には、耐熱性に優れ、かつ激しく燃えすぎないように火を抑えることができ、その上で美しさを表現できる、さらさらとした灰が最適だと言われています。
一般的にはナラ、クヌギ、カシなど広葉樹(堅木)でできた木灰(もくはい)が使われますが、木の種類によってはもちろん、同じ種類の木でもそれぞれ先にあげたような効果に違いがあるので、灰選びはなかなか難しいですね。
灰の美しさとは?
先ほどから出てきている灰の「美しさ」という言葉。違和感を感じ人もいるかもしれません。
美しさのためにさらさら感が大切なのはなぜかというと、「灰模様」という模様を灰に描くからです。
日本庭園の砂に描かれる美しい波模様などをイメージしてもらえるとわかりやすいと思いますが、そのような模様を灰に描くことで美しさが生まれるのです。囲炉裏の灰を美しく整えてお客様を迎えると言う習慣自体が、素敵だと思いませんか。
美しい灰模様のために必要な道具、灰ならし
灰模様を描くのに必要な道具が、灰ならしです。
模様は描かなくとも、灰を整えることにも使います。
金属製のヘラであることが多いですが、昔は木製のものもあったようです。
ヘラの先はギザギザの波状になっていて、これによって美しい模様を描くことができます。
先だけがギザギザになっているものもあれば、フォークのような深いギザギザのものもあります。
色々な形状がありますので、好みのものを探すのも楽しいですね。
灰ならしとよく似た灰かき
灰かきにギザギザがついているものもありますが、焼け跡の炭火や薪を掻き出す、掻き寄せるなどして後片付けをすることが主な目的の道具です。
また灰に穴を掘ったり、山を作ったりすることにも使われます。
昔は囲炉裏だけでなく、風呂の釜など色々な用途で使われていたようです。
よく似た用途で、先の細い形状のものに火搔きというものがあります。
火力調整のため、薪や木炭を移動させるのが主な目的です。
大きさは様々ですので、囲炉裏のサイズにあったものを選ぶと良いでしょう。
火搔きに似た用途の火箸
その名の通り、長いお箸ですね。
金属でできていて、火のついた木炭や薪を移動させたり、ひっくり返したりして火力を調整するための道具です。
火箸や灰ならしは黒い鉄製のものと光った真鍮製のものの2つに分かれます。
特に性能には差はありませんので、好みで選ぶと良いでしょう。
木炭や木灰を運ぶ十能(じゅうのう)
名前だけでは、何をする道具なのかさっぱりわかりませんね。
簡単に言うと、木炭や木灰を運ぶための鉄製のスコップです。
新しい木炭や木灰を追加するときにも使います。
十能の進化版、台十能(だいじゅうのう)
こちらもその名の通り、台がついた十能のことです。
十能に足をつけることで、板の上などにも置けるようになっています。
より安全に炭を運ぶことができます。
ありがとうございます
囲炉裏に関わる道具をたくさんご紹介しました。
残りの道具はまた別の機会にご紹介しますね。
これらの道具にはあまり馴染みのないものが多いでしょうから、一つ一つ調べながら最適なもの、そして自分の好みのものを選びましょう。
また自分自身で使う予定がない人も、日本の素晴らしい伝統として知っておきたいものです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
独楽(こま)と演芸~昔ながらのおもちゃ~
日本の伝統文化、「麻」のこと知ってますか。
風呂敷を活用した生活〜なんでも包める魔法の布の包み方〜
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld