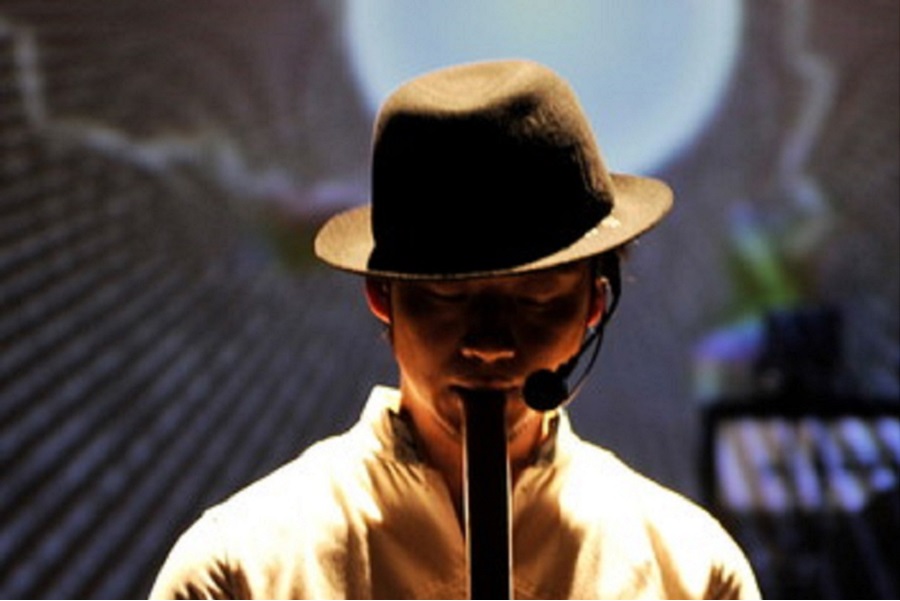今日は重陽の節句

節句とは季節の節目となる日
こんにちは。
今日、9月9日は重陽の節句、日本の五節句の一つ。
節句とは季節の変わり目を指し、無病息災、五穀豊穣、子孫繁栄などを願い、その季節に収穫できる旬のものをお供えしたり食べたりして邪気を祓う行事のことです。
今日は菊の花を飾り、菊の花びらを浮かべたお酒を楽しんだりして長寿や無病息災を祈願します。
重陽の節句以外には、1月7日の人日(じんじつ)の節句(七草の節句)、3月3日の上巳(じょうし)の節句(桃の節句)、5月5日の端午の節句(菖蒲の節句)、7月7日の七夕(しちせき)の節句(笹竹の節句)があります。
奈良時代に中国からはいってきた節句。
昔からある風習と合わさって現代の節句の形になりました。
もう今ではおめでたい節句を祝うことも少なくなりましたが、日本では奇数は縁起のいい数字、この奇数が重なるこれらの日は縁起のいい日とされてきましたのでお祝いしましょうね。
追伸、今では五節句ですが元々はさまざまな節句があったそうです。
また、調べて報告しますね。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
菊の被綿(きせわた)
先にも書きましたが、今日は菊の花を飾る日でもあり「菊の節句」ともよばれます。
この日の菊の節句に因んだ伝統的行事の一つが「菊の被綿」。
重陽の節句の前の日に、菊の花にまあるく作った黄色・赤色・白色の真綿を被せて夜露と香りをすわせます。
そして節句の朝に、その真綿で身体を祓い清めると魔を祓い長生きできると言われています。
白色の菊には黄色の真綿を、黄色の菊には赤、そして紫の菊には白色の真綿を被せます。
私は、床に飾られた菊の被綿に古からの、今という時を大切にするすてきな文化の深さを感じました。

この風習は平安時代から行われており、貴族の間では盛んに行われていたそうです。
枕草子や源氏物語などにもその様子が書かれています。
因みに、この菊の被綿は二條家の香道桜月流の入校式に飾られたものです。

桜月流入校式
重陽の節句の前ですが、7日に二條さまの香道桜月流の入校式が北鎌倉でありました。
昨年の息子の入門式の時に「これが最後」とおっしゃてましたが今年も5名が入校されました。
「今年が最後」とおっしゃってました。
最初の写真の女子は和のすてきの丸尾さんです。
丸尾さんんも入校されました。
おめでとうございます。

月に一度の学びですが、5年間とのこと。
すてきな事をたくさん学んでくださいね。
ありがとうございます
節句ですが、元々は五節句のほかにもさまざまな節句があったそうです。
調べてみますね。
節句は元来「節供(せっく)」という漢字使われていたそうです。
節供とは、稲作を中心とした日本の農耕儀礼において、その節目の日に神前に供え物を供えることをいうそうです。
「節(せっ)」は折り目、「供(く)」は供え物をあらわします。
つまり、節句ごとの食べ物には特別な意味が込められていたのですね。
江戸時代に入ったころ、庶民の生活も豊かになってきたころに節句となり、五節句が祝日となったそうです。
しかし旧暦から新暦に変わった明治時代に五節句が廃止され祝日でもなくなったそうです。
何ででしょうね。
ふしぎ!
日本人は日本人らしく海外のまねではなく、古よりのすてきな文化などを大切にしていきたいです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

関係記事
9月9日、9は最高の徳を表す数字とされてました
陽子の旬をいきる ~重陽の節句~
「作法」 理由がわかればあたりまえに
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld