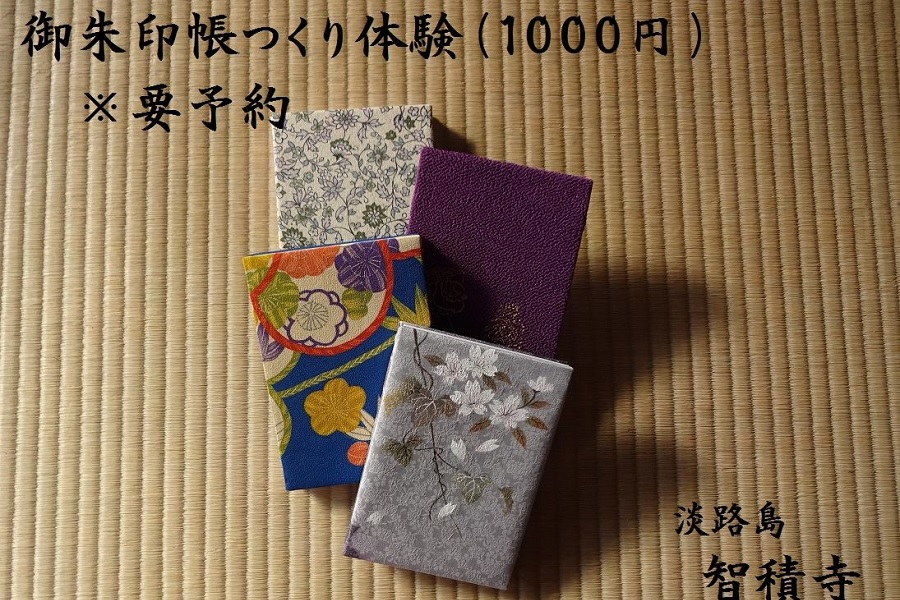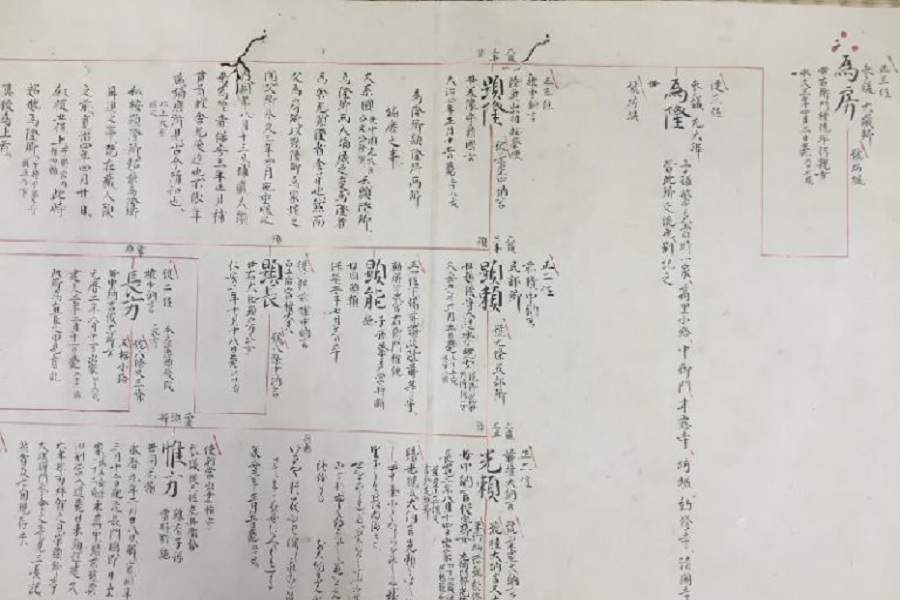今日から9月、長月です。

お月見、重陽の節句、美味、楽しいことがいっぱい
こんにちは
八百万、目に見えないものまでにも「ありがとう」と思える和の心が大切。
和の素敵では、「ありがとう」という言葉が、この世界をいつも笑顔あふれる幸せな毎日にしてくれると思っています。
さて、今日から9月、長月。
暑い夏がいつの間にかそーっと姿を消して、気持ちの良い風がそーっとやってきてます。
でも、日本人は気が付くんですよね、季節の移り変わりを。
そして、楽しむんですよ、季節の移り変わりを。
長月、楽しいことがいっぱい待ってますよ。
みなさんは何をして楽しまれますか。
私は浄住寺でお月さんと楽しみます!
宜しかったら秋の夜長を浄住寺でご一緒にいかがですか。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World

なぜ長月というの?
日本では、旧暦9月を長月(ながつき)と呼び、現在では新暦9月の別名としても用いています。
旧暦9月は新暦で10月上旬から11月上旬、夜がだんだんと長くなってくるころです。
長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力です。
他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説などがあります。
また、「寝覚月(ねざめつき)」の別名もありますね。
この9月は菊の花の盛りにあたるため別名「菊月」ともいいます。
特に9月9日は「菊の節句」とも「重陽(ちょうよう)の節句」とも呼ばれます。
「重陽」とは、陰陽説で奇数を陽、偶数を陰と考え、陽の数つまり奇数の一番大きな数となる9が日月で重なる佳日という意味で。
この日には古くから「菊酒」を飲む習俗があります。
「菊酒」とは菊で造った酒ではなく、菊の花を浮かべた酒のことですよ。
この一月、楽しみ(笑)
長月はやっぱりお月さま
日本人は、時々刻々と深まりゆく秋の気配を、耳を澄まし、肌で感じながら秋月のさやけさをことさらに愛し、生活を楽しんできました。
お月さまの日毎に変わってゆく名前、御存知ですか?
「中秋の名月」-八月十五夜の月。
「十六夜(いざよい)」-十五夜より少しおくれてでるので、ためらいながら出る月の意。
「立待月(たちまちづき)」-十七夜の月。 縁に立ったり、戸口に出たりして待つ月。
「居待月(いまちづき)」-十八夜の月。 家の居間や座敷でゆっくり待たねばならない月。
「臥待月(ふしまちづき)」-名月から四日目の月。 燈火に乏しい古えの人々は、寝所に入って窓から月を眺めました。
「更待月(ふけまちづき)」ー二十日月。 半月に近い形でのぼってくる。一眠りしてから見る月。
「有明月(ありあけづき)」-名月からの日数ではなく、翌朝の有明空にあわくかかる月。
また、名月を遡って前日の月(八月十四日の月)は、「待宵の月」、「小望月」と呼び、待つ心を大切にしました。
これらの他にも、名月の一ヶ月後は十三夜が良いとされ、九月十三日の月は「後の月」という名がついています。

長月の一品をご紹介
秋は食欲の秋、美味しいものを食べることはみなさんの楽しみ。
今年のサンマは脂がのっているとか、松茸は食べつことできるかな・・・食いしん坊談義は事かきません。
そんな中、「和心美人」でご紹介されている素敵な一品をご紹介。
「空也蒸し(空也豆腐ともいいます)」です。ご存知ですか?
お豆腐を月に見立てて、まぁるく仕上げました。
もともとは、「四角いお豆腐を、お寺のお堂に見立て」お堂の周りを、空也念仏を唱えながら踊りまわるようすを模して作られた料理名だといわれています。
他にも、空也派の僧がよく拵(こしら)えていたので、その名を「空也蒸し」としたとかいくつもあります。
完全食品といわれる「卵」と平安時代には中国から伝わったといわれる大豆イソフラボンがいっぱいのお豆腐との一品。
秋の名月を眺めつつ、月に見立てた茶碗蒸しで、縁側で一杯なんてオツですね。
こんな風に、のんびり、ゆったりと過ごせる幸せを味わってはみませんか。
(文参考・写真:「和心美人」長月の行事食は・・・?」より)

ありがとうございます
それにしても、月に対する美意識は、お国柄や風習によって違うらしく、その違いはそれぞれの国の古典文学に著されています。
シェークスピアが主人公に言わせる有名な科白(せりふ)。
「日毎に形を変えてゆく不実な月に、愛を誓ってはいけない。」
漢詩に使われた月の表現には、月の形よりも月の明るさを讃える「明夜」「明月」「月光」などの言葉が多いです。
中天に輝く満月や、美女の眉を思わす三日月のように、くっきりと輪郭の濃いい月が好んで詠まれているようです。
さて、では日本人の場合はどうでしょうか。
数寄者風流人の兼好法師は、「徒然草」に
「花は盛りを 月は隈なきをのみ 見るものかは。
雨に向かひて月を恋ひ、垂れ籠めて春の行方知らぬも、なほあはれに情け深し。
咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころ多けれ。」
と書きとめ、日本人ならではの美感に標識をたてています。
現代語訳しますと
「花は満開のときだけを、月は雲りがないのだけを見るものであろうか、いやそうではない。
降っている雨に向かって(見えない)月のことを慕い、すだれを垂らして室内にこもり春が移り行くのを知らずにいるのも、やはりしみじみとして情趣が深い。
今にも咲きそうな梢、花が散ってしおれている庭などにこそ見るべき価値がたくさんある。」
いかがですか。
風情豊かな日本の心。
見えないものにまで心に姿をうつして愛おしむ。
大切にしたい心です。
今日のお月さまは、月齢10.4、半月から少し丸くなってきました。
今宵はお月さまを見て、そして、目を閉じて、心に何かをうつしてみてはいかがですか。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
これからも浄住寺共々、宜しくお願いいたします。
(初版2014.09.01:再編2017.09.01)
参考:
今日は重陽の節句
旬を先取り
今宵は中秋の名月、お月見ですね
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld