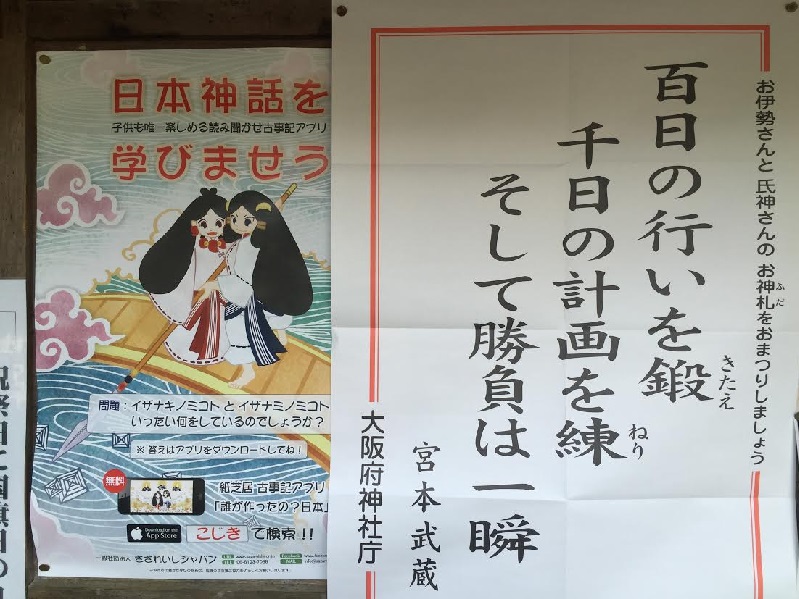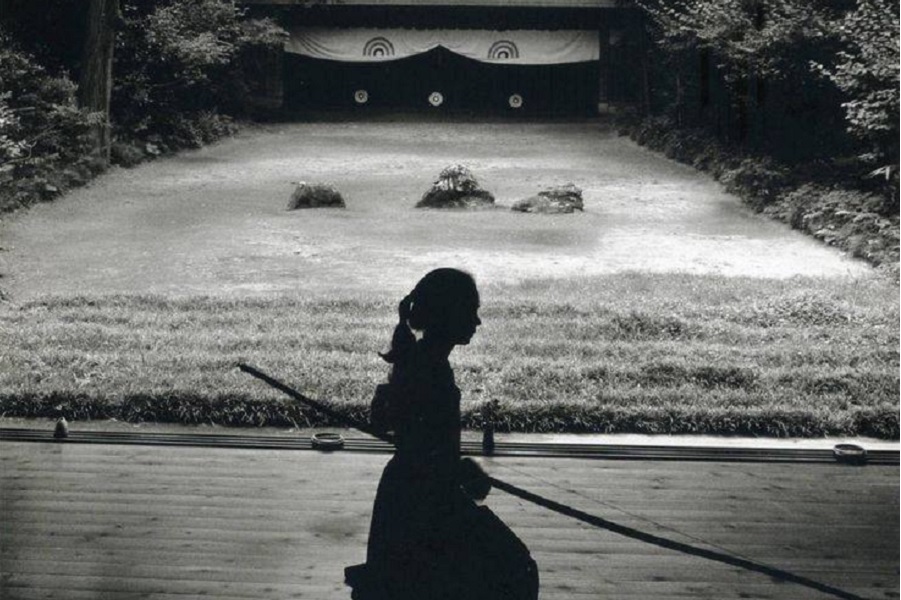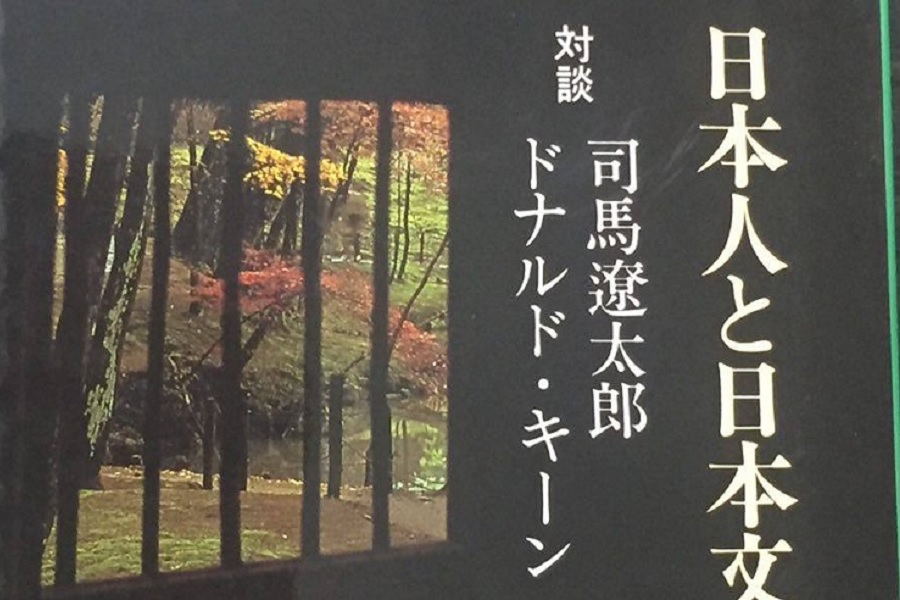枚岡神社 二六七十余年の太古の聖域

枚岡神社
こんにちは。
私にとって大切な神社のひとつ。
叔父が春日大社の宮司になる前、平成4年から2年間、宮司をされていた神社です。
叔父もここから、神の道に進まれたのですね。

ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
天種子命
枚岡神社の創祀は、初代神武天皇が大和橿原の地で即位される前、皇紀前三年(今から二六七十余年前)と伝えられています。
神武天皇が御東征の砌(みぎり)、勅命を奉じて天種子命(あめのたねこのみこと、天児屋命(あめのこやねのみこと)の孫。中臣(なかとみ)氏の遠祖)が国土平定を祈願し、天児屋根命・比売御神(ひめおおかみ)の二神を本殿背後の霊地、神津嶽に祀られたのが始まりです。
その後、幸徳天皇白雉元年(六五十)に中臣氏である枚岡連等により、現在の場所に奉還されました。
称徳天皇神護景雲二年(七六八)に天児屋根命・比売御神の二神が、春日大社に分祀されたことから「元春日」と呼ばれ、その後、武甕槌命(たけみかづちのみこと)、経津主命(ふつぬしのかみ)の二神が増祀され四殿となりました。
また、延喜式神名帳では、名神大社に列せられ、中世には一宮制度の成立で河内国一之宮となり、明治四年(一八七一)に官幣大社に列せられました。
二六七十年の太古の聖域。
長い歴史と信仰の中で育まれた数々のご神事。
この世に生かされていることに感謝し、枚岡大神様の広大無辺の御神徳にふれて、幸せな家庭を築きましょう。
社務所のお部屋にマークさんの奉納の絵が飾られてました。
そして、参道にはさざれいしジャパンのポスターも貼って頂けてました。
本当にありがたいことですね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld