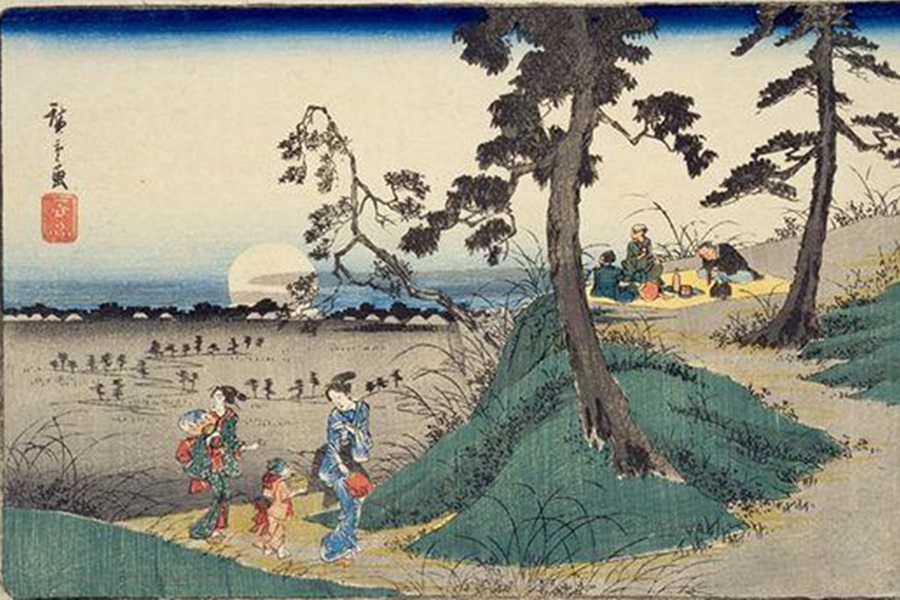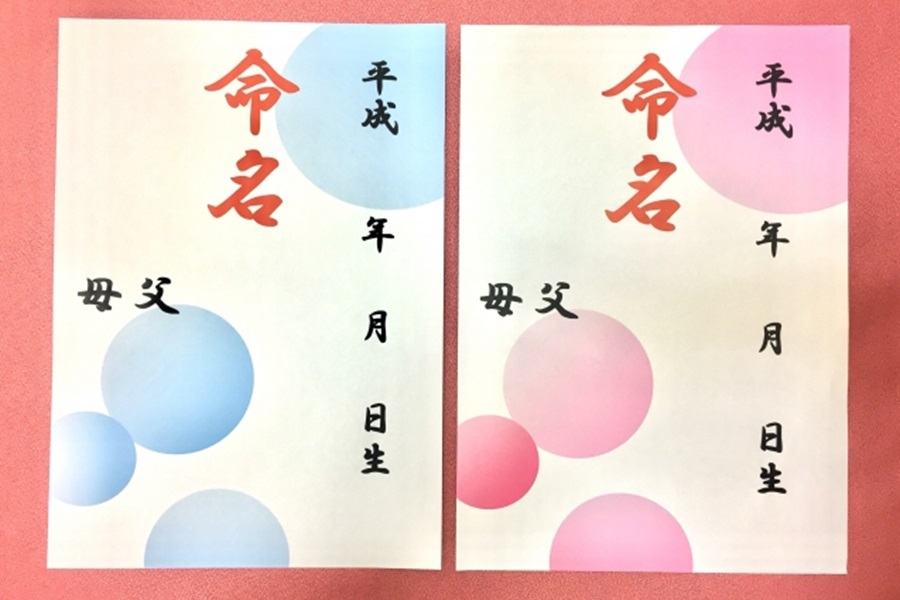丙申歳 大きく時代が変わりはじめます

60年前は?
こんにちは。
昨日、素敵な学びをいただきました。
黎明塾の中山貴英先生のお話です。
60年ごとに時代は大きく変わっていきます。
60年とは干支が一回りする年月、生まれてから60年、還暦ですね。
今から60年前は1956年、昭和31年。
「もはや戦後ではない」と国が宣言しました。
戦後の低迷からGNPが過去最高になり高度成長へと進んでいきます。
この60年で生活に必要な全ての物が生まれました。
そう「経済優先」、「お金」の時代。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
その前の60年は?
1896年、明治29年。
1894年から1895年の日清戦争から日露戦争、第一次世界大戦、そして第二次世界大戦。
「武力」「力」の世界でした。
これからの60年は?
世界が優しくなる時代です。
競わない、争わない、相手を思いやる、気づかう時代です。
そう、「和」の時代です。
黎明塾 中山貴英さんの巻頭言辞より
「ならわし」、そして「しきたり」これらは現代日本ににおいてはもはや因習にとらわれ生活の規範のような扱いでしかないのではないだろうか。
不自由そうであり、古臭く、何より現代社会に適合しなくなったために忘却されたかのように見える。
例えば「二十四節気」「七十二候」、そして「雑節」。
太古の暦はもはや一部の人々だけ(茶人や伝統芸能の世界)に通用する高尚な趣味に過ぎないのではないか。
日本が近代化の道を進み始めてまだ150年に満たない。
とくに近年この60年のそまざまな仕組みの返還と意識の変化は、ひとつの国が経験したものとしては大変大きかった。
幸いにして日本は、経済的に豊かになった。
私たち日本人は、その間に多くのものを忘れ去り、多くのものを捨て去った。
前へ前へ、早く早く、と急ぐあまり捨てなくてもいいものを捨ててしまい、忘れてはならないものを忘れてしまったのではないか。
そう自問しなければならない時期にさしかかったのである。
ありがとうございます
東日本大震災から5年が経とうとしている。
この未曾有の出来事とその後の時間の経過は、日本人が忘れてしまった大事なことは何か、日本人が捨ててしまった大切なものは何かと問い直している。
多くの人が取り戻そうとしているもの、それは「ならわし」や「しきたり」に象徴される「和」の心で、日本人の生活観の基礎となるものである。
そして、その底流には二十四節気や雑節という自然と対話することによって自然の恵みを受けていた時代の自然観と世界観がある。
ただ単に復古や復帰を声高に叫ぶことではなく、古来より受け継いできた文化を自然に身につけること、それが自然と調和して豊かに生きていることほかならない。
みなさん一緒に学びませんか。
忘れてしまった日本の素敵なことを。
こころから豊かな人になりませんか。
お待ちしています。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld