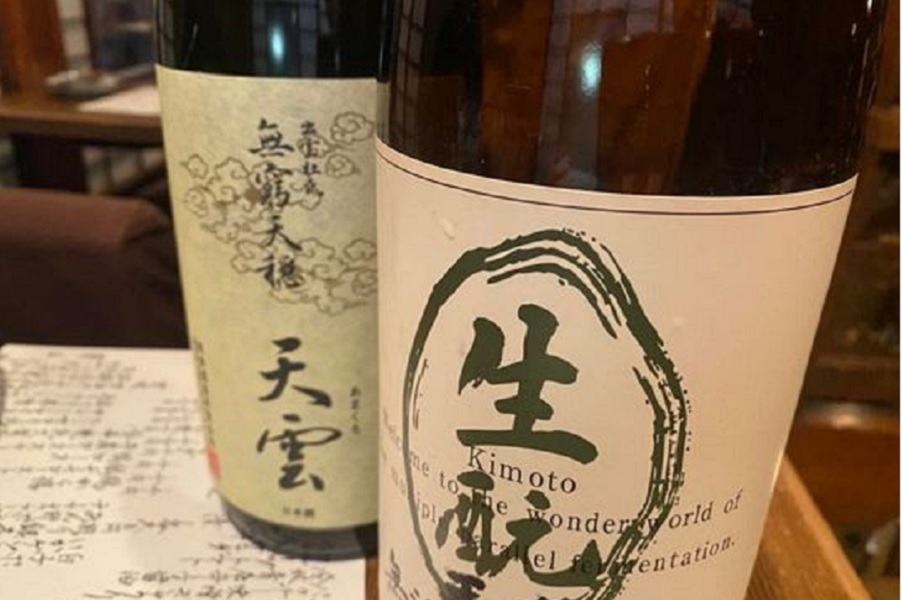「やまとことば」 日本人のおおらかさから生まれました

「やまとことば」とはどんな言葉?
こんにちは。
やまとことばには、そのことばの指す意味が広いという特徴があります。
これは、中国語とくらべると違いがよくわかります。
順を追って説明しましょう。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
訓読みとは
大昔に中国大陸から漢字が伝わってきたとき、当時の日本人は数多くのやまとことばを対象にして、意味の近い漢字をあてるという方法を発明しました。
それが訓読みです。
例でいえば、「湖」という漢字は、やまとことばの「みずうみ」と同じ意味だとわかったので、「みずうみ」という訓読みをするようになったわけです。
当時の大陸の発音である「コ」は、音読みとして残りました。
同じように、「食」という漢字は、やまとことばの「たべる」ことと関係しているということで、「たべる」という訓読みをするようになりました。
そうした訓読みを見ていくと、興味深いことがあります。
1つのやまとことばに対して、2つ以上の漢字があてられていることが、よくあるのです。
たとえば、「はかる」というやまとことばには、「計る」だけでなく、「量る」「測る」などの漢字が使われています。
いわゆる「同訓異字(どうくんいじ)」「同訓異義語(どうくんいぎご)」というもので、学校で習った覚えのある人もいると思います。

やまとことばは「言霊」を大切にしています。
なぜこのようなことが起きたかというと、漢語では、長さをはかるとき、重さをはかるとき、気温をはかるときなどで、別々の漢字を使っていたためです。
ところが、やまとことばでは、長さも重さも気温も、すべて同じ「はかる」ということばで済ませていたのです。
同じようなことは、「うつす」というやまとことばにもあてはまります。
「うつす」には、「写す」「映す」「移す」のように、いくつもの漢字が使われています。
確かに、「写す」と「映す」はだいぶ意味が似ているとおわかりでしょう。
「移す」はちょっと違うかなと思うかもしれませんが、共通の意味を考えることはできます。
「あるものを、そのままの姿で別の場所やものに置き換える」という意味です。
そうした広い意味で使われていたために、「写」にも「映」にも「移」にもあてはまったということなのです。
(文:本「やまとことば50音辞典」著高村史司 より)
ありがとうございます
最近は「超すごい」「マジやばい」といった言葉が若い人たちの間で沢山使われるようになってきました。
「超おもしろい」はやまとことばに直すと「このうえなく面白い」になります。
平安時代に戻ったような雰囲気になりますね。
好きな人がいることを伝える場合には「心を寄せる人がいます」といいます。
テレビで見る皇室の方々のお話しかたが正にこれですね。
やまとことばを使うことで、言葉に気品が出てどことなく丁寧な相手に嫌なイメージを与えない印象になってきます。
やまとことばは言霊といわれる音を大切にしている言葉だからかもしれないですね。
ぜひ声に出して言葉の一語一語を感じ取りながら話してみて下さい。
きっと貴方の魅力もアップするはずです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld