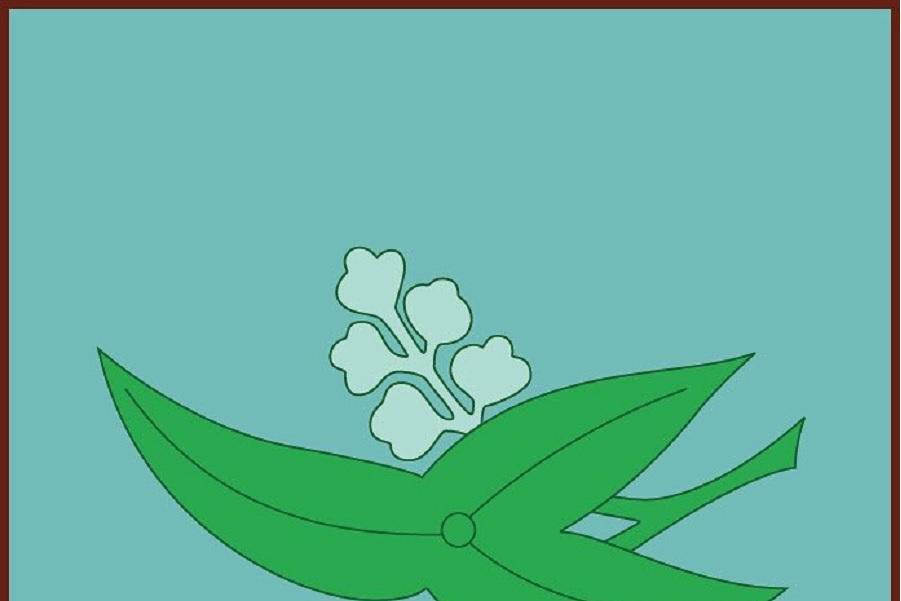江戸中期の煎茶家 大枝流芳

大枝流芳(おおえだりゅうほう)
こんにちは。
今日は香道家で煎茶家の大枝流芳のお話し。
江戸中期の煎茶家に大枝流芳(おおえだりゅうほう)という人がいます。
青湾が号です。
中国の煎茶に関する記事をまとめ、『青湾茶話』という煎茶仕様集を編集しました。
1756年のことです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
日本の茶書を記す
『花の時 月の夕 茗盌(ちゃわん)を啜(すす)り 以て清興(せいきょう)を助け酒杯を把(は)りて幽情(ゆうじょう)を開く 此を舎(す)てて 又奚(なん)ぞ求めんや』
清興(せいきょう) 上品で風流な楽しみ。
把(は)りて 手に取って。
幽情(ゆうじょう) 奥深き心。
この詩はその序に挙げられているものです。
煎茶家という時の煎茶が指すものは、茶業でいう煎茶の括りと少し違います。
抹茶という茶道に対して、葉茶を使う喫茶を好む人を茶道家というほどでないにしても、煎茶家と呼ぶという感じでしょうか。
扱うお茶は、茶業でいうところの緑茶いろいろ。
つまり、煎茶も釜炒り茶も番茶もというところ。
いえいえそれどころか、『青湾茶話』には、紅茶も記されていますし、大枝流芳は抹茶の茶道でも大家でしたから、つまり、お茶に関して多種多様を心得ていたのです。
同じような時代、佐賀に生まれた売茶翁が万福寺を訪ねるのは13歳の時です。
隠元さんが入滅されて15年ほど後のこと。
佐賀ではすでに釜炒り茶は飲まれていましたが、明調の萬福寺で味わうお茶は、若き菊泉(売茶翁の幼名)にどのようなメッセージを与えたことでしょう。
釜炒り茶は、隠元さんより以前、1406年に栄林周瑞が霊厳寺(福岡県八女)に茶の種と共にその製法を伝授したとも、1504年に紅令民が佐賀嬉野に南京釜を持ち込んだとも伝えられていますが、中国風のお茶を飲む仕様は根付いてはいなかったのです。
喉を潤すだけのものではないお茶。
江戸中期になって、ようやく青湾や秋成がきちんと中国の茶書を繰った上で、日本の茶書を記すようになるのです。
目次の中にある「良友」の文字が、茶とは何かを伝えているようです。
(文:上原美奈子さん 茶の葉の声に耳を澄ませて)
ありがとうございます
大枝流芳の本名は岩田信安、本姓は大江、大枝流芳は版本の筆名。
号は漱芳ほか、多く隠逸趣味を反映しています。
流芳は難波でも由緒ある家格の富家の出身。
多病のため世事から離れ京都に享保年中まで隠棲し貝合から始まりさまざまな雅遊の故実について漢籍・古典を渉猟し筆録し考察を加えていました。
大坂に本拠を移したのは享保15、16年。
香道への関心を強めたのはその頃でしょうか。
享保17年御家流の口伝を受けていた大口含翠に香道伝授を願って弟子入り。
含翠の香道三流に通じた解釈と幅広い知見と多くの伝書の提供を受けた流芳は、含翠とともに伝統的な公家の雅びの世界としての香道御家流を新たに作り上げました。
1730年代に多数の香書を書き,そのほか茶書『貝尽浦の錦』『本朝瓶史抛入岸の波』『雅遊漫録』『青湾茶話』 (煎茶の書) を出します。宝暦5 (55) 年には没していたらしいです。
花道,煎茶道にも明るく,いわゆる文人。
売茶翁と共に、教えを乞いたい人です。
もっともっと学ばなければ。
今日もありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld