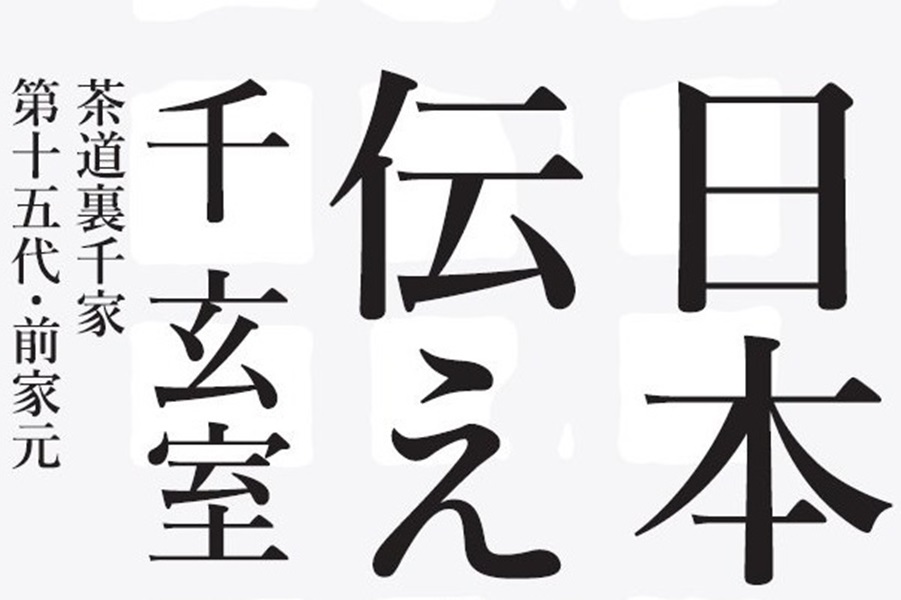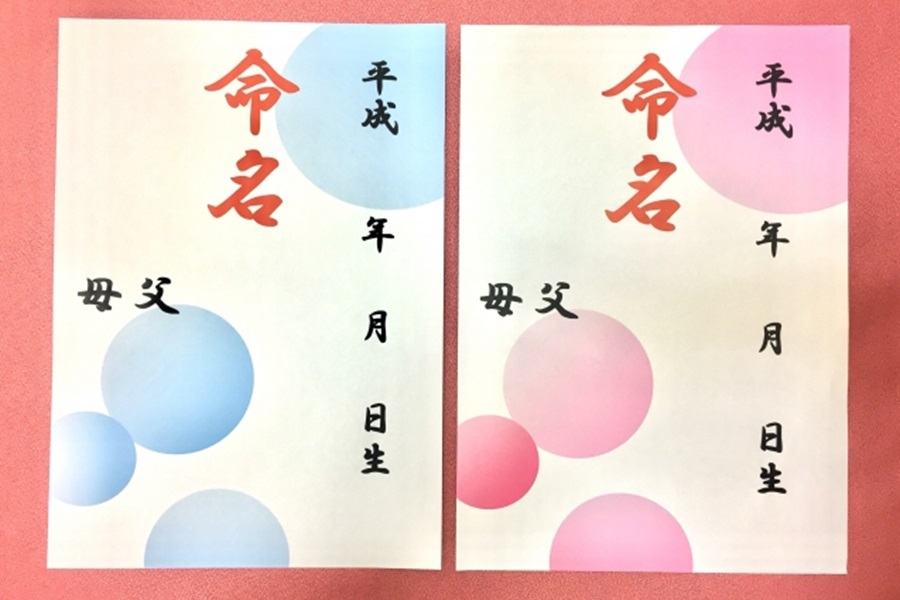夏の季語で俳句を作るときに入れたいもの

あなたの夏は何?
こんにちは。
夏の季語を思い浮かべると、どこに居ても暑いイメージがするのですが、俳句を詠んでいくにつれて涼しげで爽やかな雰囲気を感じさせてくれます。
俳句を作る時は夏の季語をいれますが、たくさんある中でどの言葉を持ってくるかを考えるのも楽しさではないでしょうか。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
夏と聞いて思い出すものとは
夏の俳句を一句詠もうとする時、夏の季語を思い浮かべてから五七五に語句を組み合わせていきますよね。
俳句の季節の区切りは旧暦になりますので、現代の感覚に少しズレを感じることがあります。
旧暦では5月から7月までを夏と捉えていることから、「柏餅」も「こどもの日」も夏の季語になっています。
確かに、5月は青々とした草花を目にする機会も増えて、初夏らしいようにも思えますね。
「朝顔」も夏の季語に感じてしまいますが、秋の季語に含まれます。
うっかりしていると、間違えてしまいそうになりますね。
水遊び
日本の夏をイメージしていくと、季語に「水遊び」を入れると涼しげな夏の思い出を想像できます。
水遊びの背景には、何が見えて何を感じたかを自分の表現によって、一つの世界を作り出してみたくなりますね。
子供を眺めているのか、自身が子供の目線となってはしゃいでいる風景なのか。
胸が躍るような嬉しさに、懐かしさだけでなく直接川辺へ足を運んでみたくなりますね。
花火
夏の季語らしい「花火」も、日本の夏を思い浮かべる句が出来そうな気がします。
夜に打ち上げられる大きな花火や、線香花火のように下を向きながら余韻を楽しむ手持ち花火など、花火をお題にした俳句もとても風情を感じますよね。
花火を見つめる時に、何を思うかを感じたままに表現するのも面白さを感じるのではないでしょうか。
向日葵
太陽のような大きな「向日葵」も、夏の季語にふさわしい印象がありますね。
真夏に虫取りに出掛けると、向日葵の花が空き地に咲いていたのを思い出しませんか。
学校でも、向日葵を種から栽培して日記に書いていたこともありました。
夏の植物として、取り入れると明るい俳句が作れそうな気がしますね。
花束に夏をイメージしたものをと花屋さんに告げると、向日葵を選んで下さるところが多く、夏のイメージとして定着している花だと実感します。
夕立
「夕立」も夏の季語として、俳句を引き立たせてくれる言葉です。
最近では、夕立というよりもゲリラ豪雨なんていう言葉を聞くことが多くなりましたが、通り雨のような一時的な雨に遭遇すると、良い一句が浮かびそうですよね。
幼い頃は、気温が高く蒸し暑い夏の午後は夕立が降ると言われて、気を付けて外遊びをしたものです。
目で見て懐かしむこともありますが、文字に記した時に、季節を感じイメージが膨らむこともありますよね。
夕立は、まさに文字に書き記した後から、あの風景を想像できる言葉ではないでしょうか。
夏草
夏の季語に「夏草」がありますが、夏草と言われて目を閉じて想像すると、生い茂った草や原っぱが脳裏に浮かんできます。
今では草木が生い茂った場所を探し出すことも難しい時代になってきましたが、公園のすみっこ学校の木陰などに夏草を見掛けることがあります。
身近にあった当たり前の景色も、時代の流れと共に探し出すのも難しく感じますね。
ありがとうございます
サングラスやラムネ、パイナップルなど、カタカナの言葉も夏の季語として親しまれています。
俳句と聞くと、漢字とひらがなを用いたものとのイメージがありますが、カタカナの季語もたくさん存在します。
俳句は、楽しく言葉を紡いでいくものです。
いろいろな季語を集めるだけで、新たな俳句も浮かびやすく創作意欲にもプラスに働きかけます。
面白いと感じることが、俳句を楽しむコツではないでしょうか。
夏の季語を選びながら今年の暑い思い出を振り返ると共に、夏らしい一句を詠んでみたくなりますね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
<関連記事>
日本の夏の工夫「水は涼しい」
夏の風物詩と聞いて思い浮かぶもの
「日本の夏の工夫」
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld