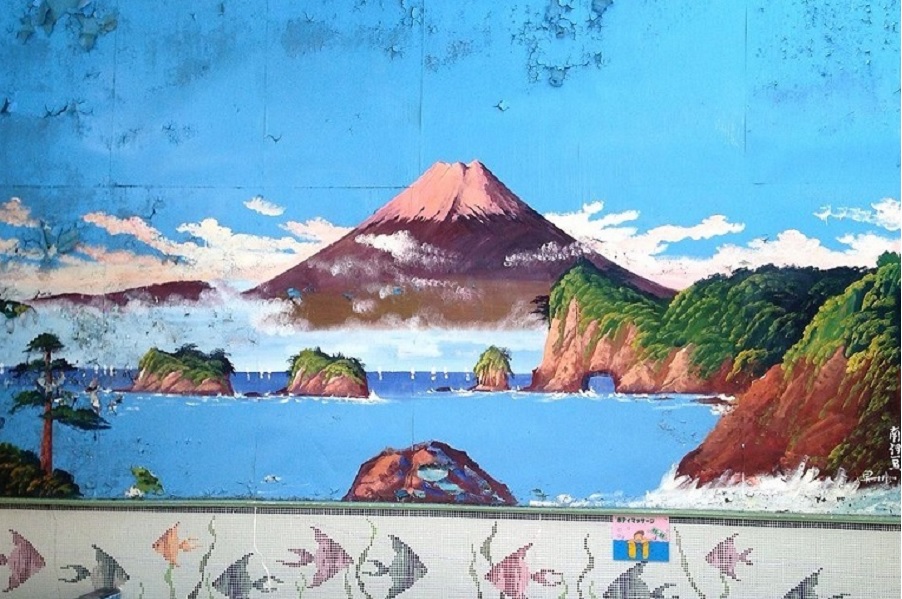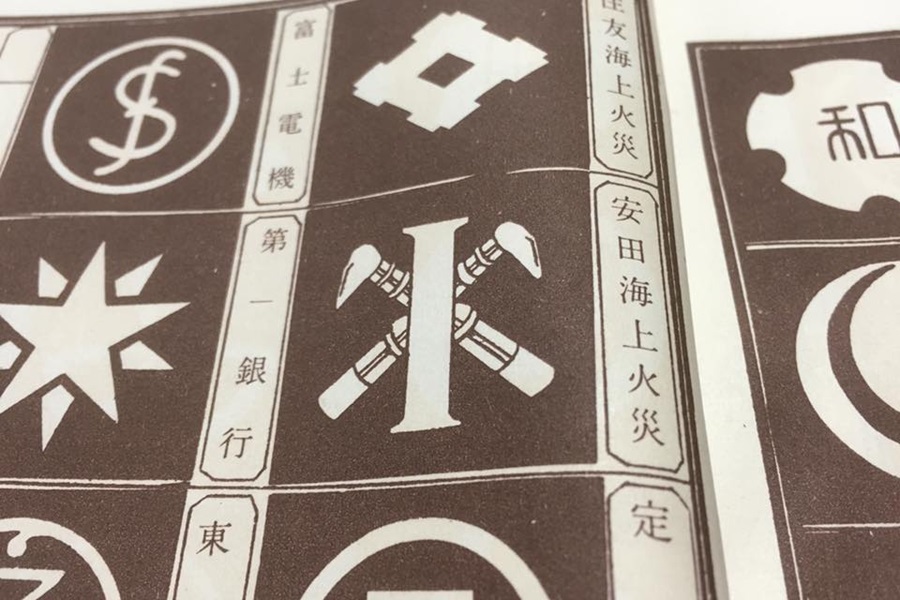刺青と歴史上の人物の関連性について知ってみよう
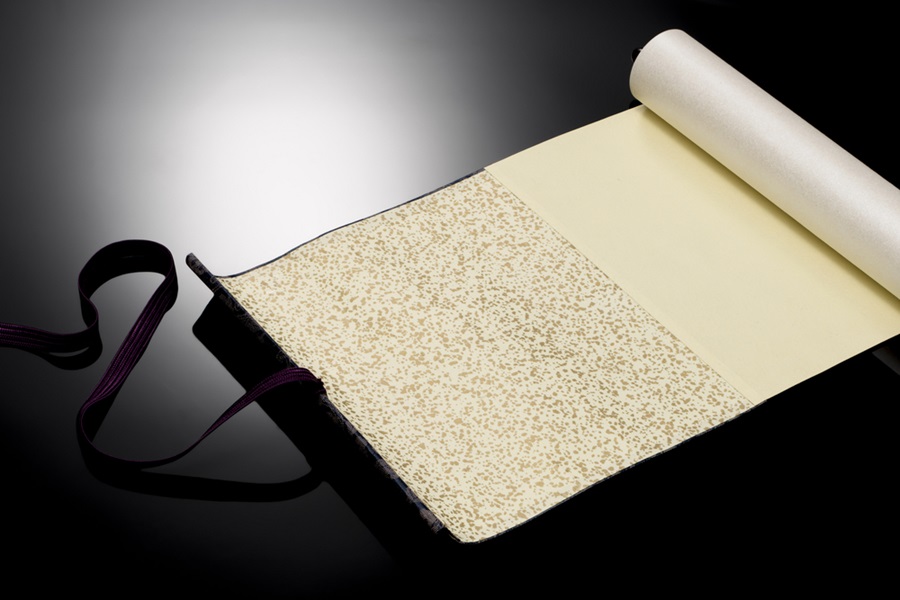
噂のような刺青
こんにちは。
刺青は歴史上の人物ともかかわりは深いと言いますが、詳しいことがわからないまま謎が多く残されています。
見せるための刺青と言いますが、地域によっては意味合いも違うため、噂のような形で歴史上の人物の名前が挙がっていることも。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
大久米命
大久米命は、久米部という軍事的な部民をまとめていたとされる伝説と呼ばれている久米氏の祖先にあたる人物。
古事記によりますと、神武天皇の警護として活躍した大久米命は、目の周りに刺青をしていたとの記述が残されています。
後に、大久米命は神武天皇のお妃を紹介したということで、強くて人脈もある人柄が伺えますよね。
諸説ですが、神武天皇も刺青をしていた歴史上の人物ではないかと言われているそうです。
四代目中村歌右衛門
刺青を入れた歴史上の人物で知られているのが、歌舞伎役者の四代目中村歌右衛門。
小柄な役者だった中村歌右衛門は、舞台で自身の演技をより華やかに大きく魅せるために、全身に刺青を入れたと言われています。
これが評判となり、多くの人が刺青に対して憧れを抱くようになりました。
ブームを作った火付け役だったのかもしれませんね。
遠山の金さんのモデルとなった遠山景元
刺青と歴史上の人物というと、テレビの時代劇でもおなじみの「遠山の金さん」を真っ先に思い浮かべます。
金さんこと遠山景元は、江戸の旗本として町奉行を務めた人物です。
大きな桜吹雪の刺青が、ドラマでは印象的でしたよね。
諸説がいろいろと残されていて、体のどの部分に彫られていたのかはわかりませんが、若い頃に興味本位で彫ったとのこと。
女性の生首が描かれていたとも言われていますが、人前で見せることはなかったと言われています。
根岸鎮衛
30年以上書き溜めたという随筆集「耳袋」の作者根岸鎮衛は、江戸時代の南町奉行を務め、刺青を入れていたとされる歴史上の人物。
奉行所時代から書き溜めていた作品は、周囲から聞いた奇談を綴ったとのことですが1000編にも及ぶ大作です。
ここから生まれた怪談話を、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
松平定信にも気に入られていたという根岸鎮衛は、人当たりが良く出世も早かったそうです。
断れない性格から、頼まれごとが多かったのですが、聞き入れるだけで行動しなかったというお調子者の一面も。
火消しの出身ではないかとの噂もあり、見せないようにしながら役職を全うしたと言われています。
内田正容
江戸時代の後期の大名に、刺青をした歴史上の人物がいました。
下総小見川藩の大名、内田正容は刺青の魅力に魅せられた人物だったと言われています。
全身に彫られていたとの説が残されていますが、どのようなデザインだったのか気になりますよね。
やんちゃな大名としても有名で、幕府の命令で隠居させられてしまいました。
ニコライ2世
1891年に長崎へ立ち寄った際に刺青を入れた歴史上の人物が、当時ロシアの皇太子だったニコライ2世。
親戚でもあった英国の皇太子が、一足先に日本で彫った姿を自慢してきたことを羨ましく思い、龍の刺青を彫り師にお願いして彫ってもらったという逸話があります。
青い墨の色に惹かれたとも言われ、ロシアでの和彫りへの注目が高まったそうです。
英国の皇太子も日本で彫っていたとは、日本の確かな技術が認められた証ですね。
ありがとう
江戸時代に流行ったとされる刺青ですが、歴史上の人物が刺青を彫っていたという記録がほとんどといっていいほど残されていません。
もしかすると噂話として、現代まで伝わってしまったことも考えられるでしょう。
または、明らかになっていないだけで、有名な武将も刺青を彫っていたかもしれませんよね。
時代の流れによって負のイメージが根強く、公に出来なくなってしまったことから、隠すことが多くなっていった刺青。
これから先の未来では、刺青のイメージはどのように変化していくのでしょうか。
今までの価値観も変わり、繊細で進化した技術が生まれているかもしれませんね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
日本の伝統文様 「菱」
日本の伝統色といえばこの色を思い出す
日本の伝統文様 松竹梅
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld