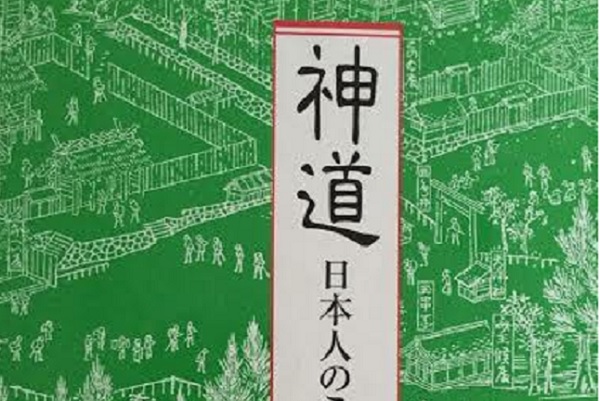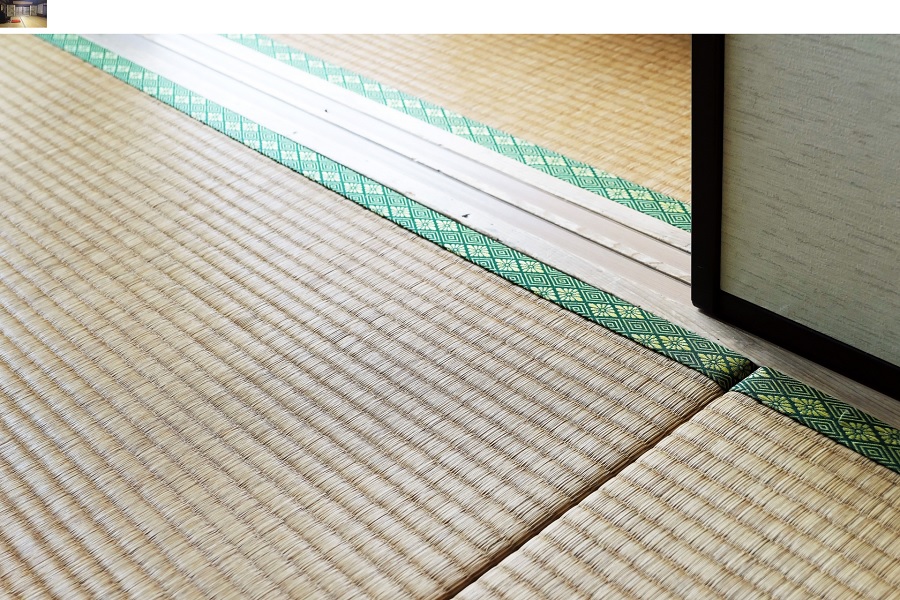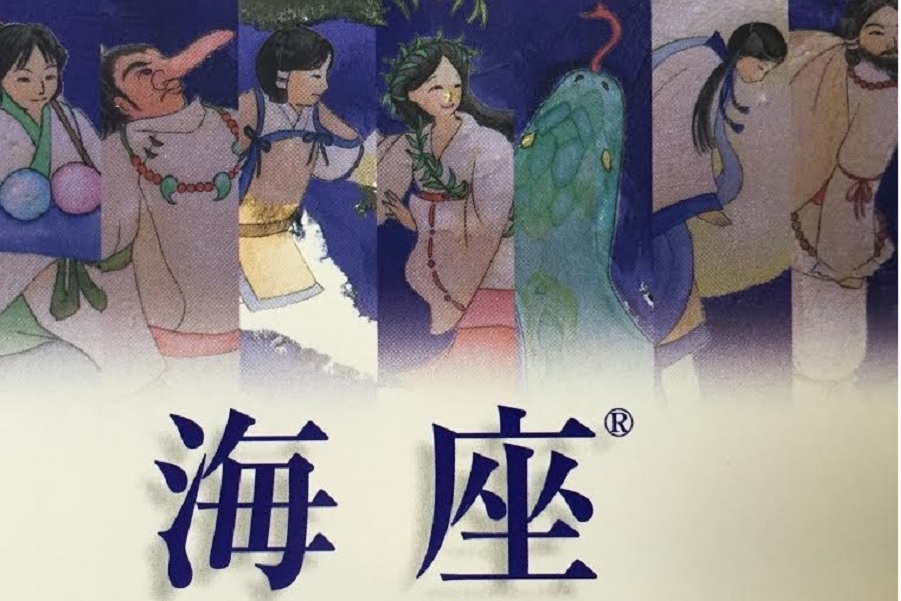赤ちゃんのお食い初めとは何?

何気なく行っているその行事の意味とは
こんにちは。
赤ちゃんが生後100日を迎えると、「お食い初め(100日祝い)」というお祝いをします。
お食い初めという名前はよく耳にしますが、いつから行われているかご存知ですか。
実はとても歴史が古い行事です。
今回はそのお食い初めについてご紹介します。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
お食い初めの由来は?
お食い初めは平安時代に赤ちゃんにお餅を食べさせる儀式が起源であるといわれています。
その頃は生後100日にお祝いするのではなく、生後50日目頃に重湯の中にお餅を入れ、そのお餅を赤ちゃんの口に少しだけ含ませるというものでした。
その儀式を「五十日(いのか)の祝い」と呼び、50日目に食べるお餅を五十日餅(いのかもち)と呼んでいたのです。
やがてお餅から魚肉へと変わり、鎌倉時代には「真魚初め(まなはじめ)」と名前を変えました。
「真魚初め」では初めて箸を使うことから「箸初め」「箸立て」「百日祝い(ももかいわい)」、とも呼ばれ、地方によっては今でもこの名称で呼ばれているところもあります。
室町時代に書かれた「河海抄(かかいしょう)」に「冷泉天皇の生後百日後に御餅を供す」と記されており、その後この風習が「食い初め」と呼ばれるようになったそうです。
平安時代から千年以上続く行事が、今も受け継がれているとは驚きですね!
お食い初めに込められた願い
お食い初めは「食べ物に一生困りませんように」「健康で丈夫に育ちますように」という願いが込められたお祝いです。
飢饉や病気に見舞われやすかった時代から、今も続く親の共通の願いでですよね。
また、歯が生え始めるまで無事に成長したことをお祝いする意味もあります。
なぜ石を用意するの?
お食い初めのお料理の中に、石を並べるならわしがあります。
もちろん実際に食べるわけではありません。
この石は、歯固めの石とよばれ、歯が石のように丈夫で堅くなりますようにとの願いから料理に添えられるようになりました。
他には、歯が丈夫で歯並びが良いこどもは顔立ちよく育つといわれていたため、美男美女に育ちますようにという意味も込められているそうです。
さらに歯が強い子は長生きをするので、長寿祈願のためという説もあります。
瀬戸内海地域では石の代わりにタコを用意することも多いですよ。
「固いタコでも食べられるくらい丈夫に育ちますように」「多幸になりますように」と様々な縁起の良い意味があります。
他にも「梅干しと同じくらいシワができるまで生きられるように」と梅干しを用意したり、「固い栗の実が噛めるほど丈夫な歯が生えるように」と勝ち栗を用意したり、地方によっても特色があります。
石はどこで用意するの?
一般的に、お食い初めの際に歯固めに使う石は氏神様のいる神社、もしくは近くの神社の、人が歩かないところに落ちている石を拾ってくることが多いです。そうはいっても、衛生的に心配なことも正直多いでしょう。
最近ではお宮参りのときにもらうことも多いですが、歯固め用の石として専用に販売されているものもあるので、購入するというのも選択肢の一つです。
大きなものを一つ用意する場合もあれば、小石を3つ用意する場合もあります。
もし神社から拾ってきた石を使う場合は、終わった後は綺麗にして神社にお返しする、というのが習わしです。
拾った場所に戻しておきましょう。
お固めの石は実際には食べるわけではありません。
ちょんちょんと石にお箸で触れ、その箸を子どもの歯茎に軽く当てながら「丈夫な歯になりますように」とお祈りをします。
これを歯固めの儀式と呼びます。
ありがとうございます
実はこのお食い初め、日本だけではなく韓国や中国でもとてもよく似た行事があります。
どの国の行事も赤ちゃんの健康と健やかな成長を願う、という共通点があります。
子を想う親の気持ちには時代も国境も関係がありません。
やり方にとらわれず、自分たちに合った方法でも良いので、記念すべきお祝いを家族でしてみてはいかがでしょうか。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
赤ちゃんのお七夜(命名式)とは何?何気なく行っているその行事の意味とは
こどもの行事~帯祝い~
寿司屋はいつからOK?子供の寿司屋デビューについて
珍しい名前に対しての子供の思いはどういうもの?
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld