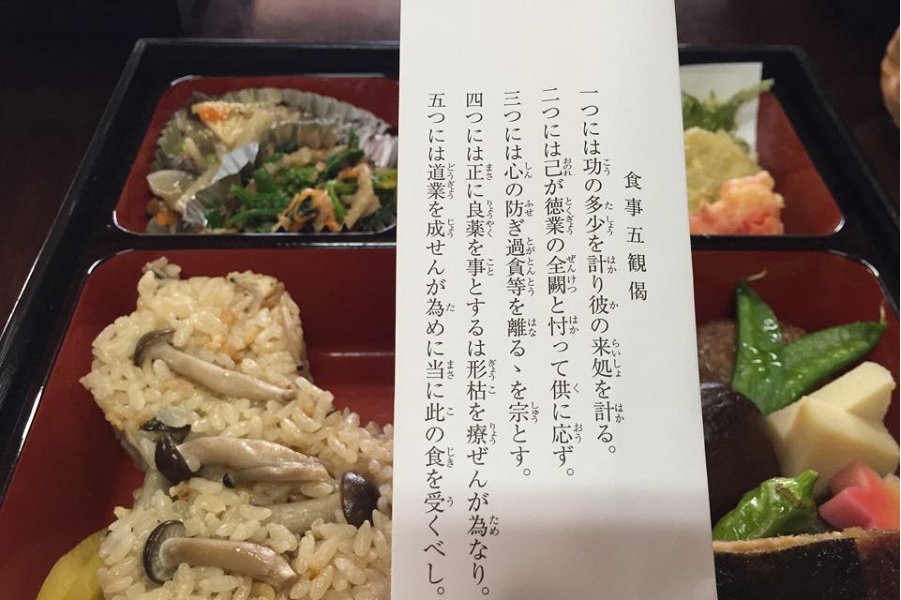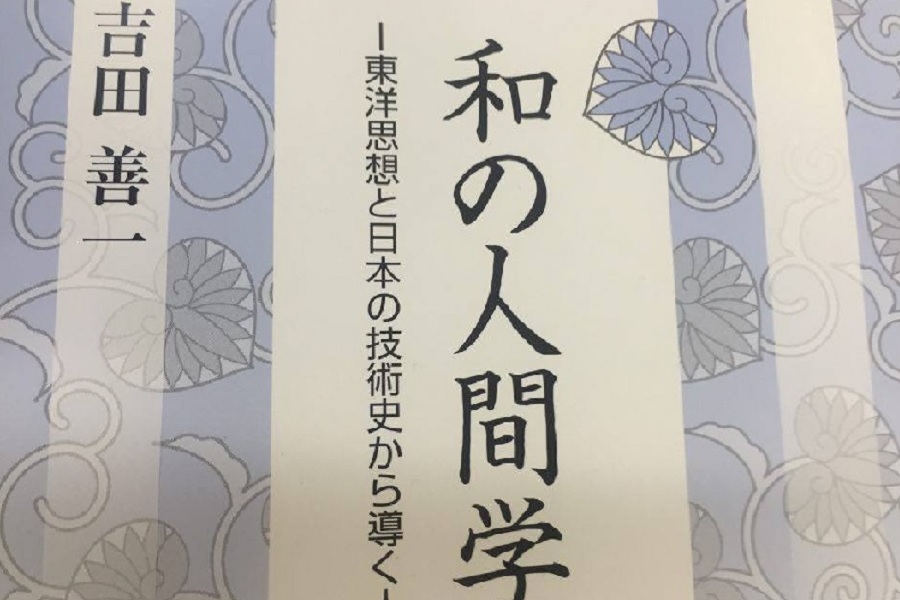喪服の色 昔は黒ではありませんでした

春は色とりどり
こんにちは。
春真っ盛りの今日この頃。
浄住寺では、さまざまな色に出会います。
桜のさくら色、新緑・若葉のみどり色、菜の花の黄色、トサミズキにドウザンツツジ・・・。
色とりどりのこの季節、幸せですね。
さて、色といえば、簡単そうで一番難しいのが「白」と「黒」
今日は喪服を鑑みながら「白」と「黒」を少し学んでみましょう。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
喪服の色に色黒をつける
昔、最初の喪服は白色でした。
人はみんな、いつか死にます。
残された人々は悲しみにくれます。
宗教儀式はいろいろありますが、故人を送り、偲ぶ会などが行われます。
その時に何を着るのか? 要するに喪服ですね。
「隋書倭国伝」(629年)には、「素服と呼ばれる白い喪服」を着ているという描写があります。
『日本書紀』にも斉明天皇崩御の時(661年)、皇太子・中大兄皇子が素服を着用したとあります。
7世紀に、喪服は白だったそうです。
奈良時代は「薄墨」
奈良時代に入り、『養老律令喪葬令(ようろうりつりょうそうそうりょう)』(718年)で、「天皇は二親等以上の葬儀に際し、錫紵を着る」と定められました。
これは、喪葬令のお手本としました。
唐の制度から持ってきたものです。
「紵」とは麻布のこと。
唐では「錫紵」とは白い麻布を指しています。
ところが日本は文献だけでそれを学んだので、「錫は金属のスズのことだから」と「薄墨」にしました。
外国の制度を文献だけで輸入する悲しさですね。
島国日本は、これ以降もいろいろな分野で、似たようなことをしてきました。
それはともかく、平安時代は、天皇にならい貴族たちも、喪服は黒系統になっていきます。
通常の服の上に、薄墨の衣を重ねて、喪服としました。
故人と親しい関係ほど濃く、遠い関係ほど薄く染めるという定めもできました。
現在も僧侶の喪服は鈍色(濃い灰色)ですが、それはここを源流にしているといえるでしょう。
室町時代は再び「白」
しかし室町時代あたりに、再び喪服は白となります。
理由は、よく分からないのです。
黒い喪服を着ていたのは上流階級だけで、実は一般の庶民はずっと白のままだったとも言われています。
薄墨とか黒は染料が必要で、手間がかかるからです。
武家の時代に入り貴族の力が衰えたので、再び庶民の白い喪服の文化が上流階級にも復活したのではないか、とも言われる。
以来、江戸時代もずっと喪服は白でした。
明治に入っても、変わりませんでした。
明治以降は?
しかし、文明開化で西洋の黒の喪服文化に接します。
早く西洋化することで世界に並びたい明治政府が、気にしないわけがないですよね。
明治11年、大久保利通の葬儀には、多くの人が黒の大礼服で出席しました。
明治30年、英栄皇太后の大喪の礼の時、外国人参列者を迎える葬儀であったため、西洋の常識に合わせ、喪服は黒とされます。
大正元年、明治天皇崩御に際し、黒の喪服の着用が決められました。
このあたりから、上流階級の喪服は黒となりました。
理由は西洋化です。
しかし、平安貴族の時と同様に、庶民はまだ白でした。
大正から昭和にかけて、一般の間にも黒い喪服が定着していきます。
理由は、近代のたび重なる戦争で葬儀が多く行われるようになり、汚れの目立たない黒になっていったのではないか、とも言われています。
悲しい理由ですね。
参考:日本の伝統の正体
ありがとうございます
白色は、穢れを清める色。
だから、結婚式に白無垢を着ます。
そして、亡くなると白の死装束。
黒は?
やっぱり、無かな。
でも、正反対のようで陰陽の関係、もっとも近い関係かもしれないですね。
難しい!
白と黒、白黒つけるのも大切かもしれませんが、白黒つけずにグレーのままも大切かもしれませんね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld