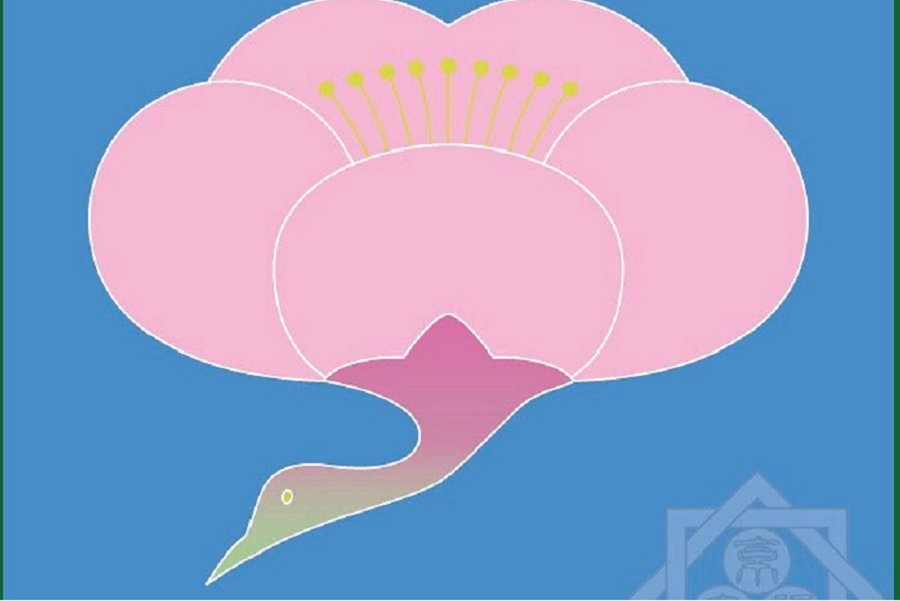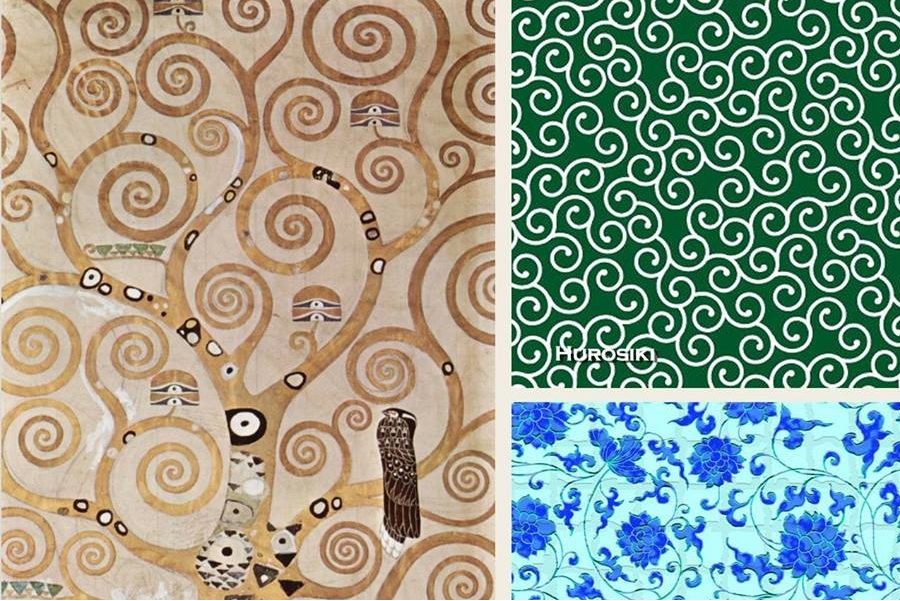梅仕事が終わると、夏がくる

梅と日本人のあゆみ
こんにちは。
日本人は昔から、梅の力を借りて夏を乗り切ってきました。
6月に「梅仕事」を終えて梅雨が明けると、夏には梅を頂くことが出来ます。
暑さが身に染みる季節、梅と日本人の歴史を振り返り、日本の風習とも言える梅仕事を、より身近に感じて頂ければと思います。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
梅のパワーと日本の夏
「梅仕事」とは、梅干しや梅酒、梅シロップなど、梅を使った加工食品の仕込みをする作業を言います。
梅の季節は1年に1回、だいたい梅雨の季節の6月頃が梅仕事の時期になります。
1年を24分割にした「二十四節気」をさらに細かく分けた「七十二候(しちじゅうにこう)」の中に、6月16日~20日ごろまでの5日間を指す、「梅子黄(うめのみきばむ)」という季節があります。
この頃になると梅の実が熟して黄ばみ、梅仕事も佳境に入ります。
そして、梅子黄が終わると夏至になり夏がやってくるのです。
昔から、梅仕事は夏を迎える準備として、日本人の生活に季節の彩りを添えてきました。
「梅仕事」で仕込んだ梅干しや梅酒、梅シロップには梅のパワーが凝縮されています。
特に梅干しは、時に薬として重宝されていたほどです。
梅の酸っぱさの源であるクエン酸やリンゴ酸には疲労回復・食欲増進の効果があり、夏バテ予防になります。
また、梅の殺菌作用は食中毒を防いでくれますので、暑い季節にはもってこいです。
最近では、梅の成分に脂肪燃焼作用があり、生活習慣病の予防に効果があることもわかってきました。
このように、梅のさまざまな効能は暑い夏を乗り切るために必要なものばかりです。
そんな夏の準備として行う6月の梅仕事は、とても理にかなった作業と言えるのではないでしょうか。
梅と日本人の歴史 ~万能薬から庶民の食卓へ~
では、梅はどのように日本人の生活に溶け込んでいったのでしょうか?
梅の始まりには諸説ありますが、多くの文献では弥生時代に中国から梅の木が伝来したとされています。
日本最古の歌集である「万葉集」には梅の歌が118首あり、桜の42首と比べても、昔から梅が日本人にとても馴染みのある花だったことが分かります。
奈良時代になると、遣唐使によって「鳥梅(うばい)」と呼ばれる梅の実を燻して作られた薬が入ってきます。
更に梅の実は、桃や柿、ビワなどと共に生菓子として食べられるようにもなりました。
しかし、当時はまだまだ上流階級の食べ物でした。
平安時代の中ごろには、梅干しの原型となる梅の塩漬けが作られます。
梅干しは薬として広く使われ、病気が流行した時には、六波羅蜜寺の空也上人が梅入りの薬茶で多くの人々の命を救ったという逸話があるほどです。
最古の医学書である「医心方(いしんぼう)」にも、動悸や熱を鎮め、皮膚病や腹痛にも効果を発揮すると記されています。
この頃の梅干しは、万能薬として扱われていたことが分かります。
鎌倉時代になると、梅干しは武家社会の中で「おもてなしの為の縁起物」として扱われるようになります。
気前よくたくさんのものを振る舞うことを「大盤振る舞い」と言いますが、この語源にも梅が関係しています。
当時、御家人が将軍に祝膳を振る舞うお正月の儀式、「椀飯振」というものがありました。
膳の上には、お椀に盛ったご飯、梅干し、鮑の干物、くらげ、調味料の塩と酢をのせたご馳走を出したとされています。
後々、この「椀飯」が語源となって、「大盤振る舞い」と言われるようになったそうです。
梅干しは茶菓子
また、梅干しは禅宗の僧の間で茶菓子として用いられていました。
お菓子というと、甘い味を想像しますが、梅干しの塩気がお茶とよく合ったのかもしれません。
戦国時代になると、梅干しの果肉と米粉、氷砂糖を練った「梅干丸(うめぼしがん)」という保存食が武将たちの必需品になります。
戦を戦い抜くうえで、梅の疲労回復効果や殺菌作用が活躍しました。
この頃、梅干しの需要が増えて、梅の木が全国に広がっていったと言われています。
江戸時代になると、徐々に梅干しは庶民の食卓にも並ぶようになっていきます。
特に現在の和歌山地方にあたる紀州の梅干しが評判を呼び、多くの梅干しが江戸へ運ばれていったそうです。
大晦日やお正月、節分など季節の節目に合わせて梅干しを食べる風習が根付いていきました。
明治時代には、戦国時代と同じように戦の場面で梅干しが活躍します。
日清・日露戦争では、食べ物としてだけでなく、薬や殺菌薬として使われていました。
白いご飯に梅干しを乗せた「日の丸弁当」は、この頃に生まれた言葉だと言われています。
明治、大正、昭和と日本国民の食卓に並んだ梅干しですが、戦争が終わりに近づくと食糧難のため梅干しの生産が停滞します。
しかし、戦後の復興とともに持ち直し、再び食卓にお目見えすることになりました。
その後、梅シロップや梅ジャムなどの加工品が作られるようになり、梅を使った料理のレシピもたくさん誕生しました。
現在では、はちみつ漬けで食べやすくなったものや、鰹節で味付けされたもの、減塩タイプなど、様々な味の梅干しが出回っています。
簡単な梅仕事をお家でも。自家製の加工品はいいことがいっぱい
既に梅仕事を終えて、梅干しや梅シロップ、梅酒の熟成を待たれている方もたくさんいらっしゃると思います。
また、梅仕事をしたことがないという方には興味をもって頂けたのではないでしょうか。
梅干しも梅酒も梅シロップも、途中までのレシピは全て同じです。
たくさんの材料や道具は要りません。保存ビンを消毒し、洗ってヘタをとり、水分をよく拭き取った梅を用意します。
そこに、塩をいれれば梅干し、お酒と氷砂糖を入れれば梅酒、氷砂糖やきび糖を入れれば梅シロップになります。
自家製の梅干しは、着色料や保存料が入っていないのでとても健康的です。
また、塩で変化させただけなので、上手に保存すれば何百年も腐らずに口に入れることができます。
実際、奈良県には400年以上前に漬けられた梅干しが現存しています。
梅酒は使うお酒によって風味が異なり、好みのお酒を造ることが出来ます。
梅酒を使った煮込み料理やお菓子作りなどのレシピも豊富にあり、料理の隠し味としても使えます。
梅酒を使えば、さっぱりとした味に仕上がり夏にぴったりです。
梅シロップなら、梅干しが苦手な方や梅酒を飲めない小さなお子さんでも、梅の栄養を摂ることができます。
牛乳やソーダで割れば、夏の喉を爽やかに潤してくれます。
ヨーグルトにかけたり、梅ゼリーを作ったり、梅パワーをおやつに頂くのもいいですね。
保存方法に気をつければ、梅干しや梅酒は半永久的に楽しめます。
梅シロップも、加熱処理をすれば半年から1年は大丈夫です。
オシャレな保存容器を選べばキッチンのインテリアにもなり、並んだビンを目で楽しむことも出来るのです。
初めて「梅仕事」という言葉を聞いた時、なんて素敵な響きなのかと思いました。
実際に梅仕事をしてみると、キッチンに梅の甘い香りが広がり、その一粒一粒に愛着がわいてきます。
日々変化する梅の様子を眺めるのは、梅仕事の醍醐味ではないでしょうか。
まだ梅仕事をされたことが無い方には、ぜひ次の梅の季節にチャレンジして頂けたらと思います。
ありがとうございます
古くからのことわざに、「梅はその日の難のがれ」というものがあります。
朝に梅干しを食べれば、一日、災難から逃れることができ、健康でいられるという意味です。
暑さが年々厳しくなる日本の夏、梅のパワーを借りて元気に過ごしたいものです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
今海外でブームになっている盆栽「BONSAI」、盆栽生活を始めるためには?
茶道を始めるには?マナーや道具について解説
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld