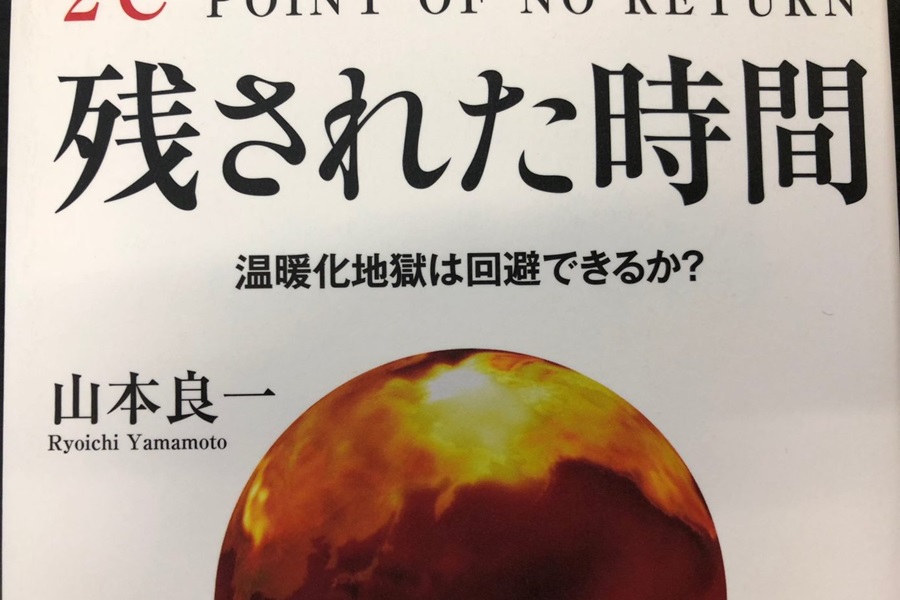盆栽を楽しむ 大徳寺 芳春院 盆栽庭園

お客さまは海外の方ばかり
こんにちは。
先日、盆栽家の森村誠二さんの「羽生本店雨竹亭」でのお話を書きましたが、京都にも森村さんの盆栽庭園があったのです。
もちろん早速行ってきました。
場所は大徳寺の中の芳春院にあります盆栽庭園です。
とてもとてもすてきな盆栽ばかり。
そしてお客さまは海外の方ばかりでした。
ここで改めて日本人と海外の方から見た盆栽も考えてみたいですね。
先ずはすてきな盆栽をご覧ください。
ほんの一部でごめんなさい。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World


盆栽とはなあに?
盆栽という言葉は「盆」と「栽」の二文字の漢字から成り立ってますが、どういう意味でしょうか。
「盆」は「おぼん」や「お皿」を意味しています。
「栽」は「木」を意味しているのですね。
これら二つを合わせますと「浅い鉢に植えられた木」となるそうです。
しかし、日本においてこれでは盆栽という意味が文化的、精神的なものとしてきちんと伝わらないですよね。
盆栽は山野にある植物を鉢の中で育てていきながら、自然界の植物の美しさ以上の美しさを求めていく趣味です。
日本の伝統的な芸術の一つでもありますね。
その根底には、生命ある植物に対する日本人の心の優しさ、きめ細やかな美的感覚が表されています。
草木を鉢に植え、花や葉の美しさだけを楽しむ鉢植えとは一線を画しています。
「盆栽」という言葉は14世紀中ごろの詩文に登場していますが、日本の盆栽の原型はさらに古く、1309年の絵巻物に見ることができます。
広く人々が楽しむようになったのは江戸時代になってからです。
(参考:web-japan)


海外で人気の盆栽
「盆栽」という言葉はよく聞きますが「私はしていますよ」という日本人は意外と少ないのではないでしょうか。
海外では非常に人気があり「BONSAI」として意味が通用するそうです。
この人気の始まりとなったのが1970年に開催された日本万博博覧会といわれています。
万博会場に設置された日本庭園の多くは外国人を魅了し、中でも一つの鉢の中の自然を表現した盆栽はひと際注目を集めたそうです。
特に、通常は大地の上でしか見られないような大木が鉢の上に表現されていることがすてきとのことでした。
そして、さまざまな技巧を凝らしても完成することのない芸術作品として大きく評価もされました。
この盆栽、2019年に輸出額は4億7900万円から2023年に9億円以上と2倍近くに急増しているそうです。
これは世界的な盆栽ブームの到来!でしょうか。

ありがとうございます
1300年ごろからあるとされる盆栽。
江戸時代になって多くの人たちが楽しむようになったといわれています。
この盆栽、いまでは海外の方のほうが楽しまれているのかな。
ここに載せた写真のようになるには何百年も多くの人の手をつなぎ渡ってきました。
本当にすてきな価値のある盆栽と思います。
ここまでするのは大変かもしれませんが、今はやりの小鉢の盆栽からでも始めてみようかな。
きっとお世話をしていくとすてきな事がたくさん起こってくるかもしれませんね。
楽しみ!
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
盆栽を楽しみましょう!

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld