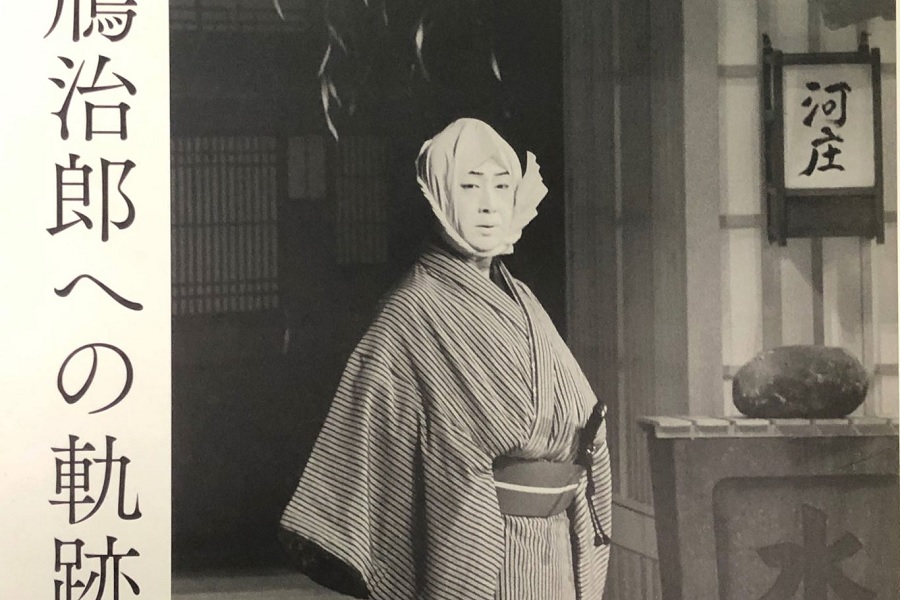型は大切、されど型にはまらず生きるもよし

型にはまらず生きることもよしかな
こんにちは。
すべてにおいて文化とは型をまるごと真似るということでしょうか。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
小学教育の事
決まっていることをそのまま「決まっていること」として受け入れる。
それを子供に伝えることが教育であり、子どもはそれを問答無用で身につけることにより文化を継承します。
だから詰め込み教育は必要なんですね。
学習とは真似をするということです。
アリストテレスは「芸術は模倣の様式である」と言いました。
文明・文化は模倣によってのみ成り立ちます。
福沢諭吉は言います。
「教育とは人を教え育つるという義にして、人の子は、生まれながら物事を知る者に非ず。先にこの世に生まれて身に覚えがある者が、その覚えたることを二代目のものに伝え、二代目は三代目に授けて、人間の世界の有様を次第次第に良き方に進めんとする趣意なれば、およそ人の子たる者は誰れ彼の差別なく、必ず教育の門に入らざるをえず。」
ーーー小学教育の事ーーー
俺の考え
理論、理屈は、型が身についたあとについてくるものです。
自転車に乗れるようになったあとに、「自転車に乗るというのはどういうことか」が言語化できるわけです。
それでも完全に言語化できるわけではありません。
経験しなければわからないことがあります。
そもそも言語で表現することができるのは、ほんのわずかな領域に過ぎません。
感覚に関することはほとんど模写できません。
本田宗一郎は、「りんごの味でさえ言語化できない」と言いました。
「りんごの味はどんなふうな味だといってみんなに聞いたところで、おそらくりんごの味はこれだという適切な言葉はない。こんな簡単な質問だって、世の中の人が納得できるりんごの味の表現はない。言葉というのは便利なものだと思っても、思うところの十分の一もいえない。」
ーーー「俺の考え」---
ありがとうございます
だから、考えるのではなく、繰り返し練習することが大切なのです。
あらゆるものは型でできています。
教育とは教養人たる型が身についているかどうかです。
(文:箸の持ち方・適菜収)
今日は浄住寺で煎茶のお稽古。 繰り返し繰り返しお稽古してきます。
今日もありがとうございます。
(元文:2014.06 再編)
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld