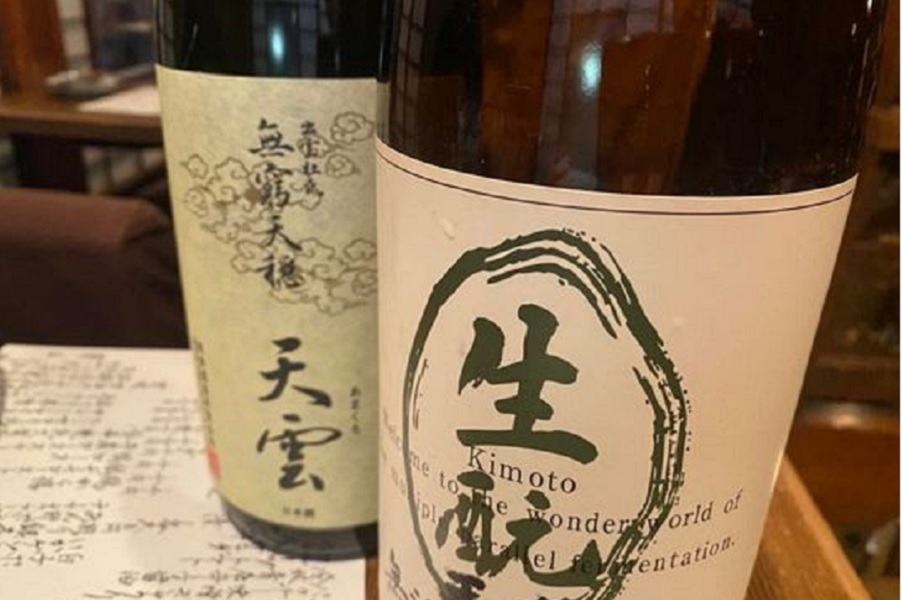日本語が世界を救う!

国や言葉は違っても、結局我々は繋がっている
こんにちは。
「日本語が世界を平和にするこれだけの理由」という本(著:金谷武洋さん)。
日本語の素晴らしさをカナダでの日本語を教えながら感じられたことが書かれています。
その中に
「2007年の夏に、久しぶりに訪れた広島で私は、「世界平和への思い」を強くしました。
具体的には、平和公園の中の慰霊碑の碑銘「安らかに眠って下さい、過ちは繰返しませぬから」を見た瞬間です。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
世界平和への思い
以前から、この二つ目の文を巡って「一体、過ちを繰り返さないと誓っているのは誰なのか」という問題が起きたことは知っていましたが、その日、広島に身をおいて、ふと私には、「誰の過ちか」が明らかにならない方がかえって日本語らしくていい、と思えたのでした。
つまり本書で注目してきた「わたし」と「あなた」の共存が、ここでは「敵」と「味方」の共存という形をとっているということに思いついたのです。
そう考えれば、敵はいつまでも敵ではなくなります。
国境を越えて、広く地球という一つの星の上に共存する人類というところまで連帯の輪を広げてゆくなら、戦争という異常な状況に敵もまた当事者、そして被害者として巻き込まれていたと考えられるからです。
確かに戦争では、ほんのひと握りの人たちを除いて、敵も味方もほぼ全員が犠牲者と言えるのです。
「正しい戦争」などというものはありません。
「結局、人は皆などこかで繋がっている」という想いは、同じ2007年夏の帰国旅行で、広島に続いて訪れた沖縄でさらに強くなりました。
我々は繋がっているのです
慰霊碑の大きさより、もっと驚いたことがありました。
何と、その慰霊碑には、戦死したアメリカ兵の名前も刻んであったのです。
以前米国の首都ワシントンでベトナム戦争の戦死者の名前が刻んである巨大な慰霊碑を見たことがありますが、そこには当然ながらアメリカ人の名前しかありませんでした。
私も同じように沖縄に墓参りに来ていたアメリカ人の姿を見て、私は、広島と沖縄の慰霊碑には共通する思想があることに気がつきました。
それは、国や言葉は違っても、結局我々は繋がっている、という「共存、共視の思想」であって、その「共視」の思想は日本語そのものに根っこがあるのだ、ということです。
それがこの本でお伝えしたかった日本語の「共視」の思想です。」
ありがとうございます
そうなんです。
我々は繋がっているのです。
国々としてみるから違う人たちになるのですが、地球という星でみるとみんな一緒の人類。
日本の昔の人たちは、もちろん、この地が丸くて大きくていろんな人がいることは知らなかったでしょうが、誰かが偉いわけでもない、悪いわけでもない、みんな一緒、繋がっているんだと無意識の思っていたのでしょうね。
それが言葉を発するようになっても、そこに心が、思いがついてくるから、素晴らし日本語になるのです。
外国語をならうのも現代には必要かもしれませんが、この素晴らしい日本語をもっと楽しみませんか。
そう、和歌などよんでみませんか。
とても素敵なお話し、ありがとうございます。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
(写真は葉室山浄住寺の亀甲竹)
正しい日本語の使い方 枻(えい)出版
日本語って?
叔父の教え 正しい日本語を伝える
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld