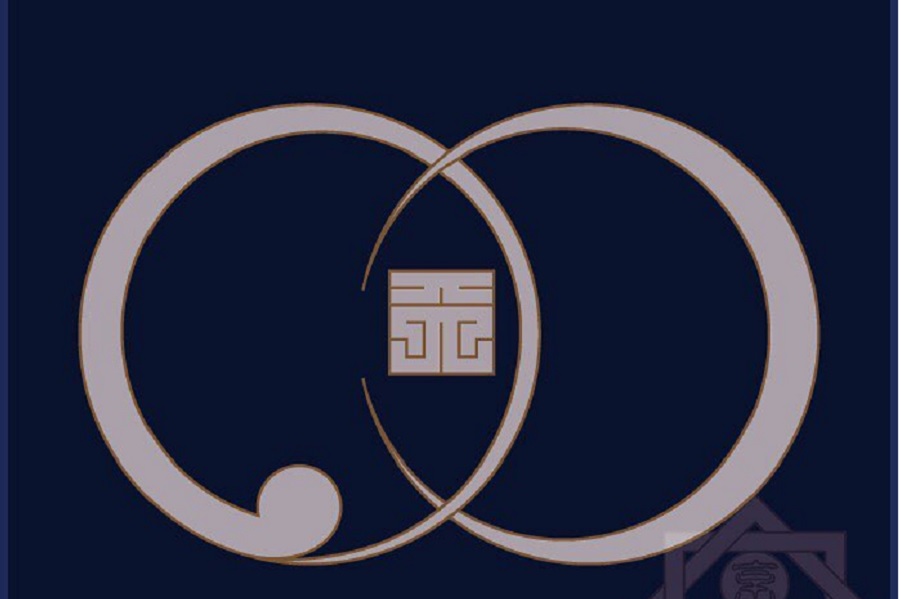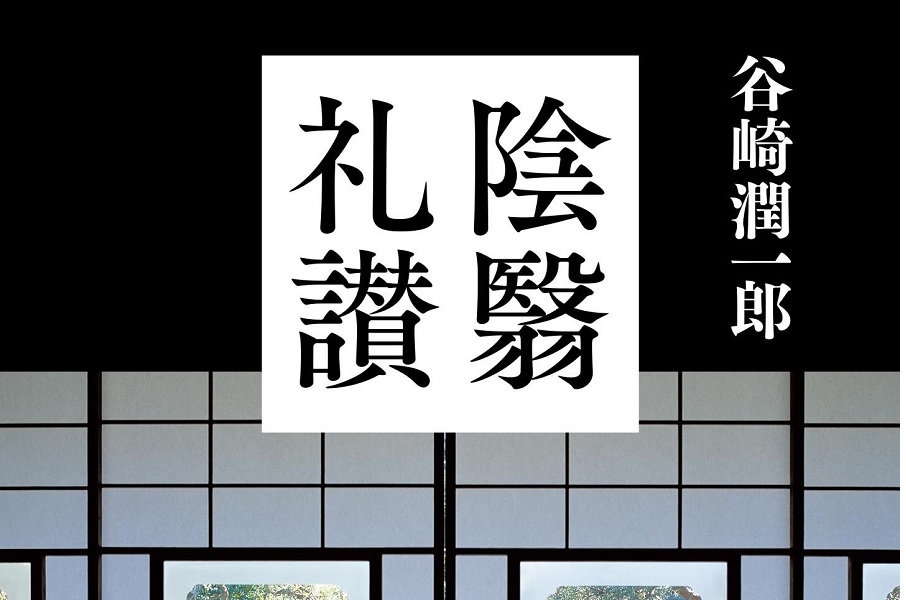「茶の間」 家族団らんの場

茶の間で家族団らん
こんにちは。
「茶の間」と「ちゃぶ台」、と聞いて今の子はわかるのかな?
不動産屋さんのお部屋の案内に「8畳の茶の間」とは書かれないですね。
いつのまにリビングやキッチンと言われるようになったのでしょうか。
小さい頃のドラマは必ず「茶の間」で「ちゃぶ台」を囲んで一家団欒。
ご飯の後は、急須で各自の湯飲みにお茶を入れて、四方山話、貫太郎一家ではその後、必ず親子けんか。
けんかはするけど、家族みんなが仲良し、一人ぼっちにはしないし、いじめなんかなかったようなきがします。
いい時代でしたね。
大切な時ですね。
今日のお話しは坂東眞理子さんのご本「和の暮らし・二 礼儀作法としきたり」より。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
茶の間
現代の住まいで家族が集まり、日常生活の中心になっているのが居間ですが、かつての日本の家では「囲炉裏」が居間の役割を持っていました。
囲炉裏という言葉は室町時代にできたといわれており、人の居る場所、あるいは火をたく場所を意味します。
江戸時代には多くの民家にとり入れられました。
囲炉裏は、農家の板の間や畳の間に作られた炉で、食べ物を煮炊きしたり、食事をしたり、冬には暖をとったりと家族みんなが集まる場所でした。
当時、囲炉裏の火は常に絶やさないようにする習慣がありました。
これには再び火をつけるのがめんどうだったからという理由だけでなく、家の中の除湿と建材を乾燥させるためという知恵がありました。
江戸時代が終わると、囲炉裏にかわって茶の間が中心になってきます。
茶の間の名前は、もともとは茶会に使われていた「茶の湯の間」「茶会の間」が略されたものです。
かつては貴族のものだった茶を飲む習慣が一般の人の間にも広まり、明治時代には、台所とは別に茶の間が作られるようになりました。
それ以降、昭和三十年代ごろまでの都市部に住む庶民の生活は、茶の間を中心に営まれていました。
囲炉裏
囲炉裏は土間から最も奥の席を「横座」といい、一家の主人の座として他人が座ることは許されませんでした。
主人の左右は男女により席が分けられ、一家の主婦は台所に近い「かか座」と呼ばれる女座で食事を切り盛りしました。
囲炉裏に鍋をつるし、火力を調整する自在鉤(じざいかぎ)は火の神への供え物を意味し、鯛や鯉などの魚がかたどられています。
自在鉤をつかって鍋を上下させるのですが、なぜ?上下するのかわかってない私です・・・。

万能なちゃぶ台
茶の間には茶たんすとちゃぶ台が置かれていました。
茶だんすは、引き出しつきやガラス戸を入れたものもあり、お茶道具やお菓子、財布や印鑑まで生活のこまごまとした道具をしまう場所として重宝されていました。
ちゃぶ台は、四脚で折りたためる小さなテーブルで、主に家族の食卓として使われていました。
それまでは銘々の膳で食事をしていましたが、ちゃぶ台の登場で、一つの食卓でみんなで食事をするという習慣が生まれました。
ちゃぶ台は、家族の食事以外にも、子どもの勉強机、裁縫の作業台としても使われました。
そして夜になるとちゃぶ台を片づけて、布団を敷き、寝室となりました。
家族そろって小さなちゃぶ台を囲んで食事をし、冬になるとこたつを出して鍋を囲むなど距離感がせばまり、自然と会話も弾んだことでしょう。
このような茶の間中心の生活から、日本の家族団らんの意識が芽生えたのです。
ありがとうございます
便利になった時代と言われますが、どうでしょうか。
昔の日本の家は、小さなお家でも、襖、障子で区切られていたので、外すと一間に様変わり。
みんなで一緒に楽しくわいわい。
ちゃぶ台も夜になると脚をたたんで部屋の隅に立てると寝室に早変わり。
もちろん自分の部屋などないからみんなで一緒に寝ますよね。
今は、壁で部屋をしきり、テーブルと称する食卓が場所をでーんと。
何が良くて、何が悪いかはそれそれの判断にお任せしますが、大切なのは自分一人で生きているのではなく、みんなと生きているということ。
誰かが悩んだり困ったり、悲しいことがあると、みんなが一緒になって真剣に考えて暮していきます。
とっても大切な素晴らしいことだと思います。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
18日から始まった浄住寺の特別拝観。
毎日1000人を越えるお客さま、ありがとうございます。
もちろん方丈は襖をすべてとって大きな部屋となってみなさまをお迎えしてます。
便利ですよね!
参考
囲炉裏で和の心を感じよう
「こたつ」の季節がやってきた
和食と何?その文化について考えてみよう
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld