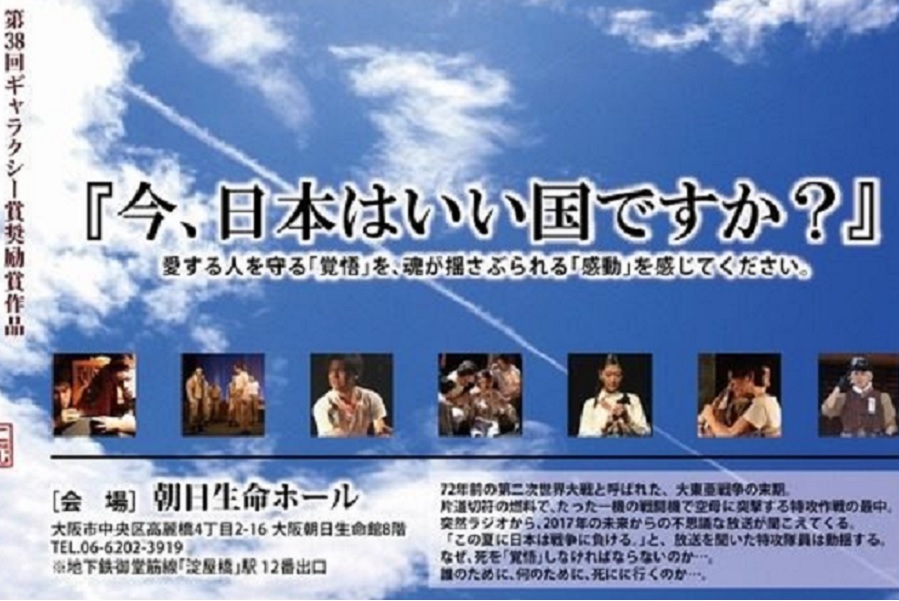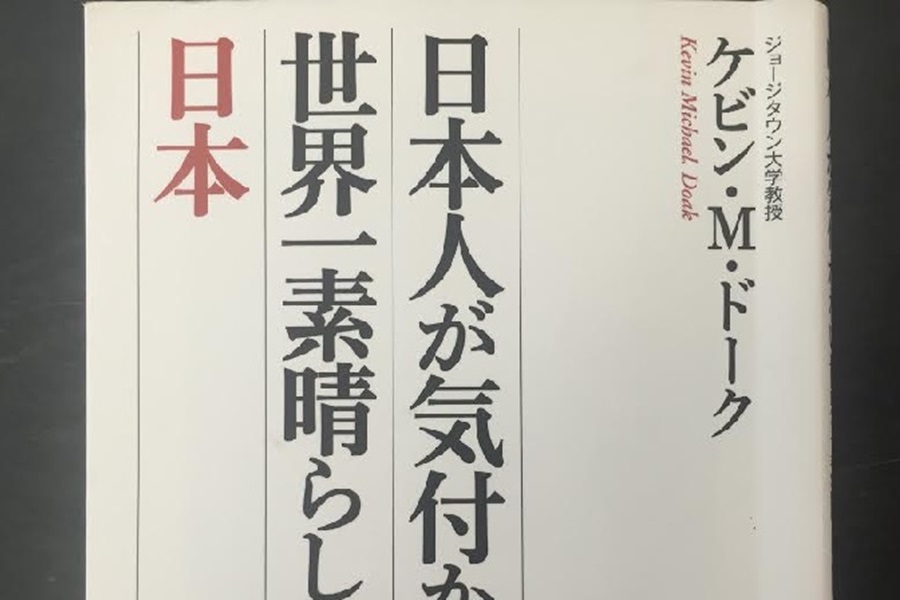三方と神饌 ご存知ですか?

「三方」をご存知ですか
こんにちは。
先日、素敵なかたより「三方」をいただきました。
ありがとうございます。
本当にうれしいです!
早速、神棚に奉らせていただきました。
普段、みなさんは「三方」いただくことなどないでっすよね。
というより、「三方」をご存知ですか。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
「三方」って何ですか?
三方(さんぼう、さんぽう)とは、もともと食膳だったそうです。
それが今では、神道の神事において使われる、神饌を載せるための台となっており、古代には、高貴な人物に物を献上する際にも使用されたそうです。
通常は檜などの素木(しらき)による木製で、折敷(おしき)と呼ばれる盆の下に直方体状の台(胴)がついた形をしています。
台の三方向に穴があいていることから、「三方」と呼ばれます。
「三方」の正面は?
台の穴の意匠に決まりはないそうですが、宝珠の形がよく用いられています。
折敷には縁の板を留めるための綴り目がありますが、これは穴のない側の反対側になるように作られています。
神前に供える際は、穴のない側(綴り目の反対側)が神前に向くようにします。
神饌が載った三方を持つときは、親指を左右の縁に、その他の指を折敷と台に当て、目の高さに持ちます。
「四方」もあるのご存知ですか?
室町末期の三条西実澄の「三光院内府記」に「大臣以上は「四方」、大納言以下は「三方」になり・・・四方はいの目四方あり」とあります。
大官用が四方で、三方はそれに次ぐものの所用であったそうです。

それでは「三方」に載せる「神饌」とは?
神饌(しんせん)とは、日本の神社や神棚に供える供え物のことです。
神事の際にはその土地の人々が特別な恩恵を享受した食物を神饌として捧げ、神迎えを行ってきました。
捧げられる神饌は主食の米に加え、酒、海の幸、山の幸、その季節に採れる旬の食物、地域の名産、祭神と所縁のあるものなどが選ばれます。
儀式終了後に捧げたものを共に食することにより、神との一体感を持ち、加護と恩恵を得ようする「直会(なおらい)」が行われます。
「神人共食」(しんじんきょうしょく)が、日本の祭りの特徴であるとも言われています。
ありがとうございます
お正月にお餅をのせるのに使いますよね。
春のお雛さまにも、使われていますよ。
お雛さまのお飾りをようく見てください。
ほら。
ん?今は、家庭にはないかな?
いかがですか、自分の家紋を入れた三方を家庭に一つ!
それぞれの節句で、神饌ならぬお供え物を載せて神さまに「ありがとうございます」って。
今日も最後までお読みいたでだきまして、ありがとございます。
神ごと、まだまだ知らないことがたくさんあります!
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld