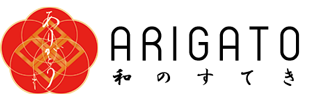「茶花」とは何か 古人の言葉で「花は足で活けよ」

花に見習わなければね
こんにちは。
今日も茶花のお話し。
野に咲く花、名前も知らないけれどかがんで見てみると楽しそう。
一輪で咲いているのか、仲間と一緒に遊んでいるのか。
風にそよぎながらふわふわって。
弱そうなのにとっても強いのでしょうね。
芯がしっかりしてるから。
見習わなければ。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
古人の言葉で「花は足で活けよ」とあります。
足で活けるとは、自分が花を探しに出向き、花が咲く様を見て、採って花入れに入れることと思います。
厳しい自然環境で育った花は、栽培した花よりも勢いがあり、花の色も綺麗です。
花と花入れの調和を考えて、剪り採る花はできるだけ最小限に、花と花入とが効果的に生きることを考えます。
そして剪り採った花は、一日でも長く生かすことが、花への慈しみであり、自然の恵みへの感謝でしょう。
四季折々の花を入れ、花より生気を貰い、人生心豊かに日々遅れることは幸せなことと、感謝の念を禁じません。
(本:「野の花でおもてなし 無法庵 花往来」著:田中昭光さん より)
「茶花」のカテゴリー
「茶花」という用語の使い方は、茶花関係の文献を見る限り三つのパターンがある。
すなわち①茶室で鑑賞用に用いる植物自体を呼ぶ場合、②花入れに入った植物の状体を呼ぶ場合、③①②を区別することなく総称的に呼ぶ場合である。
「茶花」関連の文献では③の使い方が多い。
そこで、最も一般的である③の場合の「茶花」について、平成二十二年(2010)に出版の「新版 茶道大辞典」や同二十六年に出版された「新版 茶花大辞典」などを元にして、以下に概説したいと思う。
まず第一に、「茶花」には常にフレッシュな植物が用いられる。
したがって、切り採ったばかりの植物体を最上として使用する。
ただし稀に枯死した植物器官も用いる場合がある。
たとえばカンボタンの枯れ枝やハスの枯れ葉、乾燥した果実などである。
第二に、開花の季節が明確な植物を使用する。
されにこれらは開花期を迎えたばかりの状態のものが特に良いとされ、開花の季節の先駆けを鑑賞する。
花期の定まらない植物は敬遠される。
狂い咲きの花は使用しないが、十月に限っては、返り咲きの花を名残りの「茶花」として使用が許される。
このような「茶花」は、炉(十一月~四月)と風炉(五月~十月)の二季に大別され、炉ではツバキが、風炉ではムクゲが代表的な植物として位置づけられていることは周知の通りである。
第三に、植物によっては白花が最上位として使用される(後述)。
たとえばツバキの「白玉椿」、ムクゲの白花などがこれに当たる。
しかし、ボタン、フヨウなどの類は紫、ピンクなどが使用され、キキョウやフジ、アサガオなどは元来の色がよいとされる。
第四に、一般的な植物を用い、珍しい植物は避けた方がよいとされる。
また野生の植物を「茶花」に用いることは馳走とされる(ただし、昨今では野生植物の採取は危惧種などに関連した問題が生じる場合があるため、最大の注意が必要である)。
第五に、「禁花」と称して使用しない植物が存する(後述)。
香りの強い花、悪臭のする花、毒々しい色彩の花、棘のある植物、食用の花、季節の無い花などは、「禁花」の理由となる。
しかし、厳密な取り扱いではない。
第六に、投入れの形をとる。
生花のように植物に手を加えることを良しとしない。

日本人が持つ白色への美的意識
「茶花」においての「白花」や「禁花」に対する作法の起源は、大陸から導入された経典中にその記載文が見出される。
岡田幸三氏は、「風興の花」(茶道資料館図録「花入―わび茶の造形」所収)において「立花」の源流は「供花(くげ)」であることは疑う余地はないことを述べ、その作法の源流を密教の経典に求めている。
この経典が、大陸から取り入れた「蘇悉地羯羅経(そじつじきゃらきょう)」であり、真言密教の真言行を行うに当たっての成本である。
「蘇悉地羯羅経」の「供養花品 第七」には、七十九種の花を例に挙げ、仏への献花の作法について述べている。
そこで、本書から、まず「茶花」の「白花」に関わる箇所を抽出し紹介すると、
俱に当に等しく水陸に所生の諸種の色の花を用うべし。名色(みょうじき)の差別(しゅべつ)は、各、本部に依り、善く之れを分別せよ。以て花を真言して、当に之れを奉献(ぶごん)すべし。是の願を発して言く、此の花は清浄なり。生ぜし処も、復、浄なり。我今、奉献す。願わくは納受を垂れて、当に成就を賜うべし。
経花の真言に曰く、
阿歌囉(から) 阿歌囉 薩(さらば)嚩地(びち) 耶駄囉(やたら) 布爾低 莎羅 訶
この真言を用て花を真言して、三部に供養せよ。若し観音に献ずるには、応に水中に所生の白花を用て、之れを供養すべし。若し金剛に献ずるには、応に種類の香花を以て、之れを供養すべし。若し地居天に献ずるには、時に随いて取る所の種類の諸花もて、之れを供養せよ。
(「新国訳大蔵経」十二による)
とある。
ここでは、供花にはみずみずしい、さらに白花の香しいものなどを用いよとある。
したがって、この白花を良しとする作法は、先の岡田幸三氏がいう「供花」から「立花」へと、さらには「茶花」へと遷移した過程で、供に受け継がれてきたものであろうと推定される。
であるが、「蘇悉地羯羅経」で論じられた「白花」の位置づけの受容背景には、飛鳥時代、すでに白花に対して高貴性を認めた意識が存在していたことは明らかである。
たとえば、「日本書紀」には吉野の山中で発見された白花のヤブツバキ(シロヤブツバキ)を天武天皇に献じたとする記録が残されている。
このように、現在の「茶花」における「白花」の位置づけは、密教の供花の作法と、さらには悠久の日本人が持つ白色への美的意識が渾然一体となって成立したものと言えよう。

茶花の「禁花」は桃山時代に定着
続いて「蘇悉地羯羅経」には、
諸花の中に、唯、臭き花、棘樹に生ぜる花、苦辛の味ある花の、供養するに堪えざるものを除け。前に広く花を列ねるに、名無き者をば、亦、用うべからず。
とあって、この一文には現在の「茶花」における「禁花」と一致する箇所が多い、悪臭がする花、棘のある植物、毒々しい花、名前の無い植物などは、「供花」として用いられない、とある。
「禁花」の概念の起源は、「蘇悉地羯羅経」に存在したのである。
なお「茶花」における「禁花」植物は、桃山時代、利休の狂歌によって、その代表的な植物名が定着することになった。
天正九年(1581)奥書のある利休の「天正九年紀銘伝書」には、
似きらい申はな八色有
花入ニいれさる花ハちんちやうけ
ミやましきひニけいとのはな
おミなへしさくろかうほね
きんせい花せんれい花をきらひこそすれ
とあり、これらは後に「南方録」にも引用されている。
利休の「禁花」は、弟子の古田織部に伝えられ、多少の植物の入れ替わりがあるものの、さらに上田宗箇へと伝えられている。
宗箇の口述になる「宗箇様御聞書」には、
活花ニ不用分、ヲミナメシ、カワホネ、ケイトウ、ミヤマシキヒ、チヤノハナ、キンキンクワ、センノウゲ、サクロ、此分織部殿不被用候由
とある、
オミナエシ、コウホネ、ミヤマシキミなどは利休と変わるものではないが、ここにチャが入った点が注目される。
おそらく抹茶との関りで「茶花」からネグレクトされたのであろう。
なお花道においても、室町時代に成立した最古の花伝書「仙伝抄」をはじめとして、多数の花伝書に「禁花の事」などとして先述の植物が論じられてきた。
ありがとうございます
千利休がいいます「花は野にあるように」と。
花の咲いている自然の様をよく観てみること。
「習うより慣れよ」
「茶花」は、流儀の花と異なり、はっきりした決まりはなく自由な心のもとに、それぞれ好きなように活けていいのでは。
花も茶花で、どれが茶花でないとはいわないのでは。
あまりにも毒々しい「禁花」はさけて自然観を楽しむのが一番。
季節感を尊ぶのと同時に、簡素美に。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
その時々に出会った花を、似合いの花器に活けて楽しみませんか。

「茶花の文化史」著:横内茂さん

「野の花でおもてなし」著:田中明光さん
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld