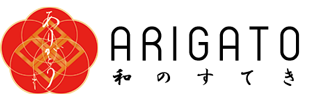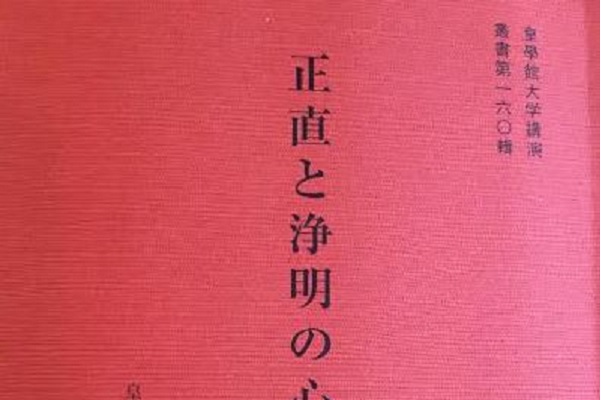「神社と神道の歴史」第6回 著:白山芳太郎

「神社と神道の歴史」第6回 著:白山芳太郎
神道の宗教現象の1つに、神意をうかがうために行う「占(うらな)い」がある。
「うらなふ」は「うらに合ふ」という語が短縮されたもの。
「うら」は「裏(うら)」であり、表に現われない神の心の「裏」という意である。
そのような神意に合致するというのが「うらに合ふ」という語である。
後に「うら」に合わない場合も含めて、その行為自体を「うらなう」というようになる。
「占い」には「鹿卜(ろくぼく)」「石占(いしうら)」「琴占(ことうら)」などの種類がある。
「鹿卜(ろくぼく)」は、記紀によると「ふとまに」という語が用いられている。
『古事記』には「布斗麻邇(ふとまに)」と記されている(『日本書紀』では「太占(ふとまに)」)。
「布斗(ふと)」は『日本書紀』が「太」という字を書いているように「りっぱな」という意味。
「麻邇(まに)」は『日本書紀』が「占」という字を書いているように「うらなう」という意味。
鹿の肩甲骨を火であぶり、それによって生じる「ひび割れ」によって吉凶をうらなう。
今日では貫前(ぬきさき)神社(群馬県)や武蔵御嶽(むさしみたけ)神社(東京都)で行われている。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World

(貫前神社の鹿卜<同社では鹿占(しかうら)という> 国の重要無形民俗文化財・文化庁文化財データベースより)
占い
「石占(いしうら)」は、石を持ち上げて重く感じるか、軽く感じるかで占う。
たとえば、京都の伏見稲荷大社に「おもかる石」というのがある。
灯籠の空輪(くうりん)(最上部)を持ち上げ、自分の予想よりも軽いと願いが叶(かな)い、重いと叶わないというものである。

(伏見稲荷大社の「おもかる石」安藤孝信氏提供)
比較的シンプルな「おもかる石」が京都市の今宮神社に伝えられている。
各神社に伝わる「おもかる石」の中では、どちらかというと多いタイプである。

(京都市今宮神社の「おもかる石」葉室頼廣氏撮影)
「琴占(ことうら)」は、神宮神嘗祭(かんなめさい)などの時に、祭典に先立って行われる「御卜(みうら)」のなかに伝えられている。
古くは琴の弦を奏(かな)で、音が澄んでいるかどうかで占った。
今は琴板(こといた)を笏(しゃく)でたたいて占っている。
古典では『古事記』の仲哀天皇の段に次のように記されている。
「太后(おほきさき)息長帯日売命(おきながたらしひめのみこと)、当時(そのかみ)神帰(かみよ)せしたまひき。かれ、天皇、筑紫の訶志比(かしひ)の宮にましまして熊曽(くまそ)の国を撃たむとしたまふ時、天皇、御琴(みこと)を控(ひ)かして、建内宿祢大臣、沙庭(さには)に居て、神の命(みこと)を請ひまつりき」
この時、仲哀天皇は「琴占(ことうら)」を行っておられたとみられる。
また「宇気比(うけひ)」をおこなった。
「宇気比」は『古事記』での記載であり『日本書紀』では「誓約(うけひ)」とある。
「誓約」という漢訳はいかがであろう。
例えば「誓約書」というと、会社に入社する際、新入社員が会社に対し「誓約」する時の書類がそれであるが、これは「うけひ」ではない。
『日本書紀』が用いた訳語は不正確だと思われる。
古代中国に「うけひ」にあたる行為が存在していなかったため「誓約」という漢語を代用した。
このような場合『古事記』は安易に漢訳してしまわず、日本語の音を1字1音で残した。
同書は、同様の配慮をいろんなところで行っている。
例えば『古事記』に「比良(ひら)」と言う語がある。
「黄泉国(よみのくに)」への坂を「比良坂(ひらさか)」と言う。
『日本書紀』は「平坂(ひらさか)」と漢訳した。
この言葉は「平坦なスロープ」と言う意味である。
曽毘良(そびら)と比良(ひら)
ところで『古事記』におけるスサノオノミコトの高天原訪問の折、姉(アマテラス大神)は、武装して弟の来訪に備えたと言う個所の記載に「曽毘良(そびら)」と「比良(ひら)」という語が登場する。
「曽毘良」の「そ」は「そっぽを向く」(あるいは「そっくりかえる」)の「そ」であり、今の「背(せ)」にあたる。
「背(そ)」の「ひら」が「そびら」であり「そびら」に1000本入りの矢筒を装着した。
単に「ひら」という場合は「脇腹」のことであり「ひら」に500本入りの矢筒を装着した。
背中や脇腹は「絶壁」である。
「比良」は「比良山脈」という場合に、今も使っている。
比良山脈(滋賀県)は、東の面が「比良断層」西の面が「花折(はなおれ)断層」である。
そのような「絶壁」が「比良」である。

(比良山脈 Wikipediaより)
「黄泉国」は「崖の下」にある地下の国という意味である。
上から覗(のぞ)くと、足がすくむ。
それが「比良」である。
華北・華中・華南では「坂」は「なだらかなスロープ」を意味する。
後にチベットやクンルン山脈が中国領となり、そのようなところには「急な坂」がある。
しかし、こういったところは、かなり後まで国外と見られていて、一般の人が目にする「坂」は「なだらかなスロープ」である。「王墓への坂」と言うことであれば、巨大な墳墓にちがいないから、その参道は「なだらかなスロープ」であろうとみて「平坂」と訳した。
こうして生まれた誤訳である。
「平坦な坂」に対しては別の語があって「ならさか」(奈良市の北から木津に向かう坂)という。
「坂」に、その状況をあらわす「なら」という語を添える。
なだらかにすることを「なら(奈良)す」(万葉集に、なだらかにすることを「奈良」すと言った例が2例(「大き海の 水底深く 思いつつ 裳(も)引き奈良しし 菅原の里」と「青柳の 張らろ川門(かはと)に 汝(な)を待つと 清水は汲まず 立処奈良すも」)ある。
日本語の「坂」は「さかい(境)」と同源の語でもある。
比良山脈の「比良」は近江国と山城国の「境」である。
「黄泉津(よもつ)比良坂」は「生の国」と「死の国」の境であった。
記紀によると「黄泉(よみ)の国」は地下にある埋葬施設であり、かつ、夫が現地へ行っているところから見て参拝施設でもあった。
崖の上から覗くと「黄泉の国」に降りていく「急な坂」があったのである。
日本の古墳
ところで日本の古墳は、古墳時代前期~中期にかけて「竪穴式石室」であり、古墳時代中期~後期にかけて「横穴式石室」となる。
記紀によると、崖の上から覗き込んだ様子は「竪穴式」のようであり、地下に降りて水平に移動する状態は「横穴式」のようである。
そのような古墳が九州南部から出土している。
「地下式横穴墓(ちかしきよこあなぼ)」である。
「竪穴式石室」が「横穴式石室」に移行していく時期のものである。
「竪穴式石室」では、棺(ひつぎ)を納めたあと、石室の上を岩で塞(ふさ)いでいる。
その時代が終わると「地下式横穴墓」であって、竪穴(約3m)が掘られ、竪穴の底から横に進む「横穴」があって「横穴」への入り口は後の「横穴式石室」のように岩で塞がれている。
昇り降りに際しては「竪穴」の壁面に「急な坂」がある(鹿児島県鹿屋市の岡崎古墳群の18号墳など)。
この「急な坂」が「比良坂」に当たるのではないか。
記紀によると「黄泉国(よみのくに)」で、夫はウジ虫だらけの妻に会った。
そして逃げ出した。
後ろから「ヤクサ(八種)のイカツチ」が追いかけてきた。
ウジ虫であって「横穴」を這(は)って追いかけてくる。
「イカ」は「厳(いか)めしい」のイカであり「ツ」は連体助詞(「天(あま)つ風」「目(ま)つ毛」「天つ神」「国つ神」などの「ツ」)である。
「チ」は「いかつち」「かぐつち」などにみられる「チ」である。
「やまつみ」「わたつみ」の「ミ」などと同種のものであって、意味は「精霊」である。
多くの種類(ヤクサは実数の8ではなく、当時数えきれる最大数が8だったため、多くの場合「8」は数えきれないという意味)の「厳(いか)めしい精霊」が追いかけてきた。
「雷(かみなり)」も古語では「雷(いかつち)」といい「厳めしい精霊」の1つであるが、雷(かみなり)は「イカツチ」の中の最も「厳めしい精霊」であったため、後になると「雷(かみなり)」に特化されて「イカツチ」と用いられることとなる。
ここでは「雷(かみなり)」だけに特化される以前の「イカツチ」であり、数えきれない種類のウジ虫が追いかけてきた。
そういったウジ虫を遮断するため、横穴の入り口を岩で塞(ふさ)いだ。
宇気比
『古事記』における「宇気比」と同様の表現法がみられる「比良」へと話を転じたが、話を「宇気比」にもどしたい。
つまり、男女や左右の比率が5:5となる場面で、あらかじめ宣言して置くことが「宇気比」であって、この言葉は日本特有のものであった。
これにあたる概念が中国にないため「宇気比」とせざるを得なかったのである。
宗像3女神誕生に先立って行われた「宇気比」の場合、現在の『古事記』には記載が見られないが「宇気比」とある以上、事前に宣言していたことと思われる。
「女の子が生まれたなら、心が清らかな証拠。男の子が生まれたなら、心が邪(よこしま)な証拠」というものである。
そのように、あらかじめ「宇気比」を行った。
そして生まれた子が女の子であったため「心が清らか」だったとスサノオノミコトは言うのである。
『日本書紀』編者のかなりを占めていた渡来人たちの考えでは、想定される読者が中国人である以上、ここでの女神誕生は疑問だとしたのであって、同書は男神が生まれたから「占いに勝った」という別の話題に転じている。
『日本書紀』の別のところでも「男神が先に声をかける」と良い結果「女神が先に声をかける」と悪い結果とされていて、良い結果はいかなる場合にも男(つまり陰陽の陽)という固定的な判断に立つのである。
そのようものは「宇気比」ではない。
『古事記』に古い姿が残っていると見る。
『日本書紀』は、渡来系の編者たちの判断に押し切られてしまったのである。
同書編纂開始の頃、編者の1人だった太安万侶は、このような古伝の改訂に対して反発して編者を辞任し、独力での『古事記』執筆を志したのである。
中国の「誓約」に近いのは、むしろ「盟神探湯(くかたち)」である。
これとて『隋書』倭国伝は「倭国独自」のものだとしている。
『論語』(李氏第16)のなかに「善を見ては及ばざるがごとくし、不善を見ては湯を探るがごとくす」とあり「探湯」という語自体はみられる。
ここでの記載は、不善を行う誘惑が起きた場合は「熱湯の中から物を取り出すようにする」という意であり「不善」を行うことを躊躇(ちゅうちょ)するという意味となる。
この行為を「宗教裁判」として実施するのは『隋書』が言うように「倭国独自」とみられる。
古典に登場するいくつかの「盟神探湯(くかたち)」(応神紀・允恭紀・継体紀などにみられる)の場面を総合すると、当該人物の正邪が明らかでない場合この裁判が行われ、当事者に「実(まこと)を得むものは全(まった)からむ。偽(いつは)らば必ず害(やぶ)れなむ」と身の潔白を神に誓わせ、その上で熱湯の中の小石をつかませ、やけどが起きるかどうかにより結審される。
神罰への恐怖を誰もがいだいていた時代の「宗教裁判」であって、偽証者は神から通常以上の激痛を与えられると信じていたため挙動不審となり、正直者は神に守ってもらえると信じているため正々堂々としていて、裁判のゆくえは誰の目にも明らかであった。
中世になると、同様の方法を「湯起請(ゆぎしょう)」と称して行った。
甘樫坐(あまかしいます)神社
『古事記』下つ巻に「味白檮 (あまかし) の言八十禍津日 (ことやそまがつひ) の前 (さき) に探湯瓶(くがへ)をすゑ」と記されている。
「探湯瓶(くがへ)」は盟神探湯を行うための湯を沸かす土器である。
味白檮 (あまかし)、即ち 「甘樫坐(あまかしいます)神社」のあたりは、かつて盟神探湯が行われた場所であったと思われる。
各地に伝わる「湯立(ゆたて)神楽」は、この「盟神探湯」の所作を模した神事で、鉄の釜(多くは鼎(かなえ))で湯をわかし、その湯のしぶきを榊の葉(または笹の葉)で参列者に振りかけ「無病息災」を祈る。
この神楽は、各地の神社(甘樫坐(あまかしいます)神社、広田神社、春日大社、住吉大社、石切劔箭神社など)や集落(多くは旧暦11月に行われることから霜月神楽(しもつきかぐら)と称し、伊勢の御師の館で江戸期に行われていた湯立神楽を再現したとされる)で行われている。

(住吉大社若宮八幡宮例祭 同社公式ホームページより)
また、祭りに先立って「禊(みそぎ)」や「祓(はらえ)」によってけがれを祓うということが行われた。
からだに「穢(けが)れ」が付着していると考える者が、川や海で身を清める行為を「禊(みそぎ)」という。
そういった「禊(みそぎ)」を略式で行うのが「手水(てみず)」である。
両手を洗い、口をすすぐことによって、からだが清められるとする「みそぎ」の一種である。
仏教寺院にも「手水舎(ちょうずや)」と称し、神社の「手水舎(てみずしゃ)」のような施設がある。
世界の仏教寺院にはない。
仏教寺院では日本の場合のみ存在する。
日本人が宗教施設に踏み入る時、なさねばならないと信じておこなう行為が「手水(てみず)」である。
日本の仏教寺院で行う「手水(ちょうず)」は神道の影響である。
厳重な「清め」を必要と感じるとき(例えば、昇殿し神職による祝詞(のりと)奏上を依頼するとき)には「祓(はらえ)」を受ける。
「禊(みそぎ)」もしくは「手水」の上に、さらに厳重に行うのが「祓(はらえ)」である。

(祓を受ける前の着座 渡邉規矩郎氏撮影)

(祓 Wikipediaより)
贖罪(しょくざい)」する行為を「祓」
また、記紀によるとスサノオノミコトが罪を犯したのち神に財を献じて「贖罪(しょくざい)」する行為を「祓」と記されている。通常の「祓」は、知らず知らずのうちに身に付着した穢れを祓うものであるが、犯罪も「祓」で祓うことができると考えられたのである。
その背後に、神に財を献じることにより犯罪を「清められる」とされた日本の原始期の「罪」の観念があった。
後の律令時代になると、中国風に贖罪(しょくざい)が行われた。
「律」という刑法を採用したことにより、鞭(むち)でたたいたり(笞(ち))、棒でたたいたり(杖(じょう))する刑となった。
スサノオの場合は、財を神に献じるという形での「贖罪」が行われたのである。
一見、軽く感じられるが、記紀ではスサノオの「ツメ」を抜き「ヒゲ」を抜いたとされている。
現在でも爪を長く伸ばして飾る民族があり、また髭(ひげ)はイスラム圏の男性の口元を飾る重要な「財」であることから見て、それらは原始時代の「財」の一部であったと思われる。
そういった身を飾る「財」をも含む「全ての財」を奪って「贖罪」させたのである。
スサノオノミコトの場合、このような「財産刑」で終わらず、重ねて「追放刑」が執行されている。
「財」を神に献じて行う「贖罪」は律令時代になると行われなくなるが、律令体制が崩壊すると復活した。
例えば、鎌倉時代の『御成敗式目』(第15条)によると、寺社の修理を命じるという刑が記されている。
『御成敗式目』は、それに堪える財力を持たない者に対しては「追放刑」に替えてよいという規定が記されている。
武家社会での「追放刑」は全財産没収に匹敵するほどの重い刑だったのである。
「財」を神に献じる刑と「追放刑」は、律令時代と明治以後の西洋刑法の時代を除いた時代の日本の基本的な刑であった。
なお、律令時代においては、根本法(憲法と民法をあわせたもので「令(りょう)」という)の中に「神祇令(じんぎりょう)」(養老神祇令が『養老令』の注釈書である『令義解』のなかに伝えられている)を置いて、さまざまな「神事」に関する規定を定めた。
また「令」の施行細則としての「式」も重要であって、母法の中国法に規定のない、日本独自の神祇に関する規定が「式」(『延喜式』に伝えられている)のなかに残されている。
そのため、日本の「式」は単なる施行細則として定められたものばかりではなく、律令以前の古法を「式」のなかに残そうとする性格を兼ね備えていた。
そういった「令」や「式」のなかで「四季の祭祀」や「祓(はらえ)」に関する規定を定めた。
律令体制が崩壊した平安中期以降「四季の祭祀」や「祓」に関する規定は、各神社の実際の祭祀の中で行われつつ守られていくこととなる。
第7回に続く

白山芳太郎 プロフィール
昭和25年2月生まれ。
文学博士。皇学館大学助教授、教授、四天王寺大学講師、国学院大学講師、東北大学講師、東北大学大学院講師などを経て、現在、皇学館大学名誉教授。
おもな著書に『北畠親房の研究』『日本哲学思想辞典』『日本思想史辞典』『日本思想史概説』『日本人のこころ』『日本神さま事典』『仏教と出会った日本』『王権と神祇』などがある。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World