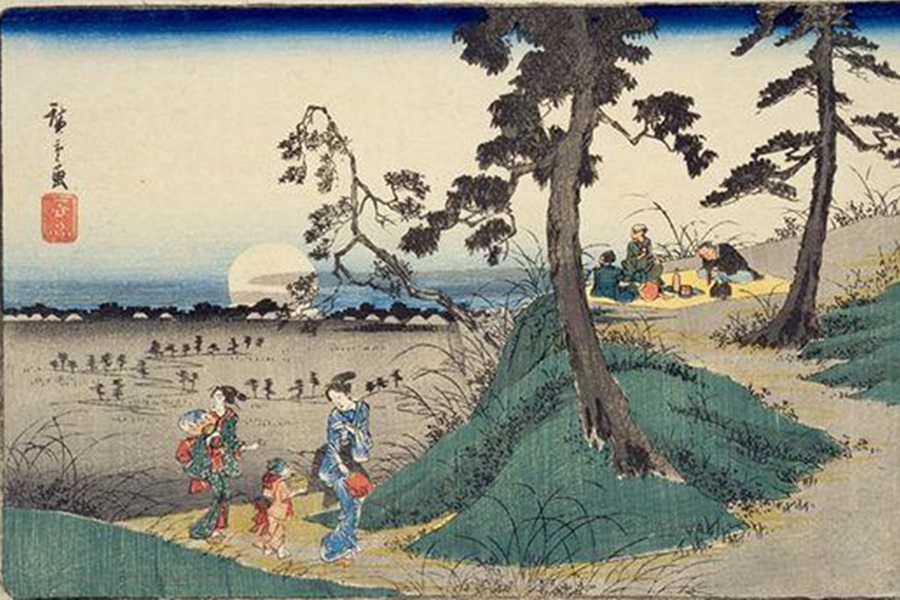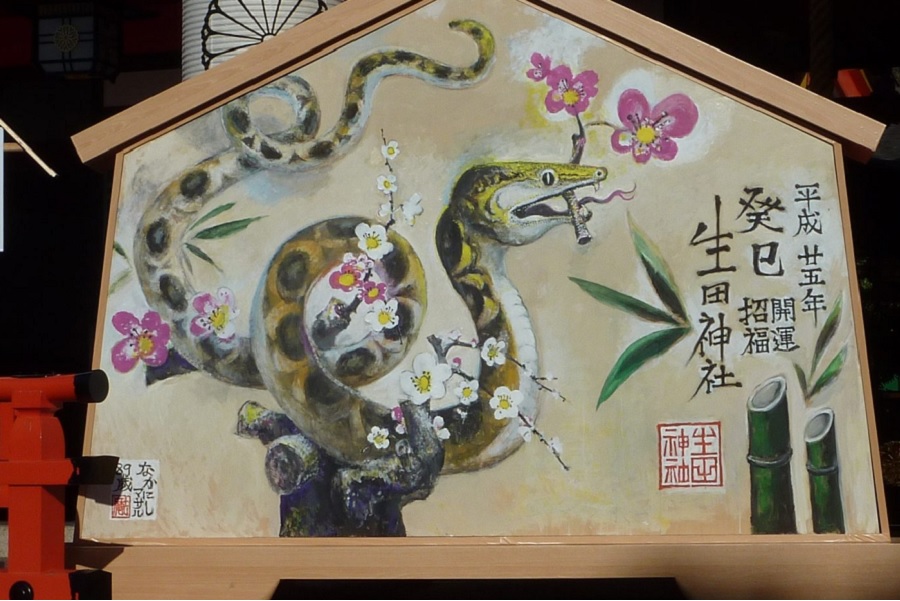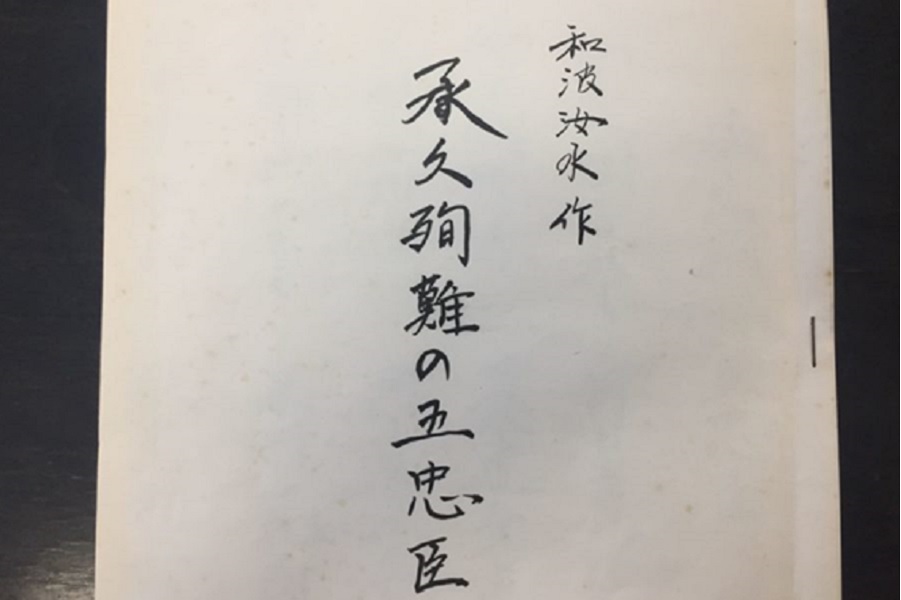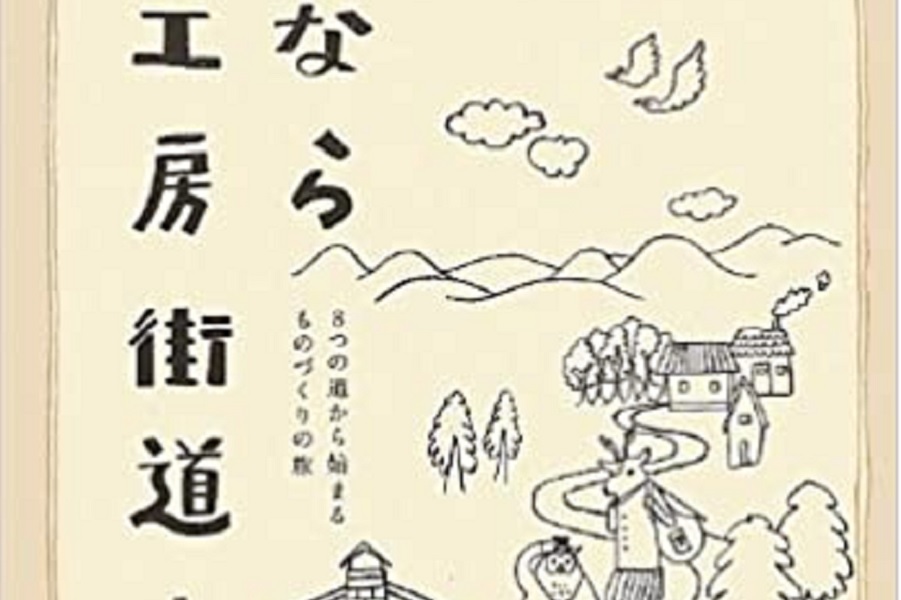株式会社Qの1周年

みなさまのおかげです
こんにちは。
昨日の8月19日は株式会社Qの一周年。
二條さまをはじめ多くの方々のお力添えをいただき、一周年記念講座を渋谷の近能八幡宮で行うことが出来ました。
皆さま、本当にありがとうございました。
そして講座では三田村先生に漆と日本文化のお話しをいただきました。
とてもとてもすてきなお話し。
重ね重ね、ありがとうございました。
皆さま、まだまだQは未熟でございますが、これからも何卒よろしくお願いいたします。
日本のすてきな事をいっぱい楽しみましょう。

ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
三田村先生、ありがとうございます

この日は三田村先生よりすてきなお話しをいただきました。
ありがたいことです。
一部ですがみなさまと。
「今ですね、世の中に紫外線によって壊されない塗料というのはないのですよね。
みんな壊れていく。
漆もやっぱり壊れていくのです。
壊れていくというのが実は日本のですね、美意識の中に、漆というのが本当にぴったりあってますね。
それは何かというと、日本の文化というものを、例えば世界の方に日本の精神性っていうのは、こういうのですよって言った時に「わび」「さび」っていう言葉を使うのですよね。
「わび」「さび」。
これは「わび」「さび」というのが分かれて考えているのですけれども、実は一体ですよね。
一体なのは何かというと、これは現象です。
これは心向きなのです。
心の趣なのです。
日本人だけが壊れた仏様の方が、今できた金ピカの仏様よりも頭(こうべ)が垂れるのです。
なぜか分かります?
なぜかというと、時間軸に私たちは頭を下げている。
この仏様は何人の方をお救いしたのだろうか。
何人の方の心を癒したのだろうかという、その長い歴史の流れに対して、私たちは自然と頭がふと下がります。
それは何かというと、壊れていった状態を「さび」、それが美しいと思う心を「わび」と言います。
「わびしい」「さびれた」とか、「寂しい」というのは現象なんです。
鉄が錆びていく、錆びたもの、寂れた街、現象でしょ。
そのことが、とっても、私たちの心の中にストンと入ってくる。
これ日本人だけなのですよ。


すてきなすてきな塗香入れ
Qでは香りを楽しんでいただきたいと思っています。
二條さまがいらっしゃるからできることですね。
これは、この日のために、三田村先生と二條さまが作られた塗香入れ。
すてきすぎます。
すてきすぎて拝見した時に言葉がありませんでした。

Qでは日本の香りを楽しんでいただけるように、いろいろな事をいっぱい行っていきます。
みなさまも一緒に香りを楽しみましょうね。
ありがとうございます

あらためてQを行っていくことで思うこと。
それは「ありがとう」の大切さかな。
単純に今、生きていることに、ありがとう。
空気があって、お日さまが登って、お月さまが輝いて。
お父さん、お母さんが私を産んで育ててくれて。
すてきな仲間たちがいてくれること。
いっぱいの「ありがとう」。
今日もたくさん、ありがとうございました。
これからもみなさんといっぱい楽しみましょうね。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld