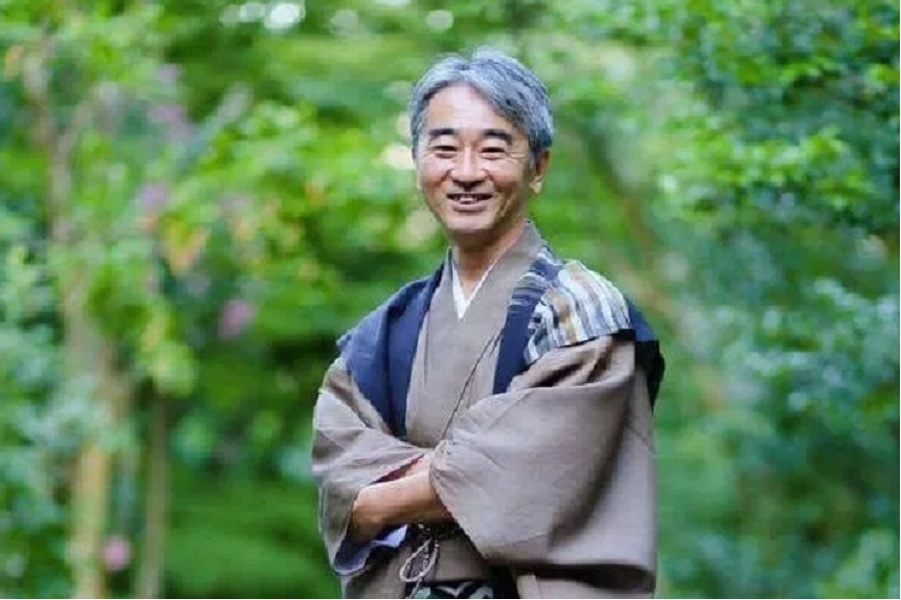「むすび」とは 「ムスコ」と「ムスメ」

神様とのむすびつき
こんにちは。
わたしたち日本人は、年が明けるとまず氏神様や崇敬する神社にお参りして、1年間家族を見守り続けてくださったお札やお守りに感謝を込めてお納めし、神様にご奉告します。
また新たな年のしあわせを祈念した上で新しい守札を授かります。
神様に新年のごあいさつをして初めて1年のすべての行事が始まります。
家庭では注連縄を張り替え、門松を立て、神棚や床の間に鏡餅をお供えしてご先祖様の神霊や家庭のなかをお守り下さる「歳神様」をお迎えします。
これは、自分自身や家庭が常にすがすがしくあろうという気持ちと、私たち日本人が古くから神様とのむすびつきをもっとも大切にしてきた例ですが、神様はいつも自分と一緒に、身近な生活のなかにいらっしゃる、というのが暮らしに息づいている日本人の意識なのです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
日本の神さま
日本の「結び」は「物を結ぶ」という以外に、人と人、心と心の関係をも「結び」として表され、特別な意味がふくまれています。
たとえば結婚式は、男女が結ばれ両家が結ばれる大切な儀式です。
神楽殿は、ご縁を表す「むすび」は、古くは「産霊(むすひ)」いって、すべての物を生み出すご神威のことを表していました。
天地・万物を生み出された神様に高皇御産霊神(タカミムスヒノカミ)・神皇産霊神(カミムスヒノカミ)、出産の際に見守って下さるのが産神(ウブガミ)という産霊の神様です。
また、産土(ウブスナ)の神様というのはわたしたちが生まれた土地の神様で、氏神様や鎮守様とも呼ばれますが、どこにいても自分の一生を見守って下さる神様です。
神と自然とすべてのものと結ばれている存在が、わたしたち人間です。
そして、この感覚を信仰の形で伝えているのが神社なのです。
神社の祭りでは、まず始めに神様にお供え物をして、終わると「直会(ナオライ)」といって、そのお供えをおさがりとして食します。
神と共にいただく、つまり神様と一体に「むすばれている」ことが大切なことなのです。
(文:平安神宮 平安の祈りより )
ムスビ
「ムス」は「蒸す」や「醸(かもす)」という漢字が当てられます。
醗酵の意にも使われます。
醗酵によって米や麦が酒というまったく異なるものに変成することを指しています。
また「苔むす」のように、岩肌から植物が突然のように生じてくることも指します。
「ヒ」は生命の根源の「火」であり、「霊」です。
つまり、「ムスビ」とは、生命・霊が殖え生まれることを意味するものです。
男女の「むすび」もまた生命・霊魂の繁殖であって、生まれた子供を「ムスコ・ムスメ」と呼ぶのです。
古来日本では、この生命的・霊的な生産を「ムスビ」と呼び、これをたいへん重要視してきました。
これを個人に当てはめれば、強く大きなものにしていくことが「ムスビ」なのかもしれません。
ありがとうございます
なぜ日本人はこのような一見わずらわしいことを行ってきたのでしょう。
それは、人は決してすべてをつかさどり支配できる存在ではない。
本来の姿は自然な清らかな存在だが、自分一人では常に過ちを繰返してしまい、反省しあらためる必要がある。
という自然の摂理をよく知っていたからに外なりません。
清らかなこころは自然の美さと全く同じものです。
海、山、川、生き物や植物の姿にすがすがしい美しさを感じることができる。
いつも自然のなかの一員であり、神々の力を崇めいただいて生活している。
これはわたしたち現代に生きるものにとっても、なんら変わりはないはずです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld