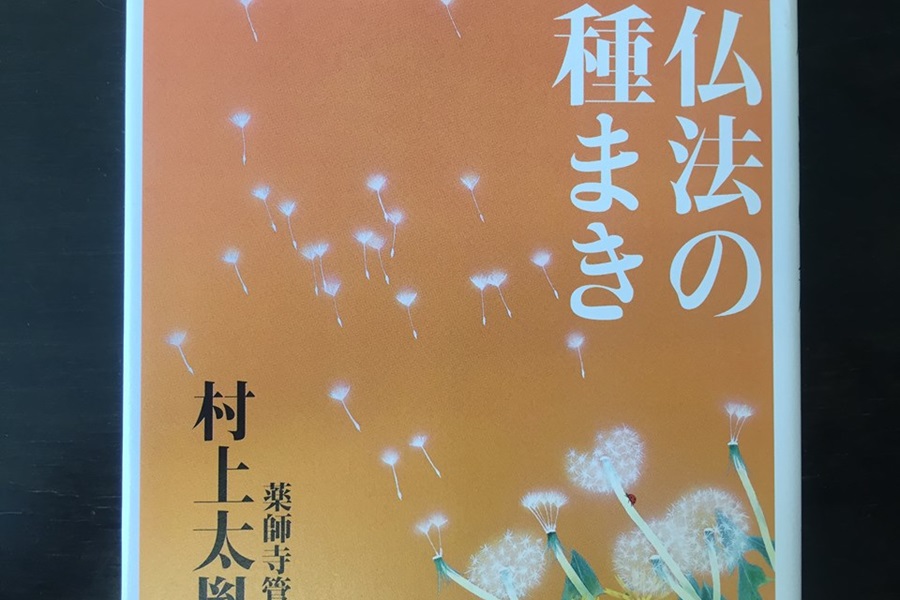どうして千木が前と後ろで違うの?

吉田神社と斎場所「大元宮」
こんにちは。
今日、「吉田神社」と斎場所「大元宮」へ正式参拝させていただきました。
大元宮の御祭神は天神地神八百萬神(あまつかみくにつかみやおよろずのかみ)。
吉田神道の教義により宇宙軸を現す大元宮は、始まりの神(虚無大元尊神)を中心に祀り、そこから生まれ来る八百万の神々を祀る事で、全国の神々を祀る社として、様々な御神徳をお授け下さいます。
大元宮でもっとも目を見張ったのが正面八角に六角の後方を付した本殿(重要文化財)はもちろんですが、それより私は千木。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
千木
千木は前方(南側)が内削(うちそぎ)、後方(北側)が外削(そとそぎ)になっていました。
棟に置かれた勝男木(かつおぎ)も独特でした。
南半分は丸材を3つ重ねたものが3組置かれていて、北半分は角材が2組置かれています。
そして棟の中央部には露盤宝珠が取り付けられているのです。
千木の先が水平に切られているものは伊勢神宮の内宮正殿と同じかたち、千木の先が垂直に切られているものは外宮正殿と同じかたちです。
写真では見にくいですが是非訪れてご覧いただけたらと思います。
詳しくはこちらのHPよりご覧ください。
なんで千木が前と後ろで違うのかご存知の方教えてください。

吉田神社
それでは、吉田神社のことを由緒書きより。
千載(せんざい)の古き都、京都の地は、東を望めば三十六峯、翠を競う山脈(やまなみ)が見えるが、その北部にあたって、白河の清い流れを挟んで、これに沿う一帯の丘陵があります。
これが吉田山であり、神楽岡の名もゆかしく古からの霊域でありました。
平安に都がさだまってから、太平の世がつづき、そのころから藤原氏は皇室の外戚としていよいよ栄えて国政に与るにいたりました。
平安遷都から、およそ六十五年、清和天皇の貞観元年(西暦859年)四月に中納言藤原山蔭卿がこの清浄な地を選んで藤原氏の氏神である大和の春日の神をここに勧請したのでした。
まさに、今より一千百余年にも及ぶ昔にあたります。
山蔭卿は藤原氏の一つの家筋、左大臣藤原魚名(うおな)の玄孫で、貞観のころは右近衛権少将となり、蔵人(くろうど)として天皇に近侍し、後には、参議に任じ、従三位に叙せられた。
思うに藤原氏は鎌足が大化改新や、天智天皇の近江朝廷の時に大功あり、それより子孫大いに栄え、代々、国務に深く参画したが、その氏神を崇めて、藤原氏が仕え住む都の地に近く、その神を祀ったのです。
都が奈良にあった時には都域の東に春日大社を建てて祭り、桓武天皇の山城の国、長岡に遷都せられた時は、その近くにある大原野神社に氏神を祭り、一族の参詣することを図ったと伝えられています。
平安京の時代はその東北の地、吉田に氏神が祭られるに至ったので、大和の春日の神をここに勧進せられたのです。
伝えるところ吉田の丘の地に斎きまつるとき、春日の神霊は神鹿に召して渡御せられたといいます。
ありがとうございます
雪予報のとっても寒い今日。
でも、吉田神社に着くまではよく降っていて、車を降りて正式参拝へそして社務所でご挨拶、この間はとってもいい天気。
そして、帰り支度の時から雪が降りはじめました。
今日は本当に神に祭られた一日でした。
ありがとうございました。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld