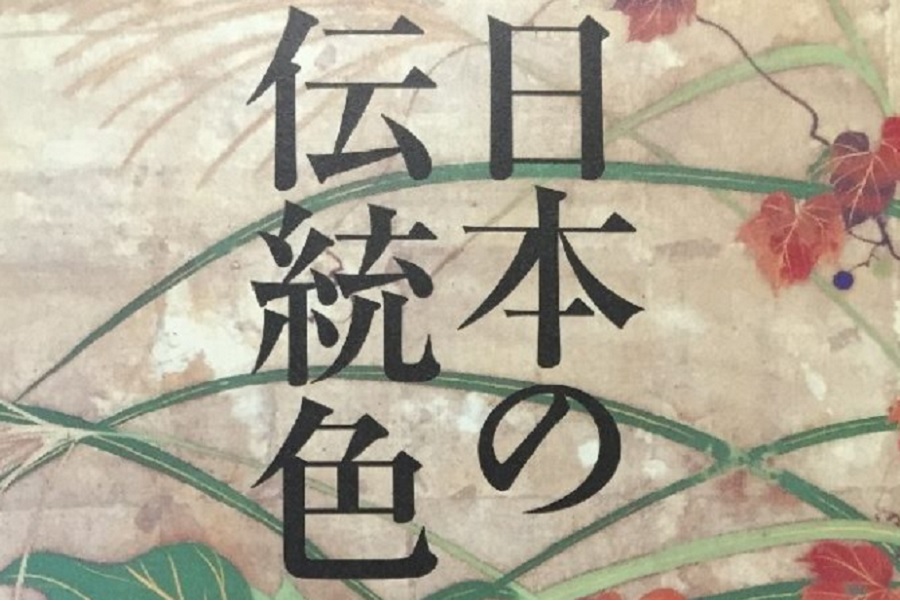叔父の教え 日本のきもの

絵本「にほんよいくに」三巻より
こんにちは。
きもの、着る機会が大変少なくなりました。
着たことがない人も多いのでしょうね。
こんなに素敵な世界からも注目される衣裳なのに。
もっともっと来ませんか、”きもの”
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
人間が着物を着る
お父さんとお母さんは、神社でけっこんしきをあげました。
おにわで、ふたりがならんでいるしゃしんは、妹のもっているひな人形いの、おだいりさまと、おひなさまに、そっくりだ。
「お母さん、きれいだね」と言ったら、「これは、日本に昔からある、とくべつなきものなのよ」と、うれしそうだった。
「こんなきものをきたら、別人みたいだね」
「こらこら」お母さんはわらっていた。
動物と人間の大きな違いのひとつは、人間が着物を着るすべを知ったことではないでしょうか。
外国のものを洋服、日本のものを和服といって区別していますが、どちらにしても服を着ることが人間の大きな特徴です。
外国の洋服は、多くが動物の毛などで作られています。
デザイナーが、その人の体に合うようにデザインし、立体裁断で作り上げ、ネックレスやイヤリング、ブローチなど、いろいろな飾りをつけて美しさを表現します。
またファッションには流行があり、毎年新しいデザインが注目を集めます。
日本の着物は、これとはまったく考え方が違います。
日本の着物は植物の繊維で
初めのころより、日本の着物は植物の繊維で作られていました。
着物は、おばあさんが着たものを仕立て直したり繕ったりしながら、大切に娘や孫に伝えてきました。
また、平安時代に始まった女性の正装である、いわゆる十二単は、一千年前のスタイルですが、今着てもとても美しいと思います。
着物は外に飾りつけをつけて美しさを表すのではなくて、人間の内面からの美しさを表現しようとします。
何枚も重ね着しているのですが、下に着たものは襟元や袖口にわずかに見られるだけです。
ちらりと見える色の美しさ、襲(かさね)の色目の組み合わせで、美を表しているのです。
裁断は、平面的な裁断で、しかもたいていの人が着られるように、ゆったりと大きく作られています。
その着物を、着る人に合うように、動きやすく美しく着せ、そこに気品というか威厳というか、神様から与えられた美を表そうとしています。
しかも、使うのはたった一本の紐です。
これで体に合うようにぴったっと着せつけるには、技術と経験を要するので、主として公家の家で、衣紋道(えもんどう)と呼ばれる作法が伝えられてきました。
これは男性の装束である衣冠(いかん)や束帯(そうぞく)も、同じ考え方です。
春日大社では毎年三月十三日に天皇のお使いである勅旨が来られ、春日祭というお祭りが行われます。
日本三勅祭のひとつともいわれる由緒あるお祭りですが、天皇陛下からのお供え物は、やはり反物です。
それほど布や着物は貴重であり、神聖なものなのです。
着物に対する日本人の心が失われてゆくのは、大変残念です。
和服を着ることはあまりないかもしれませんが、若い人たちが別に贅沢な服装をすることはく、きっちりとして服を着てくれることを心から願います。
神社で神職や御巫(みかんこ)は、こうして日本人の服装を守り伝えているということも、みていただければありがたいと思います。
ありがとうございます
きものは、日本を象徴する衣裳として、世界中で広く知られています。
時代の流れとともにその着方こそ、日常着から特別な日、晴の日のこだわり着へと変化してきましたが、その着姿の奏でる世界観は、日本人誰もにとって伝統美という点で共有され、また世界においてもファッション”KIMONO”(=JAPAN)として高く評価されています。
そこには純然たる美しさもあれば、華やかさの中の厳かさや、また歴史をも感じさせるその着姿には代々続く人としての道--日本人としての系譜すら感じさせる心があると考えます。
私たちはきものを通じて、日本人としての心を持ち続けたいですね。
https://nihonyoikuni.thebase.in/
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld