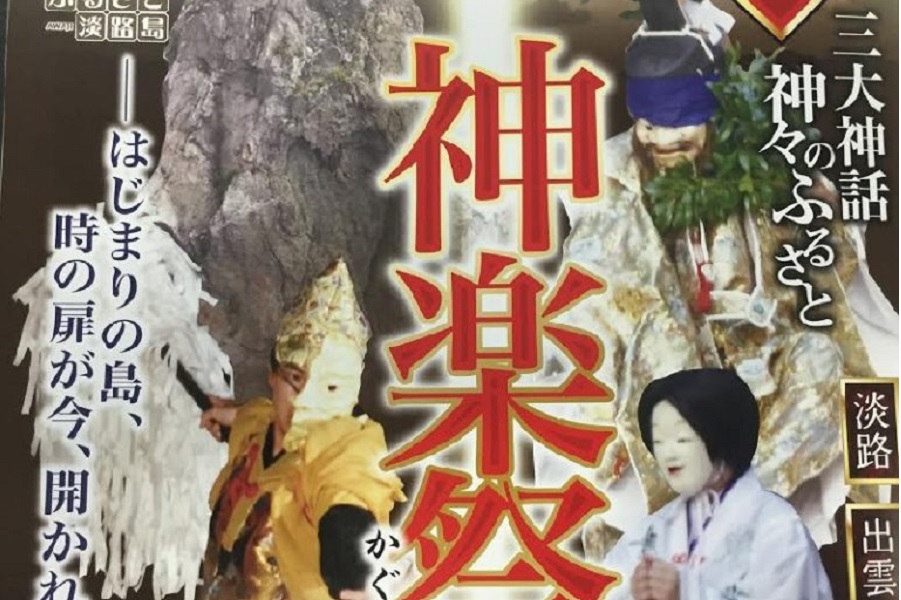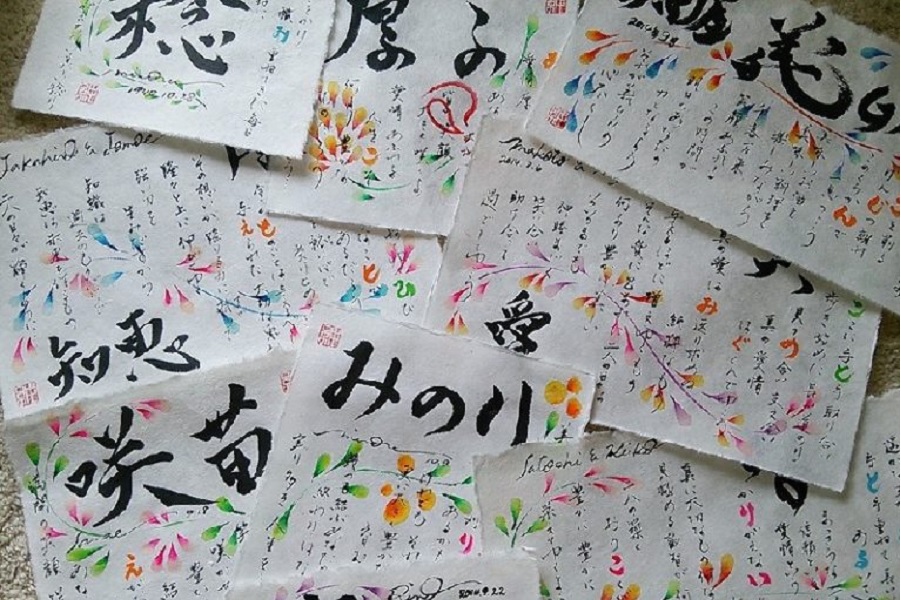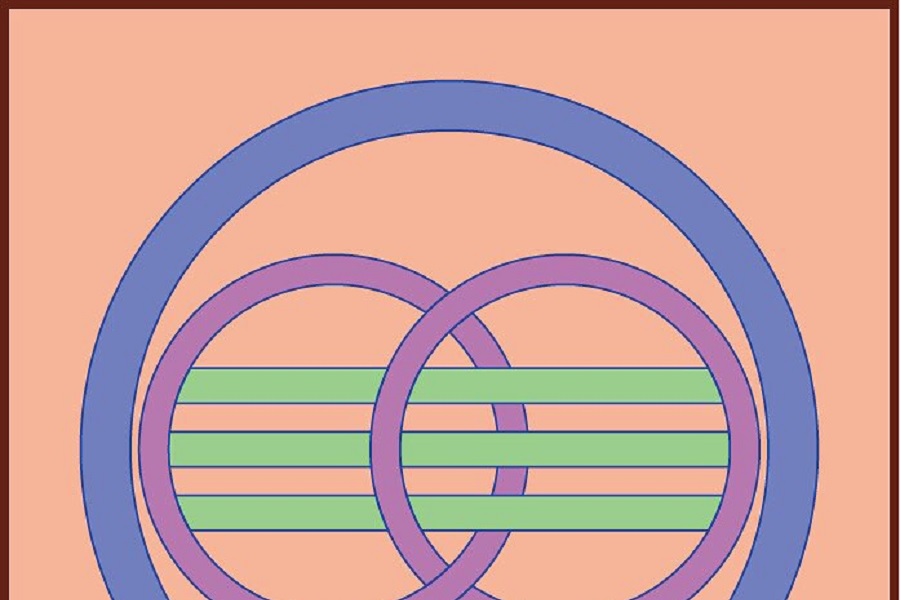芽と目、葉と歯、花と鼻、実と身

もうご存知ですよね
こんにちは。
やまとことばをいろいろと知っていくと、そのほかにも日本人ならではのものの考え方を知ることができます。
目と芽、歯と葉、鼻と花、身と実。
「め」「は」「はな」「み」。
日本人は古来より、人と植物を同じ視点でとらえていました。
人間とほかの生き物を区別することなく、人間を自然の一員としてとらえる見方です。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
同音同根
植物はどのように成長していくでしょうか。
先ず芽が出て、葉が茂り、花が咲きます。
この芽、葉、花ということばが、人間の目、歯、鼻と共通しているのは、けっして偶然ではありません。
これもまた同音同根だと考えられます。
芽というのは、土のなかや枝の途中から外に顔を出してきます。
それは、水中の潜水艦が潜望鏡を海上に出して、外の様子をうかがうようにも見えます。
つまり、外界の状態を認識するということで、人間の目に通じているわけです。
葉は、ひらひらした薄いもので、枝の端に生えてくるものです。
端という漢字は「はし」とも読みますが、山の端と書いて「やまのは」と読むことからもわかるように、これもまた同根でしょう。
そう考えると、歯茎の端に生えてくる薄い板状のものを「は」と呼ぶことにも通じています。
花は植物の中心にあって、その植物らしさを表現しているものでもあります。
人間の鼻もまた、顔の中心にあって目立っているものですから、語源は同じである可能性が高いといえます。岬の突端を「はな」というのも、顔の上に出っ張っている鼻と同根なのでしょう。
さらにいえば、植物の多くは「実」をつけます。
これを植物の本体と考えれば、人間の「身」と共通していても不思議ではありません。

ことばが心や考え方をつくります
こうして見ていくと、古代の日本人が身の回りにある草花をじっと観察している様子、そして人間の体にたとえて命の大切さを感じている様子が目に浮かんできます。
植物と人間の体を同一視するというのは、なんとものどかでおおらかではありませんか。
これは、日本人ならではのものの見方だと思うのです。
興味深いことに、中国の大学で日本語を教えている先生がおっしゃるには、日本語を学んでいる中国人学生は、ちょっと見ただけですぐにわかるとのこと。
入学直後は区別がつかないそうですが、日本語の学習が進んでいくうちに立ち居振る舞いが落ち着き、性格や話し方が穏やかになっていくというのです。
心や考え方がことばをつくるだけでなく、ことばが心や考え方をつくっていくことがわかるいい実例だと思います。
ありがとうございます
ところで、ことばはなぜ言葉と書くのでしょうか。
和歌の全盛だった時代、日本では「言霊の幸う国」といわれているように、美しい和歌には国を安泰にする力があるといわれていました。
いつまでも青々としている緑の葉を意味する常磐(トキワ・トコイワ)にたとえて、和歌の世界を「言の葉の緑」と呼んだのが始まりといわれています。
和歌が栄えることは、国が栄えることと同じと考えられていたようです。
ことばが乱れている現代。
日本人が日本人らしくなる一番はやまとことばを学ぶことかもしれませんね。
ことばはとても大切ですね。
知らないことばかり。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld