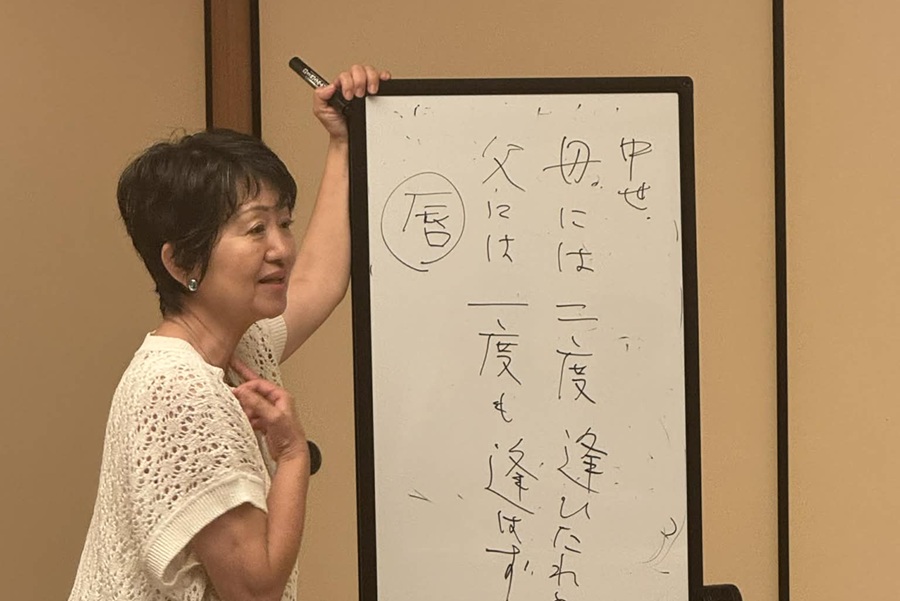相手を思いやる「おことわり」のしかた

下手な言い訳は無用
こんにちは。
早いもので11月、霜月に入りました。
別名「末つ月(すえつつき)」、もうじき今年も終わりますよって言われてるみたいです。
このころから年末、12月の忘年会などの予定も入ってきますよね。
えっ、もう12月の予定はいっぱい!ですか?
そんな忙しいときだから、新たなお誘いが入ってくるのではないですか。
このような時、申しわけなくて、どのようにおことわりしようかと考えてしまいます。
おことわりの極意は、相手も自分も気持ちよく。
下手な言い訳は逆効果。
「ありがとう」のひと言で、相手のやさしさを尊重することも大切です。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
「おことわり」
「おことわり」には勇気がいります。
でも嫌々ながら誘いを受け、その後、重い気分を抱えるよりも、理由を言ってきちんと断ったほうが、ずっと気持ちがいいと思います。
心がけたいのは、相手も自分も気持ちよくカドが立たない「おことわり」が、無理をしない人間関係をつくるうえでは大切なことです。
「おことわり」のときには、まず下手な嘘をつかないことです。
「先約がありますから」、「用事があるので」と理由をはっきり言いましょう。
あなたと出かけるのが嫌なのではなく、「たまたま、その日の都合が悪い」と伝えることがいちばんです。
「何時にどこへ行く」という用事ではなくても、たとえば「疲れているから家でのんびりしたい」という自分で決めた小さな予定でもいいと思います。
それも先約のうちではないでしょうか。
また「カドを立てない」ためには「ありがとう」のひと言が大切です。
「誘っていただいて、ありがとう」という言葉をひと言つけ加えたうえでおことわりする。
それだけで、相手のやさしさが尊重され、場の雰囲気もずいぶん和むものです。
京都の人はよく「ちょっと考えさせてもらいます」という言葉を使います。
これなどは、曖昧さの中に相手を傷つけないという気持ちを秘めた「おことわり」の代表的な例だと思います。
椀曲的な「おことわり」に長けた京都らしい表現といえます。
ありがとうございます
ちょっとした相手への思いやり。
「おことわり」するときも一緒。
曖昧さの中にも日本人らしいこころが隠されています。
そんな日本の文化を大切にしていきたいものです。
浄住寺ではこれから、この和の文化を学べる講座をしていきたいと思います。
その時は学びにお越しくださいね。
お待ちしております。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
(最初の浮世絵:葛飾北斎「富嶽三十六景 東海道吉田」
参考
いつも心に、幸せ言葉
一木一草に神がやどる <和の心>
感謝の言葉を伝え合うことの大切さとは
ひらがなで読めば日本語の不思議がわかるんですよ
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld