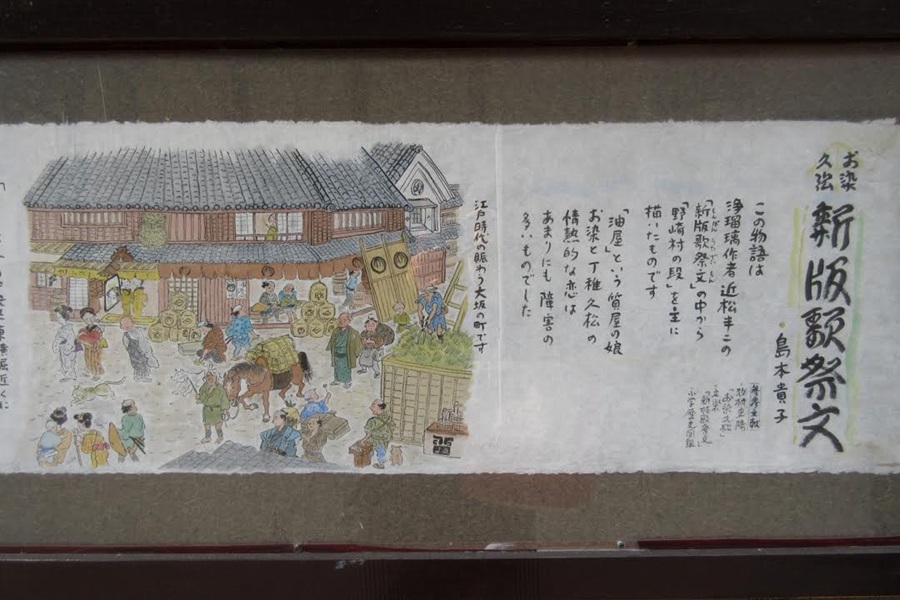明けまして おめでとうございます

戊戌年
謹賀新年
みなさまにおかれましては、無病息災、笑顔あふれる楽しい毎日となりますことお喜び申しあげます。
和の素敵は、陛下の譲位を迎えるに大切なこの一年を、改めて、日本の素晴らしいことを学んでいこうと思っています。
精進してまいりますので、今年も昨年と変わらず、宜しくお願いいたします。
念頭に素敵なお話しが産経新聞に書かれていましたのご紹介を。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
神々のいる風景 田に、山に、海辺に・・・
日本の正月はすがすがしさに満ちている。
初詣に行く神社はもちろん、それぞれの家にも街角にも淑気(しゅくき)があふれている。
戦後の占領政策などで、神道をゆがんだ目で見る見方が日本を覆った。
戦後70年以上を経て、そのような偏りはもはや過去のものとなったといってよい。
神々のいる風景こそ、この国にふさわしい。
日本の正月の習俗は、この国の人々が神々とつながっていることを濃厚に語っている。
家を清め、年神を迎えるのが正月と考えられる。
しめ縄は、神聖な場所であることを示している。
門松は、地域によって門神様ともいい、年神を迎える依り代の意味を持つ。
おせちも、元来は節日(せちにち)に神に供えた食べ物。
鏡餅は古くは、霊魂をかたどるものとして神にささげられた。
小正月には「とんど」などと呼ばれる火祭があり、正月飾りなどを焼く。
神送りの行事と考えられることが多いという。
以上、「日本民族大辞典」を参考にした。

日本人の宗教心
少し見ただけでも、正月に日本人の宗教心が濃く表れていることがわかる。
おそらくこの国の人はずっとむかしから、このようにして新しい年を迎えてきたのだろう。
習俗と結びついた宗教心は代々受け継がれ、なかなかなくなるものではない。
けれども日本の場合、宗教は戦後、大きな変質を迫られた。
正月から離れる。
戦後、日本への占領政策を行った連合国軍総司令部(GHQ)は、神道が日本の軍国主義の中核をなしているとみなし、敵視した。
終戦の年の12月、GHQは、国や自治体など公的機関と神道のかかわりを禁じる指令を出した。
国家神道は熱狂的なカルトとみなされた。
神道に関するあらゆる祭式、慣例、儀式、礼式、神話、伝説などが禁止の範囲とされた。
事実上の神々の追放だったといえる。
GHQ宗教課のあるスタッフはのちに回想録で、連合国軍の指導者の神道理解について、こう書いている。
すなわち神道の教義は「世界平和に敵意あるものであり」、国家神道のカルトによって「(日本人の)精神が汚染されている」(ウィリアム・ウッダード「天皇と神道」)。
神々の国、日本
誤解もはなはだしいといわねばならない。
けれどもこのような見方は、占領方針に沿うといってよい日本の知識人らの言動によって、占領が終わったあとも長く残ってしまった。
しかし、宮中で祭儀が行われ、家々で、全国の神社で人々が神々に手を合わせる正月の風景は、連合国軍指導者の理解とはおよそ正反対のものだ。
むしろ清らかさを尊び、神聖なものに敬虔(けいけん)な日本人の心性をこそ表しているだろう。
連綿と受け継がれてきたこの心性は、さかしろな占領方針や戦後知識人らの偏った見方で変わるものなどではなかった。
この国のあちこちの田の中に、山に、海辺に、神々はおられる。
そのような国で迎える新しい年を、心の底からことほぎたい。
ありがとうございます
戦後70数年を経て、陛下が来年ご譲位をされるこの年。
改めて日本人が日本人として、この国のあり方を考えなければいけない時ではないでしょうか。
古より神々の国として、神々とともに暮らしてきたこの地。
なにごとにも「ありがとうございます」と思う大和心。
戊戌のこの年、この国が大きく変わっていかなければ、もう立ち直ることができなくなるのでは。
憂いてしまいます。
私一人で何ができるかわかりません。
でも、できることを一つづつ、一歩づつ進めてまいります。
どうか、同じ思いのある人たちが一つになって、私という「我」ではなく、大きく丸く「皆」でという思いを広げていきましょう。
素敵な素敵な日本。
いつまでも、いつまでも、子供たちに語りつなげていけますように。
今日も最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございます。
みなさまにおかれましても、素敵な一年と成りますように心よりお喜び申し上げます。
感謝。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld