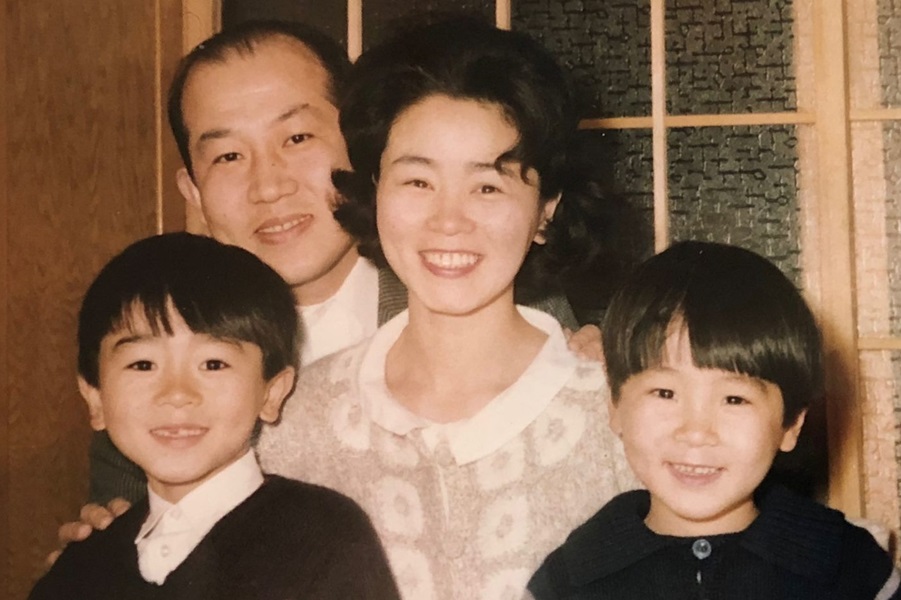今日は二十四節気の「白露(はくろ)」

露を結ぶころ
こんにちは。
空を眺めると、夏から秋へと移り変わっていくのを感じます。
今日は二十四節季「白露」。
白露とは、大気が冷えてきて露を結ぶころのこと。
暑さが処する(収まる・落ち着くという意味)「処暑」が過ぎ、昼と夜の長さが同じになる「秋分」の間で、空には夏の代名詞である入道雲の出番が減って、代わりに秋らしいうろこ雲が見られるようになります。
日が暮れるのも早く感じるようになり、ススキが黄金色に輝くのもこの季節。
ようやく残暑が引いていき、本格的に秋が訪れてきます。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
七十二候
「草露白し(くさのつゆしろし)」初候
(9月7日~11日ごろ)
早朝、野や山を歩けば、じっとりと靴や服が濡れます。
あたりを見回すと、草々に降りている露のせいだとわかります。
ついこの間まで衣服や靴が濡れてしまうことなどなかったことを思えば、それだけ季節が進んだ、というしるし。
草の露が朝日に照らされるとキラキラと宝石のように輝くのは本当に美しくて見とれてしまいます。
近づいてよく見ると、とがった葉の先端に溜まるように付いたり、縁取るように付いていたり。
どんなふうに露がついているのか、一ヶ所にしゃがんで、露を壊さぬように観察してみるのもいいですね。
「鶺鴒鳴く(せきれいなく)」次候
(9月12日~16日ごろ)
鶺鴒は、ちょこちょこと可愛らしく歩き回っては、立ち止まり、尾を上下に動かします。
日本書紀にも登場しますから驚きです。
尾を振るようすを男女の交わりに見立てたのが、イザナギとイザナミが契りを交わそうとしたとき、その仕方を教えたのが鶺鴒でした。
小鳥の尾を振る動きで、神さまたちはピンときたのでしょうか。
「玄鳥去る(つばめさる)」末候
(9月17日~21日ごろ)
南方から渡って来て子育てを終えたツバメが、そろそろまた南の国に帰り始めます。
一生懸命作った巣の中にいたあの雛たちは無事に育ったかなと気になりますね。
来年の春まで、またしばしのお別れ。
無事に数千キロの旅を終えられますようにと祈ってしまいます。
でもいつも思うこと、「不思議、どうして数千キロの旅ができるのだろう」と。

白露のいろは
赤とんぼ
空を眺めると、夏から秋へと移り変わっていくのを感じます。
その空に、すっーと現れるのが、赤とんぼ。
羽をすばやくふるわせ、飛んでいきます。
あきあかねや、なつあかね、のしめとんぼなどが赤とんぼと呼ばれるとんぼたち。
古くはとんぼを、あきつ、と呼んでいたそうです。
秋の虫という意味。
そして日本の国の名前も秋津洲(あきつしま)といいました。
野山をとんぼが舞い飛ぶ。
縁もいのちも生き生きとした国。
そんな情景が目に浮かびます。
秋の七草
言えますか?
萩、薄(すすき)、葛(くず)、撫子(なでしこ)、女郎花(おみなえ)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききょう)。
万葉集で山上憶良(やまのうえのおくら)が秋の七草を歌っています。
いちどきに咲くのではなく、秋が深まりながら花開いていく七種の草花。
たとえば萩は、万葉集でもっとも歌われる花。
秋の字が用いられるほど、秋の花としてなじみ深いものです。
逆に、藤袴や桔梗は、自生できるの山が少なくなり、絶滅の危機に瀕しているとか。
種々をたやさぬように、人の手で育て守らないといけないですね。
秋の野に咲きたる花の指(および)折り かき数ふれば七草の花 山上憶良
ちなみに秋の七草は春の七草のようにお粥にして食べません。
昔の人は厳しい冬に備えて薬草にもなる秋の草花を準備したのでしょうね。
重陽の節句
9月9日は重陽の節句。菊の節句で、長寿を祈る日です。
昔は旧暦(2019年は10月7日)で数えたので、ちょうど菊の花ざかりでしたが、新暦のこの時期は、菊にはちょっと早いですね。
平安の時代、宮中では菊を飾って鑑賞したり、盃に菊の花を浮かべて酒を飲んだり、詩歌を読み合ったりと雅に過ごしていたといいます。
また、さらに昔には収穫祭の意味合いの濃い行事で、栗の節句とも呼ばれ、栗ご飯などで祝い、感謝を捧げたともいわれています。
中秋の名月
中秋の名月とは、いわゆる「十五夜」のことです。
秋の十五夜は、一年の中でも特に空気が澄んで月が美しく見えます。
十五夜に月見をする習慣は中国から伝わり、平安時代には貴族の間で月見の宴が催されていました。
旧暦の秋は、旧暦7月、8月、9月をいいます。
中秋とは秋の真ん中、なので旧暦8月15日(2019年は9月13日)、旧暦の15日は満月ですから中秋の名月となりました。
ありがとうございます
登山を楽しむ人たちでにぎわった後、富士山の閉山日にあたる旧暦7月26日ごろ(新暦9月5日ごろ)に降る雨は、富士山を洗い清める「御山洗い」の雨、と山麓の人の間で言い伝えられてきました。
いつの時でも日本は自然をいっぱい楽しめます。
本当にありがたいことです。
当たり前と思はないでくださいね。
このありがたいことがどんどん破壊されてきてます。
虫も草花も絶滅種がたくさんでてきてます。
私たちのせいですよ。
いつも最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
自然を心から大切にしましょう。いつまでも変わらぬ日本の素敵な自然を残すために。
参照


参考
節季とは、日本は素敵だ
暦をお持ちですか? すべてはつながっているのですね
本 「入門 日本の旧暦と七十二候」
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld