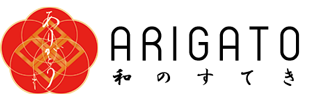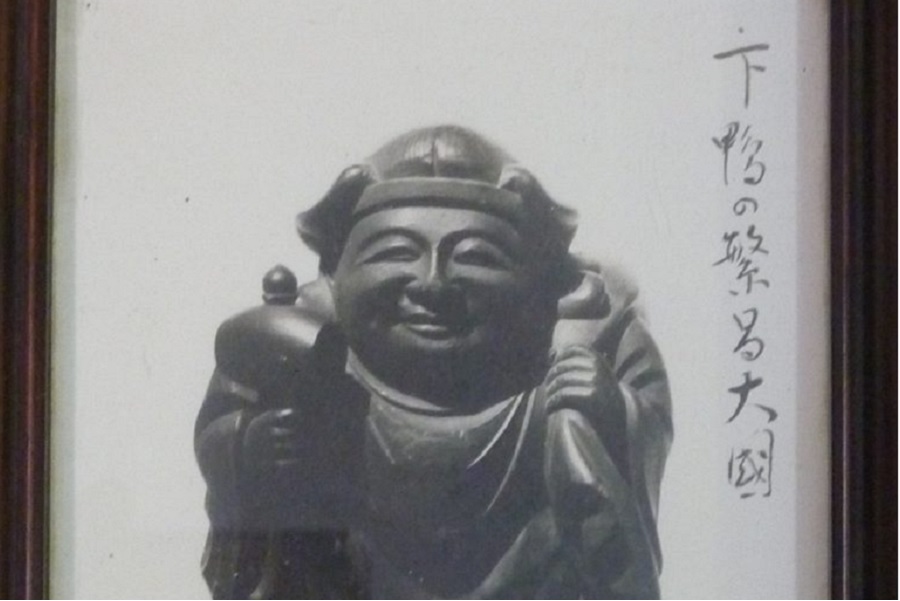「神社と神道の歴史」第4回 著:白山芳太郎

神社と神道の歴史(第4回) 著:白山芳太郎
日本のいくつかの地域、佐賀、三重、京都などに、中国(秦(しん))から「不老不死の薬草」を求めてやってきた徐(じょ)福(ふく)の上陸地とする伝承地がある。
有力とされるのが、熊野市波田須(はたす)町である。
李氏朝鮮時代(15世紀)に著された『海東(かいとう)諸国(しょこく)紀(き)』によると、徐福は「不老不死の薬草」を求めて日本の「紀州」に上陸し、日本で亡くなり「神」となって人びとに祀られたと記されている。
熊野市(旧・紀州)の波田須町では、秦の始皇帝の統一後に鋳造された貨幣(秦半両銭(はんりょうせん))が出土している。
また、同町に徐福を祀る「徐福神社」がある。

(徐福神社 Wikipediaより)
同神社の所在地は、熊野市波田須町の「丸山」というところである。
同じ熊野市の熊野川上流にも「丸山」というところがあって、前回触れた苗(ミャオ)族の「棚田(たなだ)」を思わせる「丸山千枚(せんまい)田(だ)」がある。

(丸山千枚田 白山芳太郎撮影)
「徐福」の船団は3000人に及ぶものであったから、上陸後の3000人への「食」の提供について事前に計画を立てていたはずであり、その中に農の集団が乗船していたことと思われる。
山がちの日本の地形を考慮し、苗族から選ばれた人びとが、その船団のなかに加えられていたのではないか。
この人びとが日本における最初の「棚田」を造ったのではないか。
日本の諸地域に「棚田」があるが、そのうちの古いいくつかは、この人びと、もしくはその子孫によって造られたものであろう。
そう考えたくなるほど、日中両「棚田」は似ている。
中国奥地の苗族(ミャオぞく)の村に、日本の「棚田」が伝えられたとは思えない。
日本の棚田は、苗族の「棚田の技法」が伝えられたものではないか。

(苗族の棚田 Wikipediaより)
「徐福上陸」伝承地は、丹後半島の「伊根(いね)」や「佐賀」にもある。
この船団は、きわめて大きな船団であるから、いくつかのグループに分れて上陸し、そのうちの1つが「熊野」に、また別のグループが「伊根」や「佐賀」に上陸したのであろう。


(伊根の徐福を祀る神社・新井崎神社とその周辺の千枚田)
徐福は『史記』(巻百十八)によると、2200年前、秦の始皇帝の命により「東方の三神山」に「不老不死の薬」を求めて、3000人の男女と百工(多くの技術者)を従え、五穀の種を積んで出航し「平原広沢」を得て王となり、秦には戻らなかったとされている。
この出来事は、BC219年のこととみられる。
列島が縄文時代を終え、弥生時代を迎える頃である。
「平原広沢」とは、広々とした平野と湿地と言う意味である。
彼らが営んだ水田が広々としていたということであろう。
「男女3000人」とは、農の集団を意味するのではないか。
しかし、彼らは1度ひき返した。
当時の倭は「狩猟採集生活」の時代である。
いわばジャングルであった。
航行を開始し、黒潮(くろしお)に乗って進むと、最初に到着する「倭」は、五島列島である。
第1次船団は、出航後、間もない頃、五島列島に到着したことであろう。
徐福らが、その時、見たのは「稲作」が始まっていない時代の「倭」であった。
「食」を得るための労働は、鯨やイルカの捕獲と、ジャングルでの狩猟であった。
彼らはその様子を見て「薬草」発見までの日々は長期化するであろうと直感したと思う。
「倭」の「衣・食・住」を見て、出港前夜における準備がきわめて不足していたことを強く実感したことであろう。
焚書(ふんしょ)坑儒(こうじゅ)をやってのける始皇帝の強烈な怒りを顧みることなく、1度引き返した原因は、そのような準備不足にあったと思われる。
徐福は、船団の構成員を、倭での生活の長期化にともなう「衣・食・住」のための人員を中心とするものに切り替えた。
「不老不死の薬」を持ち帰ることのない「2度目の帰国」を、始皇帝は決して許さないであろう。
そうなれば、多数の受刑者とともに、自分の命もないと考えたことであろう。
追い詰められた徐福は「薬草」が見つからない場合は帰国しない、つまり亡命を考えたのではないか。
だとすると『史記』の「秦に戻らなかった」という伝えや『海東諸国紀』の「紀州で亡くなり神となった」という伝えは、徐福たちの日本移住を意味するのではないか。
この一族は機(はた)織りを生業(なりわい)とし、日本で「秦(はた)氏」となったという日本側の伝え(『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』)も考慮しなければならない。
彼らの上陸後の「衣・食・住」を見た日本人は、それにあこがれ、それを学ぼうとしたに違いない。
われわれが今日「和服」と呼んでいる服は、中国から伝わった服(呉服(ごふく))である。
彼らは呉服を着て上陸し、呉服を着て労働した(当時の倭人たちの服は『魏志倭人伝』によると「貫頭(かんとう)衣(い)」であった)。
また彼らの船には「蚕(かいこ)」が積まれていた。
そして上陸後、生糸(きいと)を紡(つむ)ぎ、機(はた)織りを行った。
上陸後の彼らの伝承が「秦(はた)氏」伝承へと切り替わったことをふまえて言えば、彼らの影響下、日本人の着る着物も「貫頭衣」から中国(華南地方)の襟が開いた服(呉服)に移行するのを促したと考える。
彼らの主食は「米」であった。
倭人の主食は肉食(鹿やイノシシ)であった。
日本人の主食が、この後、肉食から米食へと切り替わるが、そのことが促進されたと思われる。
倭人の住まいは「竪穴式住居」であった。
彼らの住まいは「高床式住居」であった。
沖縄海洋博の時、インドネシア(トラジャ族)から「高床式住居」が運ばれた(現在、海洋博記念公園収蔵庫に収納されている)。
それは弥生時代の銅鐸(どうたく)に描かれた線描(せんびょう)の住居図や、弥生遺跡から出土する柱穴から復原される弥生時代の住居にそっくりである。
この「高床式住居」は、掘立柱で建てられるとともに、妻の中央に「棟持柱(むなもちばしら)(棟を持ち上げる柱)」のある建築であった。

(妻の中央に「棟持柱(むなもちばしら)」のあるトラジャ族の住居 Wikipediaより)
「棟持柱」は、今日の神社建築では、伊勢神宮およびそれを移築した熱田神宮、仁科(にしな)神明宮、伊勢山(いせやま)皇大神宮などで見られる。
建築技術が進歩し、一般の神社は、柱を(土中に埋めず)礎石の上に立てる技法になったため「棟持柱」はない。
そういうなか、掘立柱の技法を守ったのが伊勢神宮(その技法を「唯一神明造(ゆいいつしんめいづく)り」という)である。
ただし「棟持柱」は、弥生時代の住居の柱穴では普通に見られるものである。

(妻の中央に「棟持柱」のある伊勢内宮 白山芳太郎撮影)
徐福ら3000人の「衣・食・住」に接した日本人はそれにあこがれ、それを学んだ。
「稲」が伝来しただけでは新しい文明は「普及」しない(明治の西洋文明も、黒船がやって来ただけでは普及しない。横浜や神戸に移住した西洋人の「衣・食・住」を見た日本人がそれにあこがれ、それを学ぶことによって普及した)。
そういうなか「水田稲作」を行う男女3000人の「衣・食・住」は、新しい文明が普及していく上での大きな後押しとなった。
そのような「水田稲作」とともに、新嘗祭(にいなめさい)(新穀感謝の祭り)や祈年祭(きねんさい)(豊作を祈る祭り)などの「稲作祭祀」(弥生時代の祭祀)が開始された。
ただし、新しい「稲作祭祀」は、在来の神を「国つ神」(縄文時代の神)新しい神を「天つ神」と言い分ける以外に区別を行わず、両者を総合して「神」とした。
海外の例えば「パルテノン神殿」など、アクロポリスの神殿は、6世紀のキリスト教に取り込まれて破壊され、新しい文明の普及は、在来の神殿を「廃墟」にすることから始まった。
わが国では、縄文時代の信仰を尊重し、その祭りと神話を後世に伝えた。
たとえば「柱」を立て、その柱で「動物の霊を天に送る」ことが「縄文祭祀」であったから、縄文祭祀では神の数を「ひとはしら」「ふたはしら」と数えた。
その数え方を「天つ神」の数え方においても採用した。
われわれは、今、神の数を「ひとはしら」「ふたはしら」と数えるが、そのことの根底に「縄文祭祀」における神の数え方が残っているのである。
「稲」の伝来(詳細は次回に述べるが縄文前期。今から6000年前)から3000年がかかった後になって「水田稲作」(この後に述べるが縄文晩期のBC10世紀)が開始した。
「稲」の伝来だけでは、弥生時代に移行しない。
「水田稲作」は、唐津市の「菜畑(なばたけ)遺跡」(縄文晩期のBC10世紀)が最古である。
同遺跡から炭化米や石包丁(いしぼうちょう)などの農具とともに日本最古の「水田」が出土した。
「縄文水田」である。
次に古い「水田」は、福岡市の「板付(いたづけ)遺跡」から出土した。
同遺跡からは縄文最後の土器(夜臼式(ゆうすしき)土器)と弥生最初の土器(板付式(いたづけしき)土器)が出土した。
「水田稲作」の先進地域は、このような玄界灘沿岸であった。
しかし、このような「水田稲作」が開始されただけでは、弥生時代に移行していない。
九州全域~関東にかけての受け入れ側は、そのような「水田稲作」を受け入れた後も、土器や稲刈りの道具などの面において、縄文期の道具を使った。
弥生文化への縄文側の抵抗である。
「土偶」など、縄文時代の道具による「縄文祭祀」も行った。
これも弥生文化への縄文側の抵抗である。
土器で煮炊きするという世界でも珍しい狩猟採集文明は「水田稲作」を受け入れた後においても抵抗し続けたのである。
前述の通り「水田稲作」はBC10 世紀に始まったが、九州全域~関東にかけての「稲作の普及」は、BC3世紀を待たねばならなかった。
BC10世紀~BC3世紀の700年をかけて「弥生文化」への移行が行われた。
そのような時期、秦からやってきた男女3000人の新しい「衣・食・住」は、日本人にとって強いインパクトとなった。
そして「弥生文化への傾斜」を強く後押しした(近代における「西洋文明への傾斜」も黒船来航だけではインパクトとならず、横浜や神戸に移住した西洋人の「衣・食・住」が、強いインパクトとなって「傾斜への後押し」となった)。
BC10世紀~BC3世紀における弥生文化への移行期に、信仰の方も「天つ神」(弥生の信仰)と「国つ神」(縄文の信仰)の習合があって、両者を一体化した「天つ神国つ神」の信仰となった。
それが、今につづく「神祇(じんぎ)信仰」(あまつかみの漢語訳が「神(じん)」。くにつかみの漢語訳が「祇(ぎ)」)である。
第5回に続く

白山芳太郎 プロフィール
昭和25年2月生まれ。
文学博士。皇学館大学助教授、教授、四天王寺大学講師、国学院大学講師、東北大学講師、東北大学大学院講師などを経て、現在、皇学館大学名誉教授。
おもな著書に『北畠親房の研究』『日本哲学思想辞典』『日本思想史辞典』『日本思想史概説』『日本人のこころ』『日本神さま事典』『仏教と出会った日本』『王権と神祇』などがある。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World