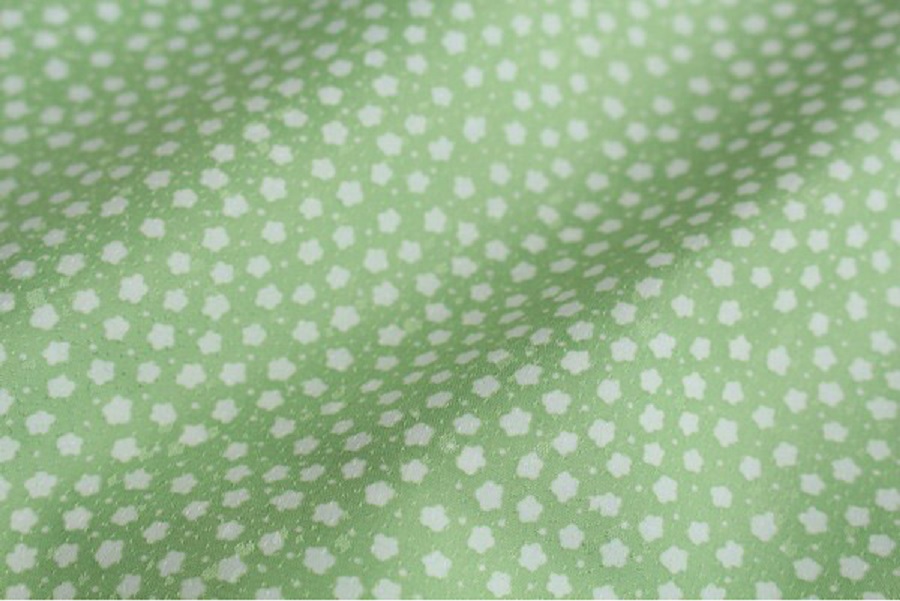和の心 「心と姿」

外見と中身の関係
「姿は似せがたく、意は似せ易し」
(外見をまねるのは難しく、心は真似しやすいものです)
ちょっと聞くと、普通とは逆のことを言っているように聞こえます。
たしかに、上から下までブランド品で決めていても中身が伴わないからダメだとか、猿まねだとかいう悪口をよく聞きます。
一方、武道や芸事では型を重視します。
たとえば茶道のお手前では、所作(動作)が美しいことが求められ、実践されています。
意味がわからないと真似もできませんが、意味がわかっているだけではだめなのです。
儒教で尊ぶ「礼」も、礼儀作法ですから、型が大事です。
だから孔子はわざわざ、「礼は玉(ぎょく)や絹布(けんぷ)のように外見ではないぞ、その精神が大事なのだ」と小言を言わねばならないのです。
外見と中身の関係は、なかなか微妙なのです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
和歌の世界の形式
さて、和歌の世界でも形式は重要な問題でした。
万葉風の歌を詠むとか、後世風の歌を詠むとかいうことがよく話題となったのです。
師の賀茂真淵は万葉風の推進者ですから、万葉風に詠むことが最も大切なこととしました。
つまり、「万葉ぶり」という外見を第一としました。
ところがそれに対する批評もありました。
いくら形を真似しても、今の人の心は万葉人とはかけ離れているから、万葉風の歌を詠んでも意味がないというものです。
そのような意見に対して、宣長は、外見こそが問題で中身はなんとでもなると言ったのです。
この言葉が有名になったのは、小林秀雄が取り上げ、「ここで姿というのは、言葉の姿の事で、言葉は真似し難いが、意味は真似し易いと言うのである」と解釈してからです。
小林は、宣長の真意は「本当に事を言ってやろう、言葉こそ第一なのだ、意は二の次である」と述べています。
やはり宣長は「言葉」なのです。
深い思いで相手を感動させることもあるでしょうが、誠意のない人だとわかっていてもその声や言葉が聞き手の心をとらえることもあるということでしょう。
(中略)
和歌の起源については、言語の技巧と心情の働きを切り離す在満とは異なり、真情を根底としての技巧と考えます。
この点は真淵と同じですが、その技巧の発達を認めない真淵と違い、和歌を生み出す真情の内面的、必然的な展開としての技巧の発達があると考え、その極致として新古今風を尊重します。
つまり和歌の技巧(表現技術)は発展するが、それは技巧のための技巧ではなく、歌を生み出す人の心に芽生えた感情の深まり、またそれを表現するための発展であるという考え方なのです。
技巧とはすなわち「言葉」であり「姿」なのです。
そしてその「姿」があっての「心」だ、と宣長は言うのです。
(文:日本人のこころの言葉:本居宣長著)
ありがとうございます
作者が区別できない二つの歌を前にして、こちらが本物でこちらが似せ物であるというためには、彼の大義という見方に宣長という言葉を導入して初めて言えます。
なぜならば、彼の大義に対する信奉のもとでは、宣長の言葉によって詠まれた歌が大義に反するということからしか、似せ物であるということは言えないからです。
したがって、歌の調べについて何も語っていません。
ある時代の人の歌をよんだ時、その心を知るのは難しいのでしょうか。
それはその言葉の調べを知るよりも簡単だというのが宣長の指摘です。
意には姿がありません。
だから、意を知るにあたって似ているとか似ていないとかの区別は無用ではないか。
だからこそ、言葉が実用的である、つまり意志の疎通について便利なのです。
意は似せ易い。
姿が無いから、柔らかく透明に変化してからだに入ってくることができるのです。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld