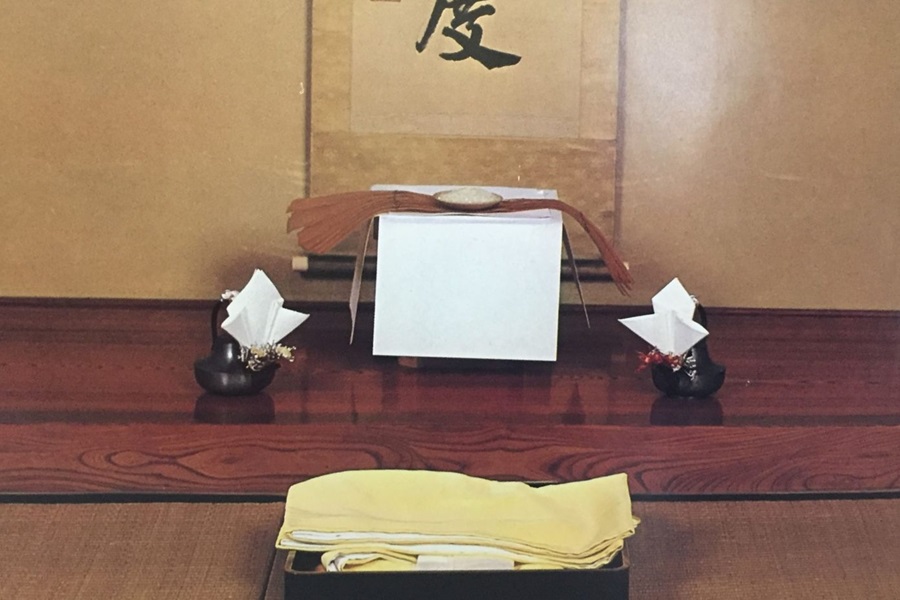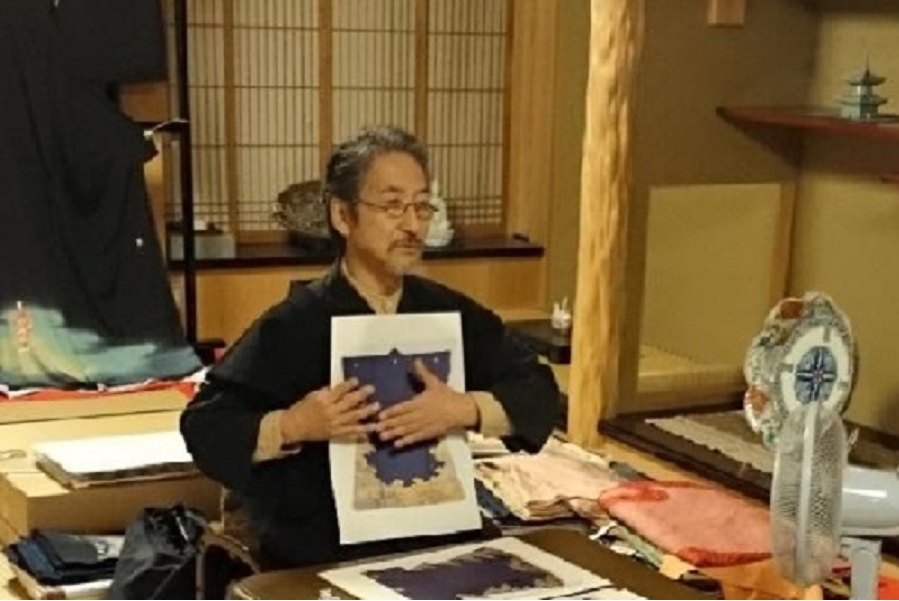大祓詞 現代語に訳すと(後段)

大祓詞(おおはらえのことば)
こんにちは。
昨日からの続きです。
大祓詞の筋は、民族の祖紳の言葉を軸に語られています。
前段は、葦原の中つ国(日本)平定から天孫降臨し、天孫が日本を治めることになるまでの内容が語られ、そして人々が犯す故意の罪や無意識の罪や穢れの祓い方が述べられています。
後段ではそのような祓いを行うと、罪穢れがどのように消滅するかが語られ、罪穢れが消えて無くなる様をいろいろな例えで表現した後、四柱の祓戸の神(はらえどのかみ)によって消え去る様子が述べられています。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
それでは後段を現代語にしてみますと
「それは、まるで雲や霧が風で吹き飛ばされて消えていくようでもあり、船が海を自由に泳ぐ姿のようでもあり、森の木々を切るとまわりが明るくなって気持ちまで爽やかになる様子に似ています。
そして罪や穢れ(ケガレ)は一つも残らず、きれいに清められるのです。
では、そうやって消えた人間の罪やケガレは、どこに行くのでしょうか。
実は、神さまたちの力で、広い海に流され、海の底に沈められ、そして、深い地下の国に吹き飛ばされて、最後は、どこかに行って跡形もなくなるのです。
みなさんが知らず知らずのうちに重ねてしまう罪やケガレも、きれいに消し去ってくれるよう、たくさんの神さまが清め、祓ってくれているのです。」
川の濁流が大海にいくら流れ込んでも、海は決して濁らず、いつも間にか元の清らかな海水になっているように、先人は、海の自浄作用が四柱の祓いの神の働きに因るものと信じたのです。
元来、祓いというのは、けがれを取り去って清浄になること。
その清浄の究極は、神からいただいた本来の自分に帰ること。
すなわち神の心と自分自身が一緒になることにあります。
私たちは、大祓詞を毎朝や霊前に唱えて、わが家を祓い、わが身を清め、心を涼やかにして、そして少しでも神の御心に近づくよう努めたいものです。
(発行:神社新報社・文:吉村政徳・絵:深田泰介)

ありがとうございます
「清浄」、清らかにする。
人間生きていくなかで、罪穢れなく過ごすことはとっても難しいです。
自分に罪穢れを感じたときは、大祓詞で自分を清めてください。
清浄を用いた言葉に「六根清浄」(ここでは「しょうじょう」と読みます)があります。
六根あとは人間の持つ六つの感覚機能をいいます。
人間の持つ六つの感覚機能、目・耳・鼻・口・身体・心を清浄にして心を大切にしていくことを説いています。
感覚機能が働けば、見たくないものまで見えてしまいます。
聞きたくないことまで聞こえてしまいます。
これは社会で生活している以上防ぎようのないことです。
しかし、嫌なことをみたり聞いたりしても、それをいつまでも心に留めておかず、心を切り替えて嫌なことを流してします。
これが六根を清浄に保つことなのです。
そういつもいつも清らかに、清らかに。
腹をたてずにいつも笑顔でいましょうね。
まだまだ出来ない私ですが(笑)。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World