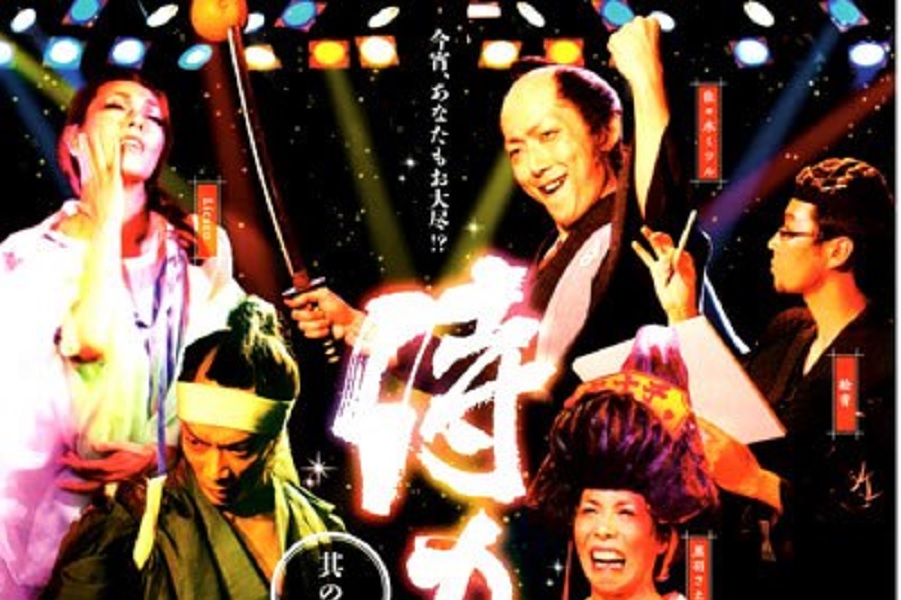和の心 No90 いのちの自覚

「神を祭る」のご本の中から
こんにちは。
前皇學館大学学長の谷省吾さまの「神を祭る」のご本の中から。
日本の思想史を見てみますと、「絶望」という思想はありますけれども、「断絶」ということについて深刻な思索をとげた思想は、ほとんど無いかのごとくに見られます。
これは、民族として、国家として断絶という経験を持たなかったからでありましょうか。
日本はいのちを一貫してきた国であります。
断絶がありません。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
いのちの根源の神聖性
いのちの自覚というものは、「ふるさと」の感情を伴うものでありますが、そのふるさとは、空のものではない。
おごそかにして、したはしいという気持ち。
神宮祭主北白川房子様のお歌に
「かたじけな おごそかにして したはしき 大御祭も いまし仕へぬ」
とあります。
その「おごそかにして、したはしい」というきもちは、抽象的観念としてではなく、事実に立脚したものとして生きているのであります。
吉田松陰が獄中で書いた「講孟剳記(こうもうさっき)」の中に、
「瞑目して此の身根本の来由を思へば、感激の心悠然として興り、報効の心勃呼として生ず。」
と述べているものも、それでありましょう。
根源にあるものは、善というべきものでもなく、悪というべきものでもなく、両者の対立でもありません。
根源にあるものは、清浄なる神聖性、神聖なる清浄でありましょう。
神道とは、その清浄を取りもどそうとするものであります。
祓へによって、それに近づこう、それをとりもどそうとする。
たえず、祓をくりかえすことによって、その本来のものにたちかえらせていただこうといたします。
その本来の清浄、本来の神聖、それはすなわち、いのちの出てかえるところであります。
そこにかえるとき、いのちはよみがえります。
その神聖なる清浄がいのちの出発点であり、ふるさとなのであります。
このいのちの根源の神聖性の自覚、それは大いなる可能性の自覚でもありますが、そこに生に対する誇りがあり、喜びがあり、人が生まれることのめでたさがあると思います。
いわゆる原罪の思想からは、基本的にこの喜びは与えられないのであります。
神道は窮極には神々にも通ういのちの、たましいの、連続を自覚しました。
神道において神々は、おそろしきものであります。
しかし、なつかしきものであります。
そのいにちの連続を自覚したとき、単なる原始以来の信仰というレベルを越えた「神道」の成立があったのであります。
ありがとうございます
先日の草場一壽さんの「生命の旅は終わらない」にも書かれましたが、いのちの連続を自覚することの大切を谷先生も語っていらっしゃいます。
世界の人びとの、神道に対する関心も増大しつつあります。
しかもそれは、単なる関心ではなくて、関心以上に魂をよびよせる何かがそこにあると感じているようであります。
彼らが失ってしまった大事なものの、美しく純粋な伝存をここにみて、感動するかのごとくであります。
事実、そういう風に感想を述べる人も少なくありません。
神宮においては、日本人のとってのみならず、外国の人びとにとっても、一つの郷愁の対象であるかのように思われます。
もとより外国の人々にとっても、一つの郷愁の対象であるかのように思われます。
それは、その郷愁が、一歩すすんで、いのちのふるさとの自覚となりうるなら、積極的な力として神道を仰ぐ境地がひらけてくると思ういます。
いのちをいただいたからこそ、今に感謝。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld