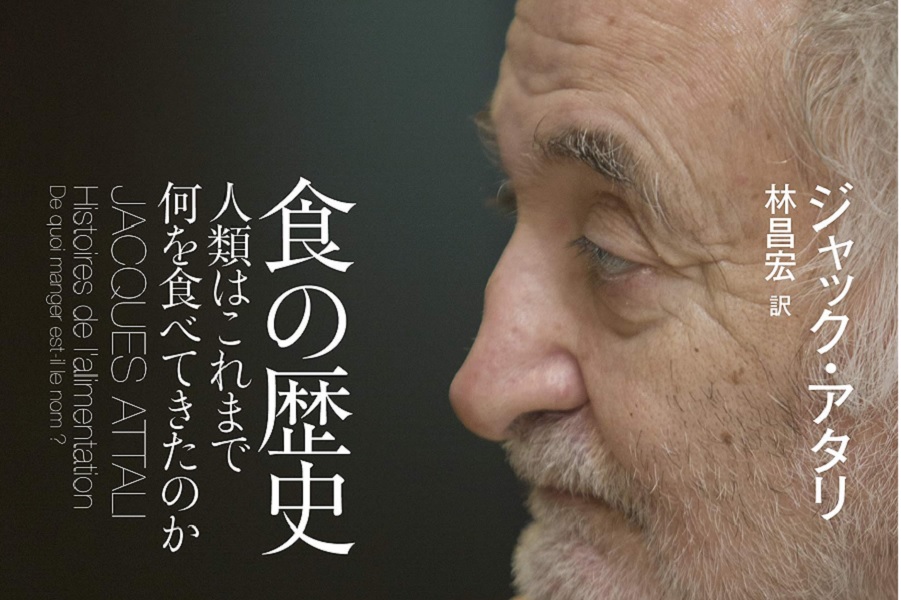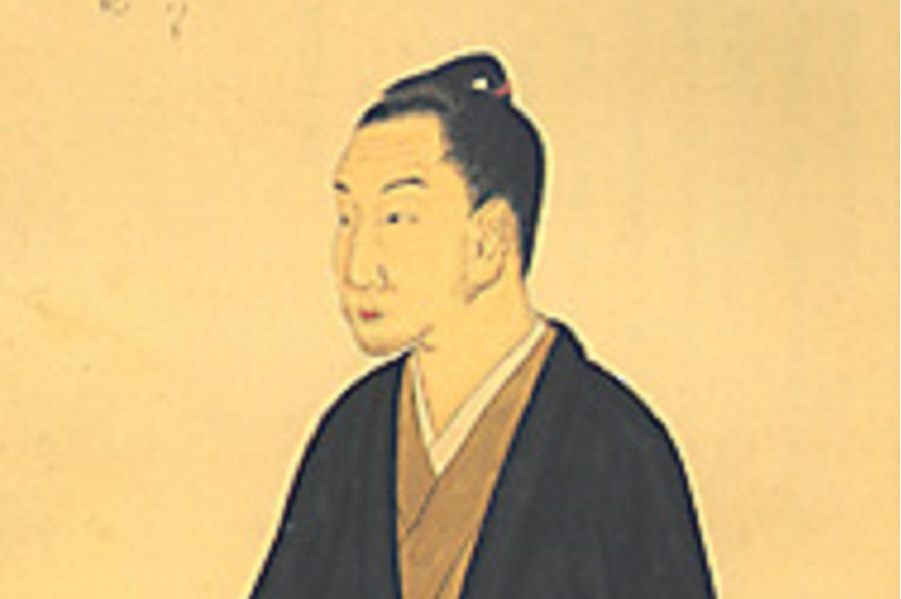茶色の種類は様々 その特徴について考えてみよう

歌舞伎から茶色は色々
こんにちは。
落ち着いたイメージがあり、暗い印象を受けやすい茶色ですが、種類も色合いも幅広くファッションカラーとしてよく目にする色です。
茶色は室町時代にお茶の成分から作られたといわれています。
しかし、今のようなブラウンではなく、鶯茶と呼ばれる緑が強いものでした。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)
四十八茶百鼠という言葉をご存知でしょうか。
江戸時代では、着る織物の繊維から色や柄まで決められていた時期がありました。
身につけていい色が藍、鼠、茶色の種類だったのです。
少しでも違った色合いをという職人の思いによって、作り出された多くの鼠、茶色の種類を四十八茶百鼠と呼び、日本の伝統色として歴史を刻んでいます。 文字から読み取ると48種類の茶色と100種類の鼠色と考えてしまうところですが、特に意味はなくたくさんの種類という意味での語呂合わせのようです。
団十郎茶
団十郎と聞いて思い浮かべるのは、歌舞伎ですよね。
この茶色は、市川團十郎のシンボル的なカラーであり、襲名披露の際に身に着ける裃の色として使用されています。
歌舞伎役者五代目市川團十郎が披露した演目、「暫」で使用した素襖の色から名付けられた色。
明るい赤みのある茶色が特徴で、歌舞伎の色では「柿色」と呼ばれています。
茶色の種類に歌舞伎役者の名前が付けられているところから、当時の文化の流行りが見えてくる気がしませんか。

芝翫茶
歌舞伎と色の関係は、団十郎茶だけではありません。
三代目中村歌右衛門が好きだった色として、渋めの赤みがかった茶色を芝翫茶と呼び、江戸時代後期に人気を集めたと言われています。
歌右衛門の俳名の「芝翫」から名付けられた茶色の名前。
芝翫人気は茶色の種類を作り出しただけではなく芝翫香や芝翫縞など、あらゆる物に芝翫の文字が使われたそうです。
まさに当時のビッグスターの象徴ですね。
璃寛茶(りかんちゃ)
芝翫茶と同じように人気があった茶色の種類「璃寛茶」。
大阪で人気だった歌舞伎役者二代目、嵐吉三郎が好きだった色と言われています。
俳名が璃寛だったことから、璃寛茶として人気の色となりました。
美男子と言われた嵐吉三郎は、女性を中心に人気が高かったと今も語り継がれています。
黒をベースにした緑に近い茶色は、当時の若者の流行りの色だったそうです。
イケメンは、いつの時代も人気者ですね。
路考茶
歌舞伎役者二代目瀬川菊之丞の俳名「路考」から、つけられた茶色の種類「路考茶」。
女形として絶大な支持を得た菊之丞。
江戸時代の浮世絵の着物の色は、路考茶がよく描かれていたと言われています。
茶色なのに淡く金のような輝きを秘めているグラデーションに、派手ではなく落ち着いた上品さが人気だった理由のひとつではないでしょうか。
長年の間、お洒落な色として人気があったのは、歌舞伎文化が根付いた証なのかもしれませんね。
ありがとうございます
千利休が好んだ茶色の種類として緑が強めの、抹茶をイメージしたような「利休茶」。
茶色というよりは柔らかい緑を基調とした薄茶色は、千利休が好んでいたという色だったとして呼ばれるようになりました。
しかし、このエピソードが記されているものは江戸時代だったので、没後であるために信憑性が低いという説も残されています。
千利休が実際にどんな色が好きだったのか、気になりますね。
このように、茶色の種類には明るさから色調まで、独特で落ち着いた風合いのカラーがたくさんあり、限られた範囲でのお洒落を楽しんでいたことが伺えます。
茶色の種類は当時の流行を知るポイントに 当時の人気だった人物の名前をモチーフにした名前が、色の名前に使われた江戸時代。
歌舞伎役者に憧れる民衆の気持ちが、身に着ける着物にも影響が表れているのではないでしょうか。
茶色の種類の多さを見ると、お洒落にこだわっていることが伝わります。
昔の流行りを色彩から学んでいき、違った角度から和の心を感じたいですね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
和服には種類が豊富。その種類とは
赤茶色の顔料「丹土(につち)」の色ってご存知ですか?
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld