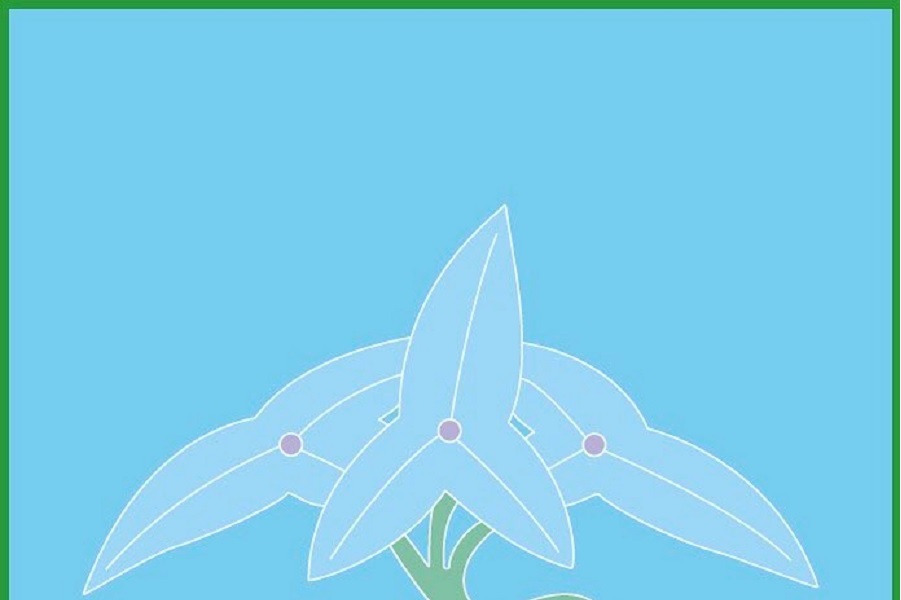これからは心の時代

薬師寺村上管主のお話し
こんにちは。
世界が混迷しているなかで「私たち日本人としての心をどうやって取り戻していったらよいのか」と思う時があります。
自国の古典は脈々とつながっている思想や文化や歴史、心を伝えていくうえで貴重なものです。
その文字が読めなくなるのは、大変大きな損失なのではないかと思います。
外国語ができればいい、というのとはまったく別の問題です。
その国で長いあいだ培われた言葉、文字にはひとつひとつの重みというものがあるはずです。
日本人は漢字が読めたり、ひらがな、カタカナが読めたりします。
ですから昔の書物、「古事記」や「日本書紀」も読もうと思えば読むことができ、そうした古い書物に親しんで日本人の精神文化をそれとなく吸収することができます。
とてもとても大切なことではないでしょうか。
さて、今日は12月16日(土)に黎明会の和の学びでお話しをいただきます、薬師寺の村上太胤管主のご本からです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
生病老死
御釈迦さまは最初のお説法で、「苦諦(くたい)、集諦(じったい)、滅諦(めったい)、道諦(どうたい)」---「人生というものは四苦八苦からはじまる」と「四諦八正道(したいはっしょうどう)を説かれました。
毎日苦しみが多いわけです。
生病老死、生まれてくることも生きていくことも、また年をとることも苦しみです。
苦しみが多い。
この苦しみを苦しみと受け止めるかどうか、その答えが「般若心経」には説かれています。
「般若心経」の主人公である観自在菩薩は、智慧を磨いて心に価値観を持って生きよう、と教えてくださいます。
外にある価値観ではなく、自分の心の内側に価値観をつくっていきましょう、と説いておられます。
日本人の心がどんどん失われてきて、西洋的な価値観や経済的な価値観が優先されている時代です。
そういう社会で生きてきて、定年を迎えようやく仕事を辞めて自分の生き方をもう一度取り戻そうという方も多いように思います。
私も団塊の世代ですから定年を迎えた友人がたくさんいますが、どうも上手に年をとる人とまったくその逆の人がいるのではないかと感じます。
その違いは何なのかなと考えると、やはりふだんからの心の持ちようにあるようなのです。
会社で偉くなる。
人よりお金儲けよう。
そういうことを第一に生きてきた人は、仕事を終えたとき心が貧しくなっているのかなという気がします。
何事も右肩上がりがいいわけではないのですね。
今はとらわれない心をもう一度取り戻すことが必要な時代ではないでしょうか。
「色即是空」
目に見えるものだけではない。
日本人としての心、人間の心を豊かにするように日々生きていくことが大切だと思います。
お金がある、ものがある人を見て自分と比較していますと、うらやましいことばかりになります。
「あれも欲しい、これも欲しい、上を見たら星だらけ」という川柳がありますように、欲しいものだらけになってしまいます。
それではあまりにも心が貧しい。
欲しいではなく与えることのできる人間になっていくことが智慧の世界です。
外との比較をするのはなく、心の価値を深めていく。
そのためには今一度、日本人として神さま仏さま、ご先祖さまのことをしっかりとかんがえてみていただきたいと思っています。
空(くう)
干支の子(ね)は「了」=「終了する」という意味にこれからはじまるという意味で横「一」が加わり、「終了してあらためてはじまる」という意味になります。
ですから十支のいちばん最初にきているわけですが、何気なく見ている十支のわずかひと文字にも漢字文化が広がっています。
千三百年前の天武天皇の時代であれば、言葉や文字というものは、きっと今よりももっといろいろな意味合いを持っていたのではないかと思います。
「般若心経」は「空」の教えですが、たったひと文字の「空」ということを理解するために、一生懸命日々勉強をさせていただいてます。
「空」というわずかひとつの漢字の意味がわかるかどうか、そのために何十年もかけて学んでいくわけですが、そのことこそがまさに「空」であり、「智慧」を磨くことにつながっていくのだと思います。
(本「かたよらない こだわらない とらわれない 般若心経の力」 薬師寺村上太胤管主著)
ありがとうございます
生老病死、生まれていつか死ぬ、長くなったといっても人生80年ぐらいでしょうか。
私も来年60歳。
生きてる(生かされてるのかも)意味が何となく少しはわかってきたのかなと思ったりもしますが、わかるのと行うのとでは違う。
ましてや「空」。
悟りを開くなど・・・。
何十年と学んでいくわけですね。
繰り返して行っていくことですね。
そこには感謝の心がしぜんとうまれてくるのかもしれません。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
村上官主に浄住寺にお越しいただいて、お話しをお聴きしたいと思っている私。
近いうちにぜひともお願いします。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld