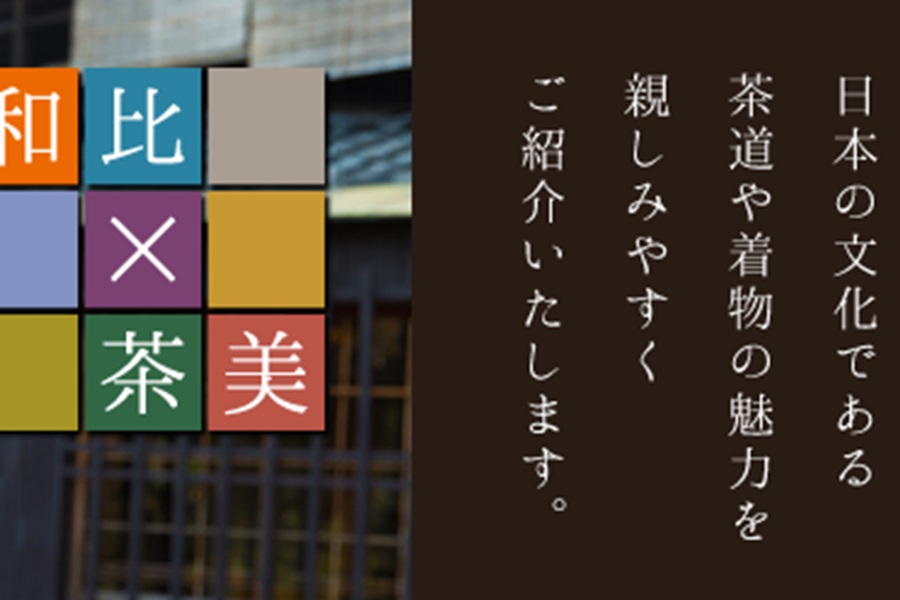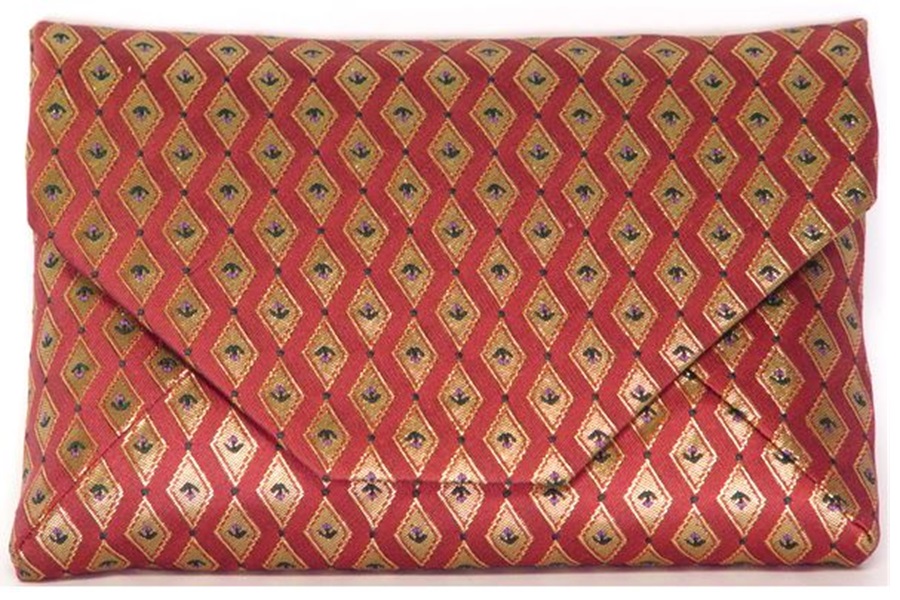おせちの原初「お雑煮」

謹賀新年
みなさま、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も宜しくお願いいたします。
お正月はいかがお過ごしでしょうか。
最近は元旦よりあいてるお店も多いようですが、元旦ぐらいは家でゆっくりとお節やお屠蘇をいただき、家族団欒でかるたなどいかがでしょうか。
ゆっくりしましょう、三元日。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
おせちの原初「お雑煮」
今年初めてのお話しは、元旦の朝に食べられたお雑煮について。
農耕民族として田畑を耕し、その実りを祝ってきた日本人。
五穀豊穣を祈り続けたその思いを象徴するものとしてお雑煮はあります。
神に捧げる精進料理。
それ故に、昆布でだしをひき、白味噌(それぞれで違いますが)で仕立てます。
なかみは野菜と穀類のみ。
直会の段になってはじめて削り節をかけていただきます。
地方ごとに違うお雑煮ですが、それぞれにいわれがあってのお雑煮。
たくさんの感謝の気持ちをこめて「いただきます」。
お雑煮の由来
お正月に食べるお雑煮の由来は古く、平安時代だと言われています。
餅は古くから農耕民族である日本人にとって、お祝い事や特別な「ハレの日」に食べる「ハレ」の食べものでした。
年神様に供えた餅や里芋、人参、大根などを、その年の最初に井戸や川から汲んだ「若水」と、新年最初の火で焚き込み、元旦に食べたのが始まりと言われています。
雑煮の語源は「煮雑(にまぜ)」と言われており、色々な具材を煮合せたことからきています。
祝い箸
お正月の三が日にお節やお雑煮を食べる時には「祝い箸」という両方が細くなったお箸を使います。
これは取り箸と食い箸の両方に使えるようにと・・・いうわけではないですよ。
一方を人が使い、もう一方は神さまが使う「神人共有」を表したものです。
このようにお水や箸にまで、こだわりがみられる昔からのお話しから、雑煮がいかにハレの日の食べものかがうかがえます。
(参考:oisixおせちより)
ありがとうございます
お正月には古から伝わる文化が習わしがたくさん詰まってます。
少し前まで、昭和の中ごろまでは、お家でお祖母さんが色々なことを教えてくれていましたが、今では私たちが知らないことばかり。
少しでも子供たちに素敵な和のことをお話しできるといいですね。
そこには先人たちの思いと感謝の心がたくさんふくまれているから。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
今年も和の素敵、何卒、宜しくお願いいたします。
(旧文 2014.01.01 再編成)
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld