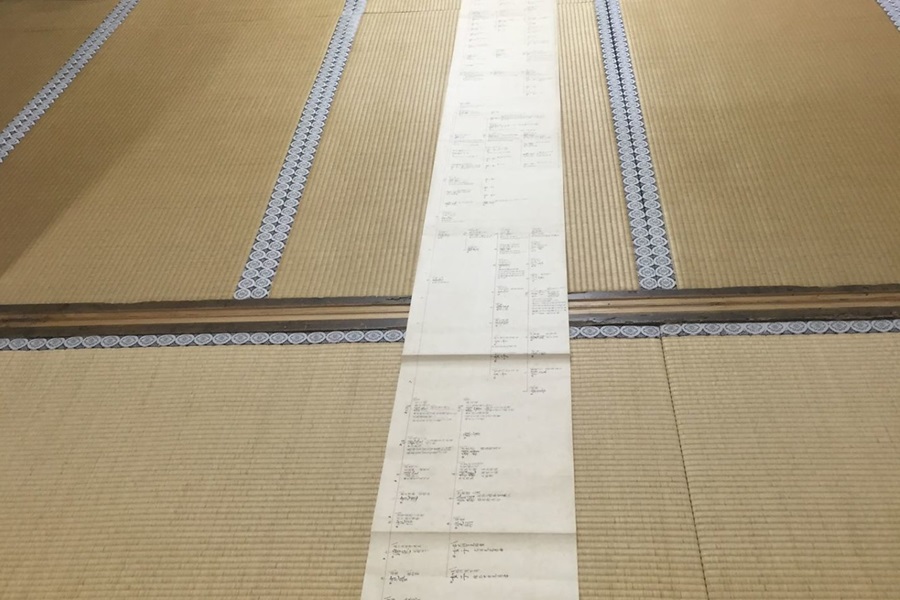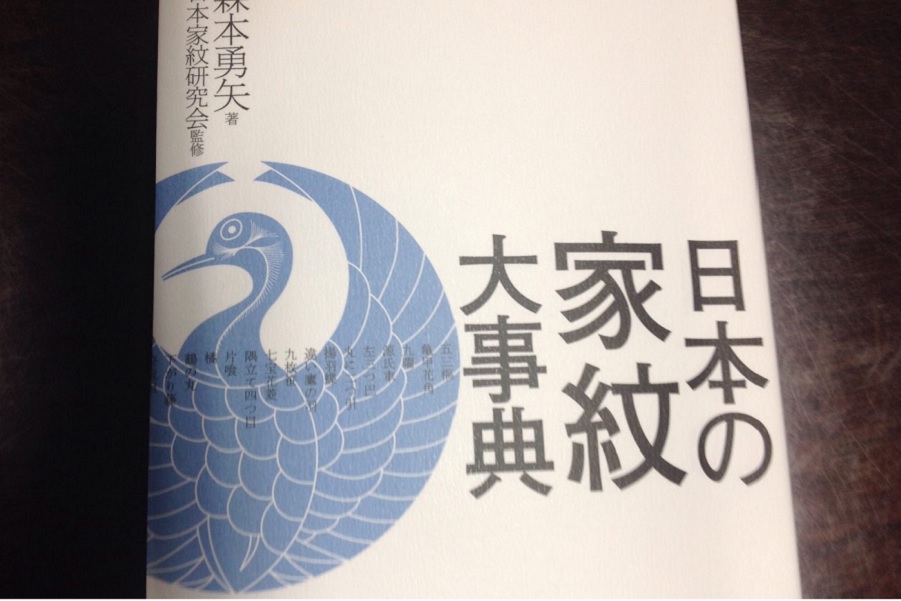今日は二十四節気の「処暑(しょしょ)」

秋のにおいが
こんにちは。
今日は「処暑」。
夕立のあとの透明な午後四時。
ほんのすこしだけ、秋のにおいがする。
葉っぱの裏側や、アスファルトの地面、枝のあいだの蜘蛛の巣のはしっこから、ちらりちらりと、すずしげな秋がのぞく。
—とはいっても、ほんの一瞬、あくる朝には、またたくまに、黄色い強い陽ざしに占領されて、かき消えてしまうのだけれど。
処暑。
暑さがすこしやわらぐ頃。
台風の季節が近づいています。
(本:「ひらがな暦」 著:おーなり由子)
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
七十二候
「綿柎開く(わたのはなしべひらく)」初候
(8月23日~27日ごろ)
綿の実を包む萼が開くころです。
種を包む綿毛をほぐし、綿の糸を紡ぎます。
綿の木は7月~8月に花を咲かせた後、蒴果と呼ばれる実をつけます。
その実がはじけて、一つの実からいくつか現れる白い繊維が種を包んだふわふわの綿花です。
「天地始めて粛し(てんちはじめてさむし)」次候
(8月28日~9月1日ごろ)
ようやく暑さが収まりはじめるころ。
夏の気が落ち着き、万物があらたまる時期とされます。
「粛」は縮む、しずまるという意味です。
立春から数えて二百十日目、台風がやってくる日とされてます。
「禾乃登る(こくものみのる)」末候
(9月2日~6日ごろ)
田に稲が実り、穂をたらすころ。
禾とは、稲などの穂先に生えている毛のことで、稲や麦、稗、粟などの穀物の総称でもあります。
のぎとも、のげとも呼ばれ「禾」の字は、もともと穂をたらした姿を描いた象形文字だったそうです。
処暑のいろは
秋の虫の声
空が高く空気も澄み、屋外で気持ちよく過ごすことができる頃。
夏休みももうじき終わりですが、こんな時こそ、自然に親しむ遊びをしましょう。
もうじき聞こえてくる秋の虫の声、日本人なら心地よさを感じるのでは。
今から1200年以上前に作られた万葉集にも、秋の虫の音を詠んだ詩が残されています。
鳴くのは求愛行動をするオスだけで、音は羽を擦り合わせることで出しています。
秋の虫の鳴き声、わかりますか?
マツムシは「チンチロリン」
スズムシは「リーンリーン」
コオロギは「キリキリキリ」ですよ。
外人さんが蝉の鳴き声はうるさいというのはなんとなくわかりますが、秋の虫の音色は何と感じるのでしょうね。
秋の味覚狩り
秋は果物が美味しい季節。
旧暦八月はブドウ、ナシ、リンゴなど、旧暦九月になるとカキ、キウイなどの収穫体験が楽しめます。
もぎたての果物の美味しいこと、週末にはいかがですか。
私はナシが何よりも大好き!
そして忘れてはいけないのが芋掘り。
9月に入ると各地の観光農園では芋掘りがはじまります。
土の中から掘り出した旬のサツマイモは、ビタミンCや食物繊維を多く含み、加熱してもビタミンCが壊れにくいのが嬉しいですね。
焼き芋も楽しんでください。
他にもイチジクはいかがですか。
漢字で「無花果」と書きますが花が咲かないわけではなく、実の中に詰まっている赤い粒々が花にあたります。
甘露煮やジャムにしてもおいしいですね。
台風の名称
このころから台風が多くなってきます。
今年は台風や豪雨による大きな被害が発生しています、くれぐれもお気をつけください。
平成12年から、アジア地域の台風には、アジア固有の名前140個を順番につけることになりました。
第1号は、カンボジアで象を意味する「ダムレイ」です。
日本からは星座からとった「テンビン」「ヤギ」などが登録されています。
また、1950年代以前は、「台風」は「野分」と呼ばれていました。
野の草を吹いて分けるところからついた「野分」は、「枕草子」や「源氏物語」などの古典にも登場します。
処暑のおいしい
すだち
酸味が強すぎず、さっぱりさわやかなすだち。
旬は8月、9月。
特産は徳島で、鍋物によし、焼き魚によしの、食欲を誘う香りと酸っぱさ。
ビタミンCもクエン酸も豊富で、肌の美容にも◎です。
鰯(いわし)
暑くなるにつれて脂がのり、おいしくなる鰯。
旬は6月~10月。
新鮮なものを握りや刺身、なめろうでいただくと旬を感じる青魚ですね。
無花果(いちじく)
江戸時代に入ってきたという無花果は、初めは薬用だったそうです。
旬は8月の終わりから10月にかけて。
実の中に咲かせる白い花は外から見えないので、花の無い果という名前になったそうです。
ありがとうございます
秋が深まると澄んだ青空が広がる日も多くなります。
そんな秋の天気を表す言葉が多くありますね。
「秋晴れ」はもちろん、秋本番のころを指す「秋深し」、秋から冬にかけての穏やかな日を指す「小春日和」など天気を表す言葉がたくさん。
「女心と秋の空」女心は、変わりやすい秋の空のように移り気だということ、しかし、もとは「男心」だったそうですよ。
「天高く馬肥ゆる秋」澄み渡る秋の空は高く感じられ、馬も食欲が増して立派に肥えるという意味で時候の挨拶にも使われます。
素敵な素敵な日本人の言葉遊びですね。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
夏から秋へ、いつの季節も楽しみがいっぱいですが、秋は何よりも食欲の秋!楽しみ---!
参考
本「日本の七十二候を楽しむ」 著:白井明大さん
虫の音はオルゴール 秋の夜長に
秋の季語と聞いて思い浮かぶのはこの5つ
人生、「勝った」「負けた」ではい。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld