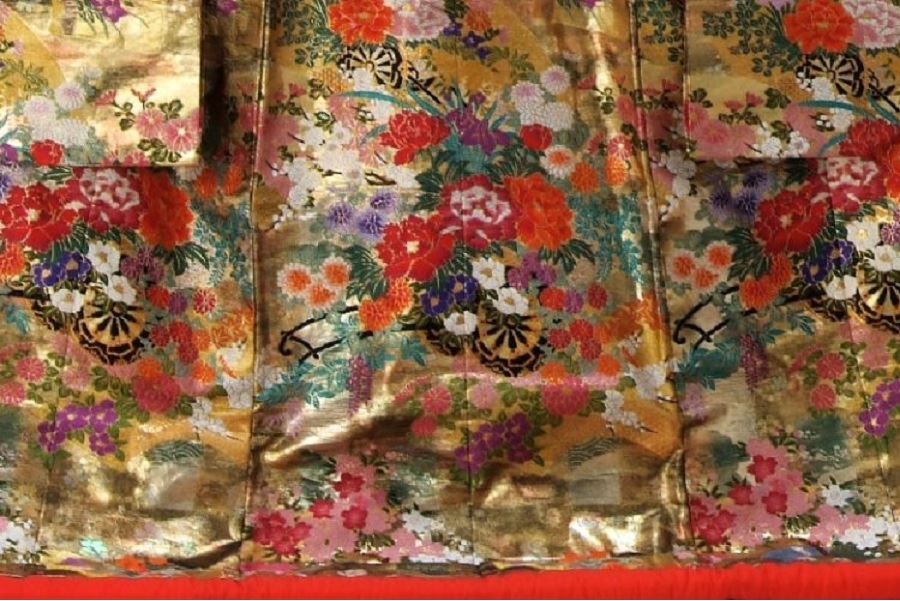「生きる」とは

白山先生の神道論集
こんにちは。
私が尊敬する白山先生の皇學館大学退任記念に書かれた「神道論集」。
今の時代だからこそ、多くの方に読んでいただきたい「和のこころ」が全編にわたって書かれています。
今日はその中の一つ「生きる」とはです。
ありがとうを世界中に
Arigato all over the World
清らかに
神道は「生きる」ということと深く関わっている。
「清らかに」とか「感謝して」とか「正直に」ということが、神道の目標として掲げられるのは、これらが、生きるための課題であるからである。
伊勢神道の教えである「正直者のこうべに神宿る」という説も、現実に生きていて神が宿るのであって、死後、神が宿るのではない。
おてんとう様が空の上から見ておられ、現実に生きている我々のなかにおける「正直者」に不幸はないか、と見守っていてくださるという説である。
このことは、「死後」を問題にする宗教と比較してみると、その違いがよくわかる。
たとえば、仏教を生んだ古代インドでは、現実に生きている社会がカーストという世襲の身分制のなかにあって生活が苦しく、環境も熱帯地方にあって悪く、生産性も伸びず、いろんな意味で八方ふさがりであった。
そのようなところから人々は死後に期待を寄せていたのである。
それで、仏教では死亡のことを「往生」という。
「往生」というのは、死ぬことであるのに、どうして生きるという文字を書くのであるか。
これは「往生」の「住」が過去という意味であり、生まれる前の過去において「極楽」にいたので、生きているうちに功徳(くどく)を積み、施しに心掛けたならば、死んだのち「極楽」に帰って、幸せに過ごすことができると説くのである。
キリスト教の場合においても、砂漠地帯のエルサレムにあって、生活難と被差別の苦しみのなかで、「天国(パラダイス)」に生まれかわりたいと、死後に希望を寄せたのである。
感謝して
したがって、「自主的に生きる」というテーマは、「生」に重点をおく神道において始めて成立する課題なのである。
さらにいえば、外来宗教の影響を受ける以前、この日本列島で暮らしていた我々の祖先が取り組んだ課題でもあった。
そのような取り組みの結果、土器発明の世界的な記録である縄文式土器や、高温で薄手に焼き上げる弥生式土器、自然や大地万物八百万神(やおよろずのかみ)と仰ぐ「神道」などを、つぎつぎに創造していった。
このような我々の祖先たちは、外来宗教の受容に際しても、まず「生」の教えとしての儒教を受け入れた。
儒教には、「生」の教えの部分、すなわち人と人との人間関係に関するものと、「死」の教えの部分、即ち儒教的祖先崇拝とがあるが、前者をより多く受け入れた。
仏教についても、僧侶が自らの学問として学ぶ南都六宗や、自らの修行を重んじる天台・真言両宗など、自律的な宗派を多く取り入れていった。
そして、誰から薦められるのでもなく、自主的に「神道」と集合させていった。
このように、「生きる」ことに対し深い関心をいだいてきた太古以来の我々の祖先が生み、そして育てたのが「神道」である。
人生を、やみくもに歩いているのと、自主的に歩いているのとでは、まるで違う。
目的もなく、人生を送っても、単なる暗中模索である。
日々、希望に満ち、可能性に胸ふくらませて、送りたいものである。
(文:皇學館大学退任記念「神道論集」 白山芳太郎著)
ありがとうございます
今の時代、「神道」という言葉がとても宗教的に誤解されてしまうことが多いですが、日本において過去からこのすべての自然に感謝する思いが神道なのです。
日本人の根本は「神道」だと思います。
先生のお書きになってるように、今をどう生きるかがとても大切ではないでしょうか。
それも目的を持って、しっかりと人生を送っていく。
みなさんに人生の目的はありますか。
私は、この「神道」、「和の心」が地球上で争いのなくなる唯一の教えだと思い、多くの人に知って頂ければと思っています。
文明の発達、経済の発展も大切かもしれませんが、もっともっと大切な八百万、あらゆる物に感謝する心がこれからの世の中、とても大切とされることを願っています。
今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この星が笑顔あふれる毎日となりますように。
Hope there will be a smile everywhere, every day.
これからの子供たちに幸せな世の中となりますように
Wish the world will be full of happiness with children.
#ありがとうを世界中に
#ArigatoAllOverTheWorld